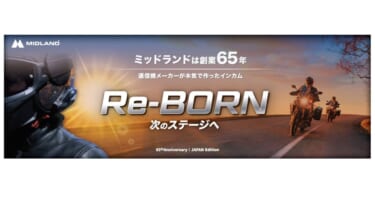愛車を選ぶ際、今までとは違うタイプに乗りたいなぁ……と思うこともあるだろう。そのとき、選んだ先に何が待っているのかを少し知っておくことで、より自分に合ったバイクを選べるかもしれない。オンロードモデルからアドベンチャーモデルに乗り換えたら、何がどうなるの?
●文:ヤングマシン編集部
見晴らしがいい!
オンロードバイクとアドベンチャー/オフロード/クロスオーバーなどの大きな違いのひとつは、走破性をよくするために車高が高くなっていること(最低地上高も同時に高まる)だろう。加えて、ステップの上に立って操縦すること“スタンディング”を想定した幅広のハンドルバーが高い位置にあるため、普通に着座しても上半身が直立したライディングポジションになる。
これらによってライダーの頭の位置が高くなり、さらにオンロードバイクほど顎を引いた姿勢にならないため、目線がかなり高くなったように感じるはず。クルマでいえば乗用車とSUVまたはクロカン車のような違いだ。
ミラーの位置も高くなる。乗用車より少し高いくらいか。
じゃあアドベンチャー/オフロード/クロスオーバーは全て同じようなポジションかというと、実はその中にも少しずつ差異がある。
アドベンチャーは上半身を直立させた傾向が最も強く、座って乗っても立って乗っても上半身の前傾は弱い。一般的にトレールモデルとかデュアルパーパスと呼ばれるものもハンドルバーはけっこう高めで、最近の大きなくくりではアドベンチャーにまとめられることもある。
クロスオーバーは、オフロードっぽい部分とオンロードっぽい部分を併せ持つハイブリッドタイプで、両方の要素がクロスオーバーしていることからそのような名で呼ばれる。基本的にアドベンチャーモデルに近いライディングポジションだが、オンロードモデルとベースを共有していることも多く、上半身は弱めの前傾に、また車高はそれほど高くない傾向だ。
オフロードはというと、競技専用車などの本格的なものになるほど車高は高くなり、シートを含む車体はスリムになる傾向。その中でも、スプリント寄りの出自のものはハンドルバーがやや低めで、やや上半身は前傾していて積極的なアクションがしやすいポジションに。耐久レース寄りになるとハンドルバーは高く手前に来ることになり、あまり大きなアクションをしなくてもいいようなリラックスしたポジションになる。細身のアドベンチャーモデルに近いとも言えるだろうか。
ついでに言うと、車高が高くて軽いバイクは横風の影響を受けやすくなるので、強風の際には少し注意が必要だ。
サスペンションが柔らかくて乗り心地がいい!
アドベンチャーモデルにもいろいろあるが、走破性を高めようとすればするほどサスペンションストローク/ホイールトラベルは長くなり、一般的なオンロードバイクが120mm前後であるのに対し、少なくとも150mm以上、中には250mm前後のモデルもある。
長いストロークを使って路面の凹凸や衝撃をいなすため、小さな入力でもよく動き、大きな入力では深くストロークすることで運動エネルギーを吸収してくれる。したがって、オフロード寄りのアドベンチャーモデルになるほどサスペンションはよく動き、印象としても「柔らかい!」「乗り心地がいい!」になる。
大型モデルなら2人乗りで荷物満載でも十分な乗り心地。
乗り心地はよくなるが、そのぶん動きも大きいため、ブレーキをかけるとつんのめるような気がしたりする。また、サスペンションの動きが大きいゆえに反力の発生までに時間もかかり、オンロードバイクに馴染んでいるとレスポンスが鈍い印象にもなりがちだ。
ちなみに、走破性を高めるためにはフロントホイールの大径化が有効で、これに長めのサスストロークが加わると、フロントタイヤが大回りするような印象になり、左右への切り返しなども緩慢に感じるかもしれない。これは路面の荒れやうねりをいなし、細かい凹凸などに左右されずに進んでいくために必要な特性なのだ。
地面が遠い!?
ここまででお気づきと思うが、アドベンチャー/オフロード/クロスオーバーモデルは総じて車高が高い。シート高もおのずと高くなり、地面との距離は開いていく。
とはいうものの、アドベンチャー系はスタンディングも考慮して細身に造られていることが多く、また前述のようにサスペンションもよく沈むため、単純に数値からイメージするよりは足着きに困らないで済むことも。足着き問題を解消するためには、縁石や路面のうねりをうまく使うといいかもしれない。
左のGSX-8Sはシート高810mm、右のVストローム800DEはシート高855mmだ。
ブレーキが利かないように感じる!?
オンロード寄りのクロスオーバーはオンロードバイクと変わらないブレーキを備えていることもあるが、オフロード成分が強まるほどに、ブレーキは絶対制動力よりもコントロール性を重視したものに変わっていく。
ダート路面でいきなり強い制動力を発揮してもロックしたり滑ったりしてしまうだけ。それよりは、滑り出す手前でしっかりとコントロールでき、またロックもしにくいような特性が歓迎されるからだ。
これに加え、長いサスペンションストロークによって、前につんのめる感じ(ノーズダイブ)が大きく、フロントサスが沈んだところで路面からの反力をライダーが感じる状態になるまで時間がかかり、ブレーキが利いているという実感が得られにくいから、という理由もある。
実際は強めにレバーへ入力すれば十分な制動力を発生してくれるので、安全性への心配は無用だ。
あくまでもオンロードバイクに比べて初期でガツンと利かないだけ。
意外と足元が濡れる
これはフロントフェンダーのタイプによるもので、タイヤの外周を覆うように配置されるダウンフェンダーならオンロードバイクと変わらないが、オフロード色の強いモデルが採用するアップフェンダーになると、フロントタイヤが巻き上げた水がライダーの足元に来るのを防ぐ機能があまり高くなく、シューズや膝周りが意外と濡れがち。長いサスペンションストロークに対応し、石や泥が舞い上がっても防いでくれるアップフェンダーだが、日常使いではダウンフェンダーのほうが優れている部分もあるのだ。
左のCL250はダウンフェンダー、右のCRF250Lはアップフェンダーだ。
転んでもダメージが少ない!
オフロード傾向が強いモデルになるほど、つくりがシンプルであることに加え転倒に備えた設計になっているので、転倒しても(多少の傷はつくが)ダメージは小さくて済むことが多い。
立ちごけや転倒の場面でバイクにしがみついたり立て直そうと頑張ったりすると、ライダーが余計に怪我をするリスクもあるので、早めに諦めてバイクを捨てて逃げるという選択も大事である。特にオフロードでは遠慮なくバイクを投げよう。
ナックルガード付きならレバーが折れる心配もあまりない。
まとめ
アスファルトに特化されたオンロードバイクは、日常使いやツーリングなどで何も困ることはなく扱いやすいが、ちょっと道を逸れてどこかに行きたいとか、環境の変化に左右されずに楽な姿勢で自由自在に乗りたい、災害時に役立つバイクを……。そんなふうに考えたことがあるなら、アドベンチャーやオフロードバイクを手に入れてみるといいかもしれない。今までとは違った楽しみが得られるに違いないし、改めてオンロードバイクのよさもわかってくる。理想はオン/オフの2台持ちだなぁ……なんて考えてしまって、バイクの魅力から抜け出せなくなるかも?!
※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
あなたにおすすめの関連記事
Vストローム250SX[56万9800円] vs Vストローム250[64万6800円] 2023年8月24日に発売されるスズキの新型モデル「Vストローム250SX」は、油冷単気筒エンジンを搭載するア[…]
【テスター:丸山浩】自身の主導団体"ウィズミー"会長/YouTubeチャンネル"MOTORSTATION TV"の司会/ヤングマシンのメインテスターを務めつつ、オンオフ2輪4輪問わずレースに参加するモ[…]
’23 スズキ Vストローム800DE 概要 ’23 スズキ Vストローム800DE スタイリング ’23 スズキ Vストローム800DE エンジン ’23 スズキ Vストローム800DE シャーシ […]
ホンダCRF250L 概要 [◯] 規制適合後も走り不変。オンロードも楽しいぞ 今年5月にホンダからスクランブラースタイルのCL250が発売された。偶然にも今回試乗したCRF250Lと価格が同じで、水[…]
1位:スズキ Vストローム250 146票/981票 '17年の登場時は圏外ながら近頃は3位に着け、ついに初優勝! ツインの心臓は実用域のトルクが豊か。旅の相棒として評価が高い。 投稿者の声【旅性能が[…]
最新の関連記事(新型アドベンチャー/クロスオーバー/オフロード)
大型アドベンチャーバイク『CRF1100L Africa Twin(アフリカツイン)』に新展開! 2016年にCRF1000L Africa Twinシリーズとして復活を果たしたのち、2019年には排[…]
2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]
前年のマイナーチェンジでデザインも装備も最新世代 ホンダが2026年型「X-ADV」を発表、カラーリング変更とともにモノトーンとトリコロールそれぞれ1万6500円プラスの価格改定した。フラットダートく[…]
3気筒エンジンがまさかの14psアップ 2026年モデルでまず注目したいのは、やはりエンジン。 660cc並列3気筒という形式自体は従来と同様であるが、新型では最高出力が従来の81psから一気に95p[…]
前輪19インチでオンロードに軸足を置くアドベンチャースポーツES ホンダは、前19/後18インチホイールのアドベンチャーモデル「CRF1100Lアフリカツイン アドベンチャースポーツES DCT」の2[…]
最新の関連記事(ビギナー/初心者)
きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]
徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]
改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]
「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]
「一時停止違反」に、なる!/ならない!の境界線は? 警察庁は、毎年の交通違反の取り締まり状況を公開しています。 最新となる「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等につい[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]
X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]
最新の投稿記事(全体)
BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]
RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]
これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]
つながらなければ意味がない!「MIDLAND Re-BORN(リ・ボーン)」を実施! 創業65周年という節目を迎え、MIDLAND(ミッドランド)が掲げたスローガンは「MIDLAND Re-BORN([…]
リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]
- 1
- 2