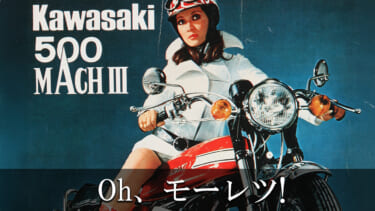元MotoGPライダーの青木宣篤さんがお届けするマニアックなレース記事が上毛グランプリ新聞。ヤングマシン本誌で人気だった「上毛GP新聞」がWEBヤングマシンへと引っ越して、新たにスタートを切った。1997年にGP500でルーキーイヤーながらランキング3位に入ったほか、プロトンKRやスズキでモトGPマシンの開発ライダーとして長年にわたって知見を蓄えてきたのがノブ青木こと青木宣篤さんだ。最新MotoGPマシン&MotoGPライダーをマニアックに解き明かす!
●監修:青木宣篤 ●まとめ:高橋剛 ●写真:Ducati, Michelin
ドゥカティファクトリーには受難のオープニングラップ
MotoGP第11戦カタルニアGPは、荒れたオープニングラップとなった。エネア・バスティアニーニ(ドゥカティ)が1コーナーへのブレーキングで突っ込みすぎて転倒。1番イン側にいたものだから、ドミノ倒し的に他のライダーたちを道連れにしてしまった。
その直後、トップを走っていたフランチェスコ・バニャイア(ドゥカティ)がハイサイドで転倒。ブラッド・ビンダー(KTM)に足を轢かれ、大きな負傷は免れないかと非常に心配だったが、幸い骨折もなかったそうで、胸を撫で下ろした。
左写真、左端にいるのが1コーナーの多重クラッシュを作ってしまったバスティアニーニ選手。右写真はその直後で、後続はクラッシュを避けたため列がバラバラに。そして先頭を走るバニャイア選手の転倒はこの直後だった。
最近のMotoGPは、スタート直後のクラッシュがかなり目立つ。「空力パーツによって操作性が重くなったからではないか」という意見も見聞きするが、ワタシの経験上、そこまで影響があるとは思えない。それよりもホールショットデバイスの進化によって、1コーナーへの進入スピードがかなり高まっていることが大きな原因ではないだろうか。
スタート練習の写真ではないが、加速時にこれだけリヤ車高を下げている。スタート時にはフロントも下げるので相当なシャコタンに見えるようになる。
決勝以外の走行セッション終了後、各ライダーが裏ストレートなどでいったん止まり、スタート練習する姿を見たことがある人も多いだろう。でもあれはあくまでもスタートする瞬間の練習だけ。他車も含めた1コーナーへの進入は、実際のレースでしか経験できない。
そこへ来て、スタート時に車高を下げるホールショットデバイスにより1コーナーへの進入スピードが高まれば、ブレーキングポイントを見誤ってオーバースピードになる可能性は上がる。デバイスがない時の感覚で1コーナーに進入すると、思ったよりもスピードが高すぎて、減速し切れずに突っ込みすぎてしまう、ということだ。
解決策としてひとつ提案するなら、スターティンググリッドの間隔をもう少し広げたらどうだろう。グリッドの間隔は、実はしばしば変更されている。ワタシがGPを走り出した頃は、フロントロウ、セカンドロウという言葉通り、オフセットすることなく横一線に4台ずつが並んでいたものだ。
’96年頃には、横一線だった4台がオフセットして並ぶようになった。’04年には1列が3台になった。’06年には1列3台の1台ごとのオフセット幅が、1.5mから3mにまで拡大された。つまり予選3番手のライダーは、ポールポジションのライダーより6m後方からのスタート、ということになる。列ごとの間隔はずっと9mだ。
これらの措置は安全面を考慮してのことだが、今のMotoGPマシンはさらに速くなっている。スターティンググリッドのオフセット量や列の間隔はもっと広げてもいいのではないか、と思う。スタート直後の1コーナーの混雑を少しでも緩和し、クラッシュを防げるのではないか。
人間が反応できない0.1秒に進む距離とは
ムジェロ名物の長いストレートでは毎年のように最高速記録が更新されていく。MotoGP元年の2002年はヤマハYZR-M1×マックス・ビアッジによる322.81km/hだった。
そしてもうひとつ、根本的な解決策として、速くなりすぎたMotoGPマシンに何らかの制限・制約を設けることも考えていい気がする。今年、イタリアGPが行われたムジェロサーキットでは、KTMのブラッド・ビンダーが366.1km/hという史上最高速をマークした。
ちなみに四輪F1での史上最高速は、’05年にファン・パブロ・モントーヤがイタリア・モンツァサーキットでマークした372.6km/hとされている。しかし近年はレギュレーションにより速度が抑えられており、同じモンツァでも’22年の最高速はニコラス・ラティフィの347.8km/h。約25km/hスピードダウンしている。
ワタシ自身は、ハードウェアの進化はモータースポーツの大きな魅力のひとつだと思っている。速さを求めるからこそ登場する新しいテクノロジーには、いつもワクワクしてきた。ただ、やはり限度というものがある。
人間の反射速度(脳からの指令で筋肉が動くまでの速度)は概ね0.2秒前後、トップアスリートでも0.1秒以上が限界と言われている。だから陸上競技では、スタートの合図音から0.1秒以内に反応した場合は、フライングと見なされる。「音を聞く前にスタートした」という判断によるものだ。
超人的なマシンコントロールをするMotoGPライダーたちだが、それでも限界はある。
この0.1秒、モータースポーツに当てはめるとかなり長い時間だ。100km/hで走行中のバイクは、0.1秒で約2.7mも進む。200km/hなら約5.5m、300km/hなら約8.3mにもなる。人間の反射速度が追いつけない0.1秒で、これだけ進んでしまうのだ。
もちろんライダーは状況を先読みし、予測しながら操作しているので、実際にこれだけの距離的な遅れが生じるわけじゃない。しかし混戦ともなれば避けきれなくてもおかしくない。
MotoGPマシンの排気量は、今の1000ccから850ccへの引き下げも検討されている。しかし’07年、それまでの990ccから800cc化した時、トップスピードは抑えられたもののコーナリングスピードがかなり高まってしまい、「かえって危険」と、結局’12年に1000ccに戻った経緯がある。
モータースポーツらしいハードウェアの進化は見たい。でも、安全性はできるだけ高めてほしい。非常に残念なことだが、将来ある若手日本人ライダーがレース中のクラッシュで立て続けに命を落としてしまった。アジアロードレース・ASB1000クラスに参戦していた埜口遥希くんは、22歳。全日本ロードレース・JSB1000クラスの谷本音虹郎くんは23歳だった。
MotoGP・オーストリアGPのオープニングラップの多重クラッシュとバニャイアの転倒も、本当にぎりぎりのところで誰もが無事で済んだ(エネア・バスティアニーニは骨折してしまったが……)。奇跡に頼ってばかりいるのではなく、できる限りの安全措置が必要な時期がきている気がする。
※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
あなたにおすすめの関連記事
出力アップはもちろん、空力&ライドハイトデバイスにより最高速は伸び続ける 最新のMotoGPマシンは、300psに迫る(クランク軸だと超えている?)パワーを出しつつ、そのパワーを空力デバイスと電子制御[…]
延期は決まったものの、空路閉鎖によりチャーター便の行方は…… となると、本来は日本GPの翌週に開催予定だったスペインGPは開催されることになるわけで、今度は日本にいる我々のような日系メーカーのスタッフ[…]
温まりやすくスライドコントロールがしやすいタイヤを 2012年のMotoGPは、使用するマシンの排気量上限がそれまでの800ccから1000ccに拡大されたことが、もっとも大きな変更点。もちろん各メー[…]
取材を忘れて、見入ってしまう迫力 モビリティリゾートもてぎ内のホンダコレクションホールでは、2023年7月22日からMotoGP日本グランプリの決勝レース日となる10月1日まで、「二輪世界グランプリ […]
ヤマハは、2023年限りでモンスターエナジーヤマハMotoGPチームをフランコ・モルビデリ選手が去り、新たにアレックス・リンス選手が2024年から加入することを明らかにした。来シーズンはファビオ・クア[…]
最新の関連記事([連載] 青木宣篤の上毛GP新聞)
MotoGPライダーのポテンシャルが剝き出しになったトップ10トライアル 今年の鈴鹿8耐で注目を集めたのは、MotoGPおよびスーパーバイク世界選手権(SBK)ライダーの参戦だ。Honda HRCはM[…]
15周を走った後の速さにフォーカスしているホンダ 予想通りと言えば予想通りの結果に終わった、今年の鈴鹿8耐。下馬評通りにHonda HRCが優勝し、4連覇を達成した。イケル・レクオーナが負傷により参戦[…]
電子制御スロットルにアナログなワイヤーを遣うベテラン勢 最近のMotoGPでちょっと話題になったのが、電子制御スロットルだ。電制スロットルは、もはやスイッチ。スロットルレバーの開け閉めを角度センサーが[…]
φ355mmとφ340mmのブレーキディスクで何が違ったのか 行ってまいりました、イタリア・ムジェロサーキット。第9戦イタリアGPの視察はもちろんだが、併催して行われるレッドブル・ルーキーズカップに参[…]
運を味方につけたザルコの勝利 天候に翻弄されまくったMotoGP第6戦フランスGP。ややこしいスタートになったのでざっくり説明しておくと、決勝スタート直前のウォームアップ走行がウエット路面になり、全員[…]
最新の関連記事(モトGP)
今のマルケスは身体能力で勝っているのではなく── 最強マシンを手にしてしまった最強の男、マルク・マルケス。今シーズンのチャンピオン獲得はほぼ間違いなく、あとは「いつ獲るのか」だけが注目されている──と[…]
本物のMotoGPパーツに触れ、スペシャリストの話を聞く 「MOTUL日本GPテクニカルパドックトーク」と名付けられるこの企画は、青木宣篤さんがナビゲーターを務め、日本GP開催期間にパドック内で、Mo[…]
欲をかきすぎると自滅する 快進撃を続けている、ドゥカティ・レノボチームのマルク・マルケス。最強のライダーに最強のマシンを与えてしまったのですから、誰もが「こうなるだろうな……」と予想した通りのシーズン[…]
2ストGPマシン開発を決断、その僅か9ヶ月後にプロトは走り出した! ホンダは1967年に50cc、125cc、250cc、350cc、そして500ccクラスの5クラスでメーカータイトル全制覇の後、FI[…]
タイヤの内圧規定ってなんだ? 今シーズン、MotoGPクラスでたびたび話題になっているタイヤの「内圧規定」。MotoGPをTV観戦しているファンの方なら、この言葉を耳にしたことがあるでしょう。 ときに[…]
人気記事ランキング(全体)
キジマ(Kijima) バイク スマートディスプレイ SD01 5インチ キジマの「SD01」は、スマートフォンとWi-Fi(2.4GHz)で接続し、スマホのマップをナビ表示できる5インチのモーターサ[…]
次世代を見据えた新技術を随所に投入 ’73年から開発が始まったZ650は、当初は”Z1ジュニア”と位置づけられていた。とはいえ、単なるスケールダウンをヨシとしない開発陣は、次世代を見据えた新技術を随所[…]
メカもライテクもこの1台に教わった 原付というジャンルが、若者にとって比較的手軽にモータースポーツを楽しむ道具として浸透していく中、別の意味で趣味性の高いアイテムとして発展したのがレジャーバイクと呼ば[…]
超えるべき指針はトライアンフ・ボンネビル ’54年に第一号車として、2スト60ccスクーターを手がけたカワサキが、2輪事業に本腰を入れるようになったのは’60年代に入ってからである。 もっとも、当初の[…]
新型CBは直4サウンドを響かせ復活へ! ティーザー画像から判明したTFTメーターとEクラッチ搭載の可能性 ホンダは中国がSNS『微博』にて、新たなネオクラシックネイキッドのティーザー画像を公開したのは[…]
最新の投稿記事(全体)
お風呂やシャワーを怠ることは「こりの重症化」の原因に? ピップエレキバンシリーズで知られるピップ株式会社が今回実施した調査によると、季節問わず、仕事や勉強で疲れたり時間がない等の理由で、ついお風呂やシ[…]
新色パールレッドだけでなくホワイトとブラックも色味新たに スズキは、原付二種スクーターの「アヴェニス125」をカラーチェンジ。2022年の発売以来、初めての変更を受けるアヴェニス125だが、ニューカラ[…]
シュアラスターの「バイク洗車図鑑」 バイクが違えば洗い方も変わる! 車種別の洗車情報をお届けするシュアラスターの「バイク洗車図鑑」。今回はホンダさんの「GB350」を洗車します。 2021年に登場した[…]
「CW-X」と大谷翔平選手が“挑戦する人”を応援 本プロジェクトは、“挑戦する人”を応援したいと考える「CW-X」と大谷翔平選手が共同で企画。大谷選手も愛用する[ボディバランスアップタイツ]約5000[…]
アイポートの広いフルフェイス:BULLITT CRF 1970年代のBELL STAR(ベル・スター)ヘルメットを彷彿とさせるクラシカルなデザインで、どんなバイクにもマッチするだろうスリムなシルエット[…]
- 1
- 2