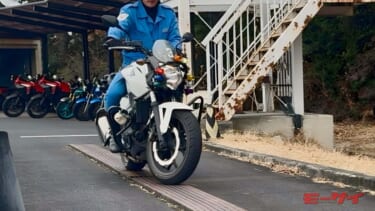●文:モーサイ編集部
第1回鈴鹿8耐(1978年)のカテゴリーは大雑把に2つだった
「国際格式の耐久レースを日本にも!」と、1978年7月に初開催された鈴鹿8時間耐久レース。国際格式というとレギュレーションがかなり厳しいようなイメージを抱いてしまうが、第1回鈴鹿8耐には、小排気量ストリートバイクから世界で活躍したワークス耐久レーサーまでがグリッドに並び、異種格闘技のような世界が繰り広げられたのである。
もちろんレギュレーションはあった。マシンは2つのクラスに分けられ、まずひとつはストリートバイクをベースにした“シルエットタイプ”。排気量は250cc〜1200ccで改造範囲は少なく、排気量拡大NG、キャブレター径はスタンダード同様、タンクもスタンダードのものの装着が義務付けられるというもの。
そしてもうひとつ、上記の改造範囲を超えたものや、純粋なレーシングマシンを含む240cc〜1000ccのマシンを“プロトタイプ”と分類した。
しかし逆に言えば、上記の条件にさえ合っていれば参戦OKというもので、その結果、ミラーとウインカーを外しただけのようなストリートバイク/極限までチューニングを施したリッターバイク/オリジナルフレームを用いたワンオフカスタムバイク/ワークスレーサー…、それらが一堂に走るレースとなったのである(ライダーへの間口も広く、ノービスライセンスで参戦可能だった)。
結果はご存じの人も多いだろう。優勝候補と目された、ヨーロッパで大活躍していたホンダの耐久レーサー・RCB勢が全車リタイア。勝利を掴んだのは、ストリートバイクを極限まで改造したマシン=ヨシムラGS1000だった。その事実が象徴するように、第1回鈴鹿8耐は改造車が輝きを放ったレースという魅力もあったのだ。
とくに、今の目で見ると異質な存在に思えるマシンを当記事では紹介したい。1000cc空冷6気筒のホンダCBXと、ヤマハXS750スペシャルの2台である。大排気量6気筒バイクと、アメリカンバイクがサーキットを走る勇姿をぜひご覧いただきたい。
アメリカンホンダのCBX(1000):参戦マシン唯一の6気筒車
まさに第1回鈴鹿8耐が行われた1978年に、輸出専用車として登場したホンダCBX(1000)。見る者を圧倒する巨大なエンジンは、1047ccの空冷4サイクルDOHC4バルブ並列6気筒。第1回鈴鹿8耐参戦マシンのなかで、唯一の6気筒エンジン車であった。
このCBXは、アメリカンホンダからのエントリーで、チーム監督は耐久レースの名手・菱木哲哉氏。ビキニカウルの装着/大型オイルクーラーへの換装/サスペンションの変更などは行われているが、参戦マシンはスタンダードの姿を色濃く残していた……
※本記事は2021年10月28日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
モーサイの最新記事
河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]
クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]
未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]
車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]
今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]
最新の関連記事(バイク歴史探訪)
ボクサーエンジンの誕生、最強バイクとして世界中でコピー BMWといえば、2輪メーカーとしてスーパーバイクS1000系からボクサーのRシリーズなど、スポーツバイクで世界トップに位置づけられるメーカーだ。[…]
軽二輪の排気量上限=250ccスクーター登場は、スペイシー250フリーウェイから ホンダPCXやヤマハNMAXなど、ボディサイズは原付二種クラスでありながら排気量150〜160ccの軽二輪スクーターを[…]
1965年までは“クルマの免許”に二輪免許が付いてきた 80歳前後のドライバーの中には、「ワシはナナハンだって運転できるんじゃよ、二輪に乗ったことはないけどな(笑)」という人がいる。 これは決してホラ[…]
ホークシリーズ登場後、すぐにホークIIIを投入。“4気筒+DOHC”勢に対抗したが… 1977年の登場から1〜2年、扱いやすさと俊敏さを併せ持つホークシリーズは一定の人気を獲得したが、ホークII CB[…]
生産台数の約7割を占めた、ハーレーの“サイドカー黄金時代” 1914年型のハーレー初のサイドカー。ミルウォーキーのシーマン社がカー側を製作してハーレーに納入。マシン本体にはカー用のラグが設けられており[…]
最新の関連記事(レース)
現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]
SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]
“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]
開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]
短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]
人気記事ランキング(全体)
日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]
7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]
GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]
ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]
グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]
最新の投稿記事(全体)
機能が形を作るとは、まさにこのこと! もはや「走る芸術品」という言葉すら生ぬるい。第7世代へと進化したパニガーレV4の姿は、単なる美しさの追求ではなく、時速300km/hオーバーの世界で戦うための「空[…]
ドラレコの「配線地獄」はもう終わり! 車やバイクに乗るなら、もはやドライブレコーダーは必須装備だ。しかし、「面倒極まりない配線処理」で購入に踏み切れない方も多いのではないだろうか。ショップに頼めば工賃[…]
【第1位】ワークマン×『葬送のフリーレン』第2期コラボTシャツが登場! 人気アニメ「葬送のフリーレン」とワークマンの異色コラボが堂々の1位を獲得した。980円という驚愕の価格ながら、ふだん着やツーリン[…]
エモーショナルな体験ができる冒険ラリー オートバイ冒険家・風間深志氏が発案した日本最大級のツーリングラリー「SSTR2026(サンライズ・サンセット・ツーリングラリー2026)」が、2026年5月23[…]
久々に『コーナリング』と真剣に向き合うことになりました。 HondaGO BIKE LABでちょくちょくバイクに乗った感想文などをお届けさせてもらっている私(北岡)ですが、実のところ私の経歴というのは[…]


![第1回鈴鹿8耐(1978年)|[バイク歴史探訪] 第1回鈴鹿8耐、驚異の参戦マシン【6気筒CBXやアメリカンXS750スペシャルが走っていた】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/02/th_01-1_START-768x506.jpg)
![ホンダCBX(1000)|[バイク歴史探訪] 第1回鈴鹿8耐、驚異の参戦マシン【6気筒CBXやアメリカンXS750スペシャルが走っていた】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/02/th_06-3-CBX-768x503.jpg)