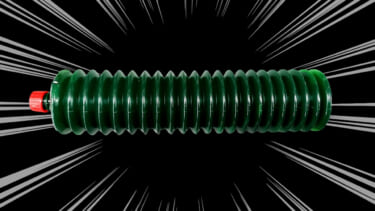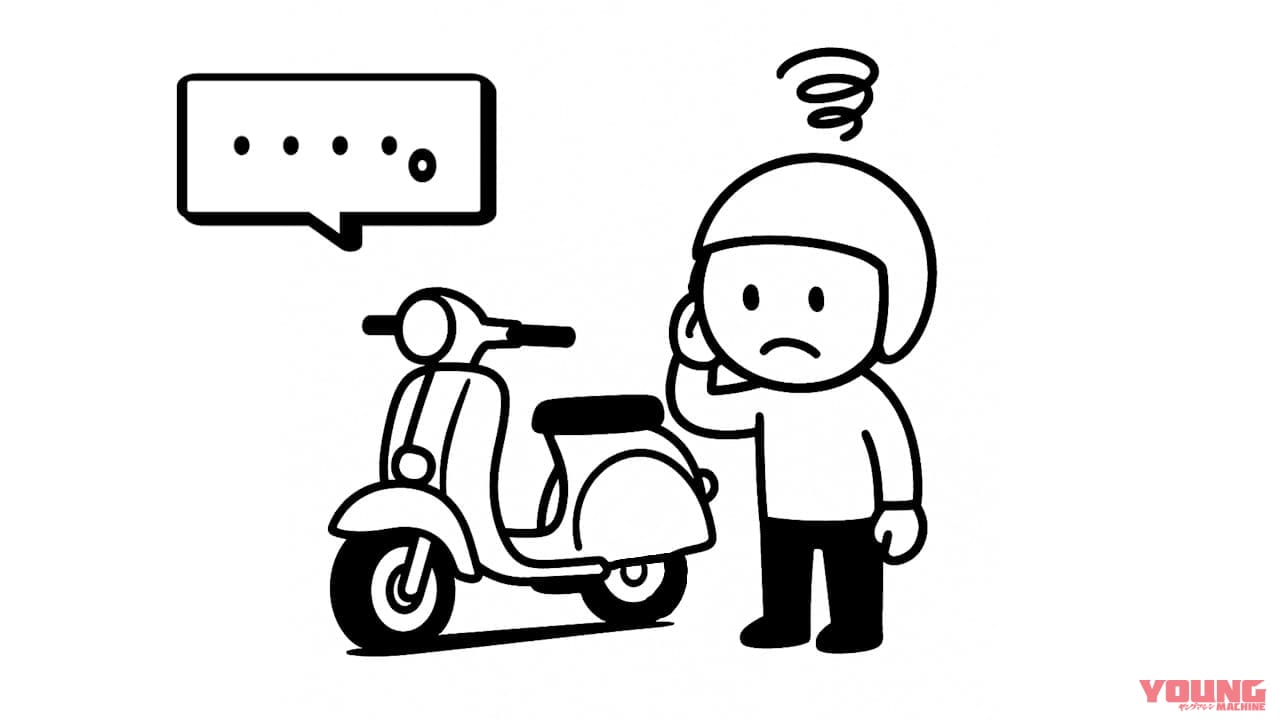
ちょっと久しぶりにスクーターに乗ろうと思ったら、エンジンがかからない…って、あるあるですよね〜!っていうか、今まさにそんな状況に直面しているワタシ。古いキャブレター仕様の原付にありがちな始動不良を解決する、古き良き?始動方法をやってみましょう〜!
●文:ヤングマシン編集部(DIY道楽テツ)
どうする? スクーターのエンジンがかからない
※これはまさに、筆者が直面した実話です。我が家のスクーター(TODAY)に乗ろうと思って、車庫から引っ張り出しました。ちょっと久しぶりですね。エンジンをかけるのは半年ぶりぐらい。
目覚めるかなーと思って、セルスターターを回します。キュルルルルルルルルルルルル…。おっと、エンジンに火が入りませんね。
しばらく放置しておくとエンジンがかかりにくくなる症状は、とくにキャブレター仕様のバイクにはありがちな現象ですよね。これは、フロートチャンバー内のガソリンが少量であるがゆえに劣化しやすく、爆発しにくくなるからと言われています。
これはエンジン不動状態に至る手前の状態で、まだエンジン始動が可能な状態がほとんど。かと言って、このままセルスターターを回していてはバッテリーが上がってしまって手間ばかり増えてしまうので、キックスタートに移行してみましょうか。
困ったときのキックスターター!
空キックからの始動方法
ここからは、エンジンがかかりにくい時のちょっとしたコツをご披露してみたいと思います。まず、キーをオフにします。
そして、キックペダルをちょっと強めに「空キック」を5回ほど踏み込みましょう。ここでキーをオンにして思いっきりキックペダルを踏み込めば、かなりの確率でエンジンが始動します。
これはあくまでも筆者の経験談なのですが、スクーターに限らず、他の車種でも似たような事例が多々ありますので、概ね共通の現象と考えられます。
これは疑似的にチョークを引いたような状態を作り出しているのですが、キーをオフにしておくことによって、スパークプラグの火花を止めることができるので「ちょっと爆発するけどエンジン始動に至らない」というスカ爆発を防ぐことで、燃焼室の中に生ガスをたっぷり溜め込むというイメージです。
もしそれでも始動しない場合
この「空キック方法」を4~5回繰り返してもエンジン始動しなかった場合、燃焼室の中のガソリンが多くなりすぎて、いわゆる「カブった」状態になっている可能性があります。そしたら、今度はまったく逆の方でアプローチしてみましょう。キーはオンにして、
アクセルを全開にして、思いっきりキックします(できれば複数回)。これはさっきと正反対。アクセルを全開にしてキックを踏むことで、ガソリンの量をできるだけ抑えた「ほぼ空気だけ」をエンジンに送り込む方法です。
自分でも不思議ではあるのですが、これでエンジンかかることも多いのですよ、いやホントに。
以前乗っていた大排気量の空冷シングルエンジンなどでは、始動に失敗してスパークプラグをかぶらせることが多かったのですが、このアクセル全開方法でエンジンかかることがよくありました。これらの方法はあくまでも経験談であり、メーカー推奨でもなければ、裏技でもないし、バズった方法でも何でもありません。
だけど、これでエンジンかかっちゃうんだからしょうがない…。
古いバイクならではの「儀式」
今回紹介した方法は、キックスターター装備が前提なので、現代のバイクにはほとんど使えない方法ではあります。だけど今や古くなってしまったバイクたちは、とくに冬の時期などはエンジン始動に苦労するという話はいくらでもありましたよね。
不思議なもので、同じ車種でもバイク個体ごとの「始動のクセ」みたいなものがあって、それをライダー達は「儀式」と呼んでました。
古いバイクに興味がある若い方達もいらっしゃると思いますが、そんなバイクの癖を見つけて「儀式」とドヤるのも楽しいかもしれませんよ♪
この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただきありがとうございました~!
私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の関連記事(メンテナンス&レストア)
鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]
軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]
怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]
グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]
徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]
最新の関連記事(ビギナー/初心者)
車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]
きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]
徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]
改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]
「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]
人気記事ランキング(全体)
簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]
型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]
初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]
EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]
異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]
最新の投稿記事(全体)
華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]
スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]
MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]
柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]
左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]
- 1
- 2