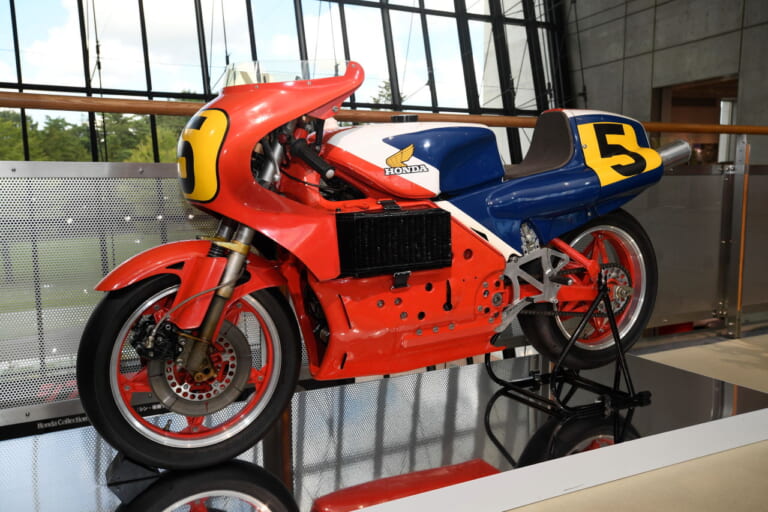写真を撮影したのはモビリティリゾートもてぎ内のホンダコレクションホールなので、メインとなるのはホンダ。ただし当連載では他メーカーも含めて、現代の視点で、1980年代以前に生まれた旧車の素性を振り返ってみたい。なお、展示内容はリニューアル前のものだ。
●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:富樫秀明 ●外部リンク:ホンダコレクションホール
2ストパラツインと4ストVツインの戦い
前任となるRD250の最高出力/乾燥重量が30ps/152kgだったのに対して、RZ250は35ps/139kgという数値を公称。1980年発売。
既存のRDシリーズから劇的な進化を遂げる形で、1980年に登場した2ストパラレルツインのヤマハRZ250(と兄弟車の350)が、2輪の歴史を語るうえで欠かせない名車であることに、異論を述べる人はいないだろう。何と言ってもRZは、1970年代末に消えかかっていた2ストロードスポーツの火を再燃させ、以後の2ストレーサーレプリカブームの基盤を作ったモデルなのだから。
VT250Fの最高出力/乾燥重量は35ps/149kg。この数値をどう感じるかは人それぞれだが、前任のスーパーホークが26ps/173kgという事実を考えれば、劇的な進化だった。初代モデルは1982年6月発売から実質7か月で3万台以上売れ、マイナーチェンジ後はさらに販売台数を伸ばし、1985年にはシリーズ累計10万台達成記念モデルも限定発売された。
では現役時代のRZ250と熾烈なバトルを繰り広げたライバル車、1982年にホンダが発売した4ストVツインのVT250Fが、世間で同等の評価を得ているのかと言うと……。それはなかなか微妙なところで、昨今ではVTシリーズに対して、エントリーユーザー向け、バイク便御用達、などという印象を抱いている人が多い気がする。
VT250Fの前後ホイールはホンダ独自のコムスターで、フロントは当時の流行だった16インチ。インボード式ブレーキディスクは、CBX400Fから継承したメカニズム。
ただし筆者としては、VT250FにはRZ250と互角、見方によってはRZ250以上の革新性が備わっていたと感じているのだ。と言うより、1980年代初頭をリアルタイムで体験したライダーなら、現在の2台の評価の差に疑問を感じているんじゃないだろうか。いずれにしても以下に記す各車の特徴を読めば、VT250Fの資質がRZ250に負けず劣らずだったことが理解していただけるはずだ。
各車各様の姿勢でレーサーの技術を転用
水冷化が図られても、RZ250が搭載する2ストパラレルツインのボア×ストロークは前任のRD250と同じ54×54mm。吸気はピストンリードバルブ式で、排気デバイスは装備しない。
まずはRZ250の特徴を記すと、筆頭に挙がるのは市販レーサーTZ250から継承したエンジンの水冷機構とモノクロス式リアサスペンション。とはいえ、パワーユニットの振動を緩和するオーソゴナルマウント、後端を跳ね上げたチャンバー、ヘッドパイプとスイングアームピボットを直線的に結ぶことを意識したフレーム、一体感を重視した外装部品、火炎をイメージしたキャストホイールなども、当時としては革新的な要素だったのである。
1973年から発売が始まったTZ250は、当初から水冷パラレルツインを搭載。モノクロス式リアサスペンションの採用は1976年から。写真は1979年型。 ※写真:ヤマハ発動機
もちろん革新的という意味では、VT250Fもまったく負けてはいなかった。ビキニカウル、フロント16インチ、ブーメランコムスターホイール、インボード式ブレーキディスク、リンク式リアサスペンション、RZ250以上にヘッドパイプとスイングアームピボットを直線的に結んだフレームなど、見どころ満載だったのである。ただしやっぱり、このモデルの最大の注目要素はエンジンだろう。既存の日本製4スト250ccが空冷並列2気筒か単気筒の二択だったのに対して、VT250FはGPレーサーNRの技術を転用した、水冷Vツインを搭載していたのだから。
現代の視点で考えても、VT250Fが搭載する水冷90度Vツインは、250ccクラスでは貴重なエンジン。初代で35psだった最高出力は、1984年型で40ps、1986年型で43psに向上。
1980年代初頭の250ccの基準で考えるなら、水冷Vツインというだけで十分に革新的だったものの、現代の視点でVT250Fを見て感心するのは、Vバンク間=中央吸気・前後排気+ダウンドラフト式キャブレターを採用したこと。そういった構成は、同時代のホンダVFシリーズやヤマハXZ400/500なども同様で、ハーレーダビッドソンは大昔から中央吸気・前後排気が定番だったけれど、VT250Fのエンジンからは“4ストで2ストを打ち負かす‼”という、ホンダの気概がビンビン伝わって来たのだ。
1979年から世界GP500への参戦を開始した4ストV4のNR。楕円ピストンや8バルブはさておき、この車両のエンジンを縦方向に半分にするという発想が、VT250Fの原点だった。
どちらも2輪の歴史を語るうえで欠かせない名車
RZ250のメーターはオーソドックスな構成だが、回転計のレッドゾーンはRD250より10000rpm高い9000rpmから。ハンドルはバー式。
もっとも前述したように、近年の2台に対する世間の見方には大きな差が存在する。VT250Fの評価があまり高くない理由は、シリーズ全体で考えると生産期間が非常に長かったため、希少性を感じづらいから……だろうか。あるいは、エンジン特性がピーキーなRZ250とは異なり、初心者でも気軽に乗れるフレンドリーなキャラクターだったことも、マニア心をくすぐらない原因かもしれない。
VT250Fのタコメーターのレッドゾーンは、当時の250ccとしては驚異的な12500rpmから。ハンドルはセパレート式で、クラッチは油圧式。
とはいえ改めて歴史を振り返ると、VT250Fを筆頭とするVTシリーズは、4ストVツインならではの世界が堪能できる貴重な250ccだったのだ。そして初代の動力性能がRZ250とほとんど互角だったこと、1982~1985年に圧倒的な強さでクラストップの販売台数を記録したこと、時代の要求に応じて変化を遂げながら35年に渡って販売が続いたこと(RZは後継のRZ-RとR1-Zを含めても約20年)などを考えると、やっぱり筆者としては、VT250FはRZ250に勝るとも劣らない魅力を備えた、2輪の歴史を語るうえで欠かせない名車だと思うのである。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)
初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]
高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]
RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]
大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]
インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]
最新の関連記事(ホンダ [HONDA])
RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]
これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]
理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]
終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]
ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]
ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]
最新の投稿記事(全体)
初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]
Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]
最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]
伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]
ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]
- 1
- 2