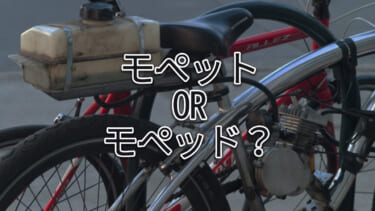●文:[クリエイターチャンネル] Peacock Blue K.K.
道路のシマシマ“ゼブラゾーン”の意味は?
道路を走行していると、交差点の手前にシマシマと白線が引かれた場所があります。通常の路面に比べてなんとなく走行しにくいシマシマですが、これにはどのような意味合いがあるのでしょうか。
通称「ゼブラゾーン」と呼ばれている道路のシマシマは、正式名称を「導流帯」と言います。ゼブラゾーンは、道路交通法上で“指示標示”のひとつに区分されており、交通量の多い交差点や作りが複雑な道路において、交通を安全かつ円滑に促すためのものです。
指示標示には、ほかにも“横断歩道”や“停止線”などが含まれ、特定の方法に従って通行するよう指定したり、道路交通法で決められた場所を指示する役割を持っています。
一方で、何かを禁止したり、規制したりするものではなく、ゼブラゾーンもその地点の通行が禁止されるというものではありません。
具体的には、ゼブラゾーンは右折車線から直進車線に交通の流れを促すような形で標示されていることが多いのですが、ゼブラゾーンの上を通行してはいけないという規制はされていません。
直進から右折へ交通の流れが促されているゼブラゾーン。公道ではこのようなゼブラゾーンが多く見られます。
そのため、ゼブラゾーンを避けて通ることはもちろん、そのまま突っ切るかたちで走行することも法律上は可能です。
例えば、上述したように、右折車線から直進車線に交通の流れを促すような形で標示されているゼブラゾーンの場合、そのままゼブラゾーンを直進して右折車線に入ることができるというわけです。
通れるけど推奨はしない? ゼブラゾーンでの事故には要注意
とはいえ、むやみにゼブラゾーンを通行することは推奨できません。
ゼブラゾーンは、上述したように交通量が多かったり、作りが複雑だったりと、基本的に事故のリスクが高い道路に優先的に標示されるようになっています。そうした道路の交通を整理することで、事故のリスクを下げようという目的があるからです。
例えば、バイクでゼブラゾーンを突っ切って走行しようとした場合、ゼブラゾーンを避けて通行した車両とバイクが接触する危険性も考えられます。バイクはボディサイズも小さく、クルマの死角に入ってしまいやすいので、とくに注意が必要になります。
また、そうした事故が起きた場合には、ゼブラゾーンを走行していた車両の過失が大きくなる可能性があります。事故の過失割合は、ケースバイケースなので一概に言えませんが、ゼブラゾーンは通常避けて通ることが目的とされているため、ゼブラゾーン上を通過していた車両のほうに過失が大きくつくのが一般的なようです。
一方で、右折車線から直進車線に交通の流れを促すような形でゼブラゾーンが標示されているケースで「右折の矢印信号が出ているのに直進車線が混雑していて右折できない!」といった場合には、安全をしっかりと確認したうえで、ゼブラゾーン上を走行しても良いでしょう。
安全かつ円滑に通行できるのであれば、ゼブラゾーン上を走行しても問題ないと言えます。
ゼブラゾーンに類似したこんな標示には要注意
道路では、ゼブラゾーン以外にも白線のシマシマが活用された標示が存在しています。もちろん、ひとつひとつ意味合いが異なるため、ライダーはそれぞれの意味をしっかりと覚えておく必要があります。
例えば、ゼブラゾーンに似た標示として挙げられるのが“停止禁止部分”の標示です。これは、主に消防署や警察署の前などで目撃することの多い標示となっており、この地点での一時停止や停車を禁止するものです。
消防車や警察署からは、消防車やパトカーなどが緊急出動することがあり、そうした場合に車両の進路を塞ぐことがないよう、常に導線を確保しておくことが求められます。そのために、停止禁止部分を設けているのです。
消防署や警察署の前にはこのように車線で区切られた場所があります。緊急車両のスムーズな出動のために開けておくように徹底しましょう。
また、ほかにも“安全地帯または路上障害物接近”の標示も、白線のシマシマが活用されたデザインとなっています。こちらは、高速道路の合流や分岐部分に標示されていることが多く、前方の障害物の存在を知らせる役割を持っています。前方に、より注意を払って走行するようにしましょう。
さらに、“立ち入り禁止部分”の標示も、ゼブラゾーンに似たデザインとなっています。立ち入り禁止部分は、白線のシマシマがオレンジ線で囲われる形になっているのが特徴です。標示場所としては、ゼブラゾーンのように道路の形状が複雑なところが多い一方で、ゼブラゾーンと違って、その地点には一切立ち入ることができないため注意が必要です。
類似した標示でも、実際の規制や指示内容は大きく異なるため、それぞれの役割を知ったうえで安全かつ正しくバイクが運転できるようにしましょう。
※本記事は当該執筆者が寄稿したものであり、その文責は執筆者に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の記事
スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]
Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]
[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]
振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]
オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]
人気記事ランキング(全体)
7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]
簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]
WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]
世代をまたくトップライダーたちのレプリカモデルが一気に3種も登場 『DIGGIA2』は、2024年12月にも発売された、MotoGPライダーのファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル第2弾[…]
製品名がグラフィック化されたユニークなモデルのニューカラー 『GT-Air3 MIKE』は、その製品名を巧みに図案化したグラフィックを特徴とするモデルで、2025年10月に発売された。このたび発表され[…]
最新の記事
- 1
- 2