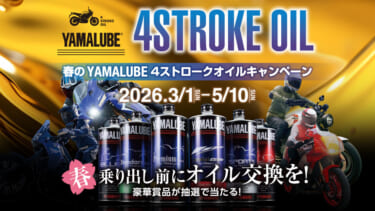![[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/06/wym2505-16-02-honda-monkey125-2024.jpg?v=1749191856)
中古車を選ぶ際、なかなか悩ましいのが何を持って完調の状態といえるかわからないこと。そこで役に立つのが、劣化や不具合のない新車当時の試乗レビューだ。自分が中古車を試乗して、それぞれの個体の状態を確かめる際の参考にしてみて。
●文:ヤングマシン編集部(谷田貝洋暁) ●写真:富樫秀明 ●外部リンク:ホンダ
ホンダ「モンキー125」(2024)試乗レビュー
この記事ではかわいらしいフォルムと実用性が同居したファンバイク、モンキー125の2024年モデルについて紹介するぞ。初期のモンキー125に近い、シンプルなカラーリングや装飾となった年式だ。 ※以下、2024年12月公開時の内容に基づく
グロムとは違うのだよ、このモンキー125は!
2018年7月、オールドウイングシリーズ第1弾として、スーパーカブC125よりも2か月だけ早く発表&発売されたモンキー125。思えばこのモンキー125とスーパーカブC125の成功が、のちのCT125ハンターカブやダックス125といったオールドウイングシリーズの続編を生み出す礎となったわけだ。
これらオールドウイングシリーズの面白いところは、日本国内主導の企画発案でないところ。…と言うのもタイをはじめとする東南アジア地域では、趣味性の高い乗り物としてモンキーやスーパーカブがカスタムベースとして持て囃されており、そんな需要を見込んで生まれたのがモンキー125やスーパーカブC125であり、現在のオールドウイングシリーズというわけだ。
【HONDA GROM】MT仕様のエンジン、車体の一部はモンキー125と共用するも、牧歌的なモンキーのキャラに対し、スポーツバイクとして作り込まれているのがグロムだ。スポーティーなポジション&モノショックに加え、最高出力で0.6psほどパワフルなエンジン特性が与えられている。またモンキーにはできない2人乗りも可能だ。
そんな出自もあり、所有欲を満たす贅を尽くした細部への作り込みもオールドウイングシリーズの特徴。モンキー125は、小ぶりのヘッドライトにクロームメッキが施された前後スチールフェンダーといった部分に格別のこだわりを感じられる。
車体に関しても、ベースであるグロムからかなり手が入れられている。ツインショック化とともに軸間距離を55mm(2018年の登場時は45mm)も短縮。ひとり乗り専用シートに割り切ることで、モンキーらしい台形のシルエットを作り出した。
エンジンに関しても、グロムはあくまでスポーツバイクとして作り込まれているのに対し、モンキー125は吸排気系やエンジンのFIセッティングが異なる。最高出力&最大トルクの発生回転域は500rpmほど引き下げて中低速域のトルクを増強。アップライトで牧歌的なライディングポジションとこの中低速重視のエンジンキャラクターのおかげで、トコトコと気楽にお散歩するぐらいのペースで走ると一番モンキーらしさが味わえる。
筆者は身長:172cm/体重75kg。776mmの低シート高&コンパクトな車体で膝をかなり余らせた状態で踵までべったり。ポジションはコンパクトだが意外に窮屈感はない。分厚いシートがフカフカで座り心地Good!!
またモンキー125で面白いのは、乗ると“ついつい余計なことをしたくなる”ところ。おそらくモンキー125の軽量コンパクトさがそうさせるのだろうが、走っているうちに、リヤをブレーキロックしたらうまくブレーキターンできるんじゃないの? とか、コイツとならもしかしてフロントアップできるんじゃないの? なんて気分になってくる。
遊び心がくすぐられるというかなんというか…、ついつい余計なことをしたくなる(笑)。でも、これこそがモンキーというバイクのキャラクターの核心だ。
ホンダ「モンキー125」(2024)のディテール
【とにかく小さくコンパクト!】ひとり乗りに割り切った車体はとにかく軽い104kg! 全長も1710mmとコンパクトで置き場所にも困らない。
ホンダ「モンキー125」 の最新相場情報
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の関連記事(自分だけのバイク選び)
ヤマハSR400試乗レビュー この記事では、ヤマハのヘリテイジネイキッド、SR400の2021年モデルについて紹介するぞ。43年の歴史に幕を下ろした、最終モデルだった。 ※以下、2021年5月公開時の[…]
ヤマハNMAX155試乗レビュー この記事では、ヤマハの原付二種スクーターから、NMAX ABS(125)の2018年モデルについて紹介するぞ。 ※以下、2018年7月公開時の内容に基づく 【NMAX[…]
ホンダPCX/160(2020/2021)比較試乗レビュー この記事では、ユーロ5に対応するため全面的に刷新し、第4世代となった2021年モデルと前年にあたる2020年モデルについて比較して紹介するぞ[…]
ホンダ CB400スーパーフォア(2018) 試乗レビュー この記事では、平成28年度排出ガス規制に法規対応するなどモデルチェンジを実施した2018年モデルについて紹介するぞ。 ※以下、2018年6月[…]
ホンダ CB1300スーパーボルドール(2018)試乗レビュー この記事では、平成28年度排ガス規制に対応しモデルチェンジを行った2018年モデルについて紹介するぞ。 ※以下、2018年6月公開時の内[…]
最新の関連記事(モンキー125)
チェック柄シートが復活、継続色はタンク色などを変更、バナナイエロー新登場 ホンダは、タイ&欧州で先行発表されていた「モンキー125」の2026年ニューカラーを発表した。とはいうものの、一部は海外仕様と[…]
2023年モデル以来のタータンチェック柄シート ホンダは欧州で2026年の125ccモデル×3車を発表。トリを飾るモンキー125はタイで先行発表された3色をそのまま欧州に導入したもので、中でも注目はモ[…]
気楽に常用高回転を楽しめる原付2種モデルだからこそ、エンジンオイル交換に気を配りたい ホンダ横型エンジンの伝統でもある、粘り強くトルクフルな走りを現代に伝えているホンダモンキー125。スーパーカブ12[…]
新たに前輪ABSを標準装備! 日本仕様のニューカラーにも期待 ホンダはタイで、「モンキー(和名:モンキー125)」の2026年モデルを発表。新型はフロント1チャンネルABSを新たに標準採用(日本仕様は[…]
GORILLAタンクと専用シートがついに販売開始! 2025年の7月に紹介されたGORILLA 125(ゴリラ125)が外装セットとして「8ft weekend」から販売スタート! 当時はプロトタイプ[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]
X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]
最新の投稿記事(全体)
8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]
なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]
平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]
BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]
RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]
- 1
- 2

![ホンダ|グロム|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/10_2240215-grom_001H-768x577.jpg?v=1734437381)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/honda-monkey125-test-yatagai_02-768x432.jpg?v=1734436544)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/11_TOG_2350-768x576.jpg?v=1734438297)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/13_TOG_2374-768x576.jpg?v=1734438299)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/1f5f3551f12b58c6be8b69859c8fb3a0-768x576.jpg?v=1734438301)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b1-TOG_2554-768x512.jpg?v=1734438372)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b2-TOG_2568-768x512.jpg?v=1734438374)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b3-TOG_2584-768x512.jpg?v=1734438375)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b4-TOG_2519-768x512.jpg?v=1734438376)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b5-TOG_2525-768x512.jpg?v=1734438378)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b6-TOG_2537-768x512.jpg?v=1734438380)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b7-TOG_2548-768x512.jpg?v=1734438381)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b8-TOG_2546-768x512.jpg?v=1734438384)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b9-TOG_2531-768x512.jpg?v=1734438387)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/b10-TOG_2561-768x512.jpg?v=1734438388)
![ホンダ|モンキー125|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ホンダ「モンキー125」(2024) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/12/a93349056591b3041918a73ac442bd73-768x512.jpg?v=1734438499)