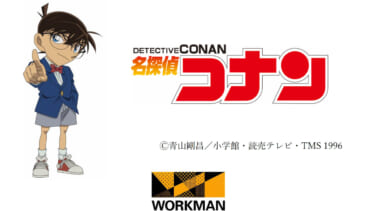元MotoGPライダーの青木宣篤さんがお届けするマニアックなレース記事が上毛グランプリ新聞。1997年にGP500でルーキーイヤーながらランキング3位に入ったほか、プロトンKRやスズキでモトGPマシンの開発ライダーとして長年にわたって知見を蓄えてきたのがノブ青木こと青木宣篤さんだ。WEBヤングマシンで監修を務める「上毛GP新聞」。第27回は、ついに剛性を抜く方向にシフトチェンジしたヤマハと、それに応えたファビオ・クアルタラロについて。
●監修:青木宣篤 ●まとめ:高橋剛 ●写真:Ducati, Michelin, Red Bull, Yamaha
運を味方につけたザルコの勝利
天候に翻弄されまくったMotoGP第6戦フランスGP。ややこしいスタートになったのでざっくり説明しておくと、決勝スタート直前のウォームアップ走行がウエット路面になり、全員がピットイン。レインタイヤを装着したマシンに乗り換えている間に赤旗が掲示されて、いったんスタート開始は仕切り直しに。ウエットレース宣言が出された。
ところが2回目のスタート直前のサイティングラップで多くのライダーが「あれ? 意外と路面、乾いちゃってんじゃね?」と感じたようで、スリックタイヤ装着マシンに乗り換えるライダーが続出。レインタイヤ組は問題なくグリッドスタートできるが、スリックタイヤ乗り換え組がグリッドスタートをする場合は、レギュレーションによりダブルロングラップペナルティを食らうこととなった。
そしていざ決勝がスタートすると、路面はしっかりウエット……。レインタイヤ組が淡々とレースを進める一方で、スリックタイヤ乗り換え組はスタート直後にレインタイヤ乗り換えのためピットインを余儀なくされ、さらにグリッドスタートしたことによるダブルロングラップペナルティも科せられ……と、さんざんなことになってしまった。
さらにレース中に意外と路面が乾いた場面もあり、スリック→レイン→スリックとマシンを2度乗り換えたライダーも。そんな中、結果的には、レインタイヤのままデーンと構えていたホンダのヨハン・ザルコが優勝を果たした。
フランス人ライダーが母国GPで優勝するのは’54年のピエール・モネレ選手以来な71年ぶりなうえ、ドゥカティの連勝をホンダとタイ記録の22で止めるという、なんとも歴史的な快挙。終始レインタイヤのままだったザルコにとっては、我慢を強いられる場面も多かったと思うが、最後に笑った。
フランスGPで優勝したヨハン・ザルコ。さらにイギリスGPではドライ路面で2位につけた。
ザルコの自身2勝目は実にドラマチックなものとなったが、まぁしかし、こればかりは運としか言いようがない。母国GPだったザルコに地の利があったとも思えないのは、同じく母国GPだったファビオ・クアルタラロがリタイヤしてしまったことからも明らかだ。天候が不安定な時のレースは、ライダーにはどうしようもない部分が多すぎて、元ライダーとしてはなんとも複雑な心境になります……。
2位になったマルク・マルケスは、本来なら今回のような難コンディションの時ほどイキイキとして、ぶっちぎりで優勝してもおかしくないライダーだ。しかし相当に滑る状況だったのだろう。しっかりと路面に合わせたライディングで、ステディに走り切った。少しはオトナになったのかな……、どうかな……。
コーナー進入で震えている?!
というわけで、マニアックな上毛GP的にはヤマハのフレームに着目したい。ヤマハのフレーム、ペラッペラのペナッペナです。もうホント、驚くほどペナペナになっている。なぜそんなことが分かるのかというと、全開で寝かし込んでいくようなコーナーでの挙動を見れば、一目瞭然なのだ。ブルブルッと震えているのは、フレーム剛性をかなり落としている証拠だ。
フランスGPのファビオ・クアルタラロ。
コーナー進入時にブルブル震えるようなフレームなんて、今までの日本メーカーでは考えられないぐらいの剛性の低さだ。フレームの剛性は安全性を担保するもっとも重要なスペックだから、ヤマハの社内でも相当な議論が行われたはずだ。恐らく社内的なコンセンサスを得るために、車体設計の方はかなり苦労しただろうと思う。
というのは、日本メーカーは安全志向が強いのだ。いい意味では手堅くて安心だし、悪い意味では攻めが足りない。今回のヤマハのペナペナフレームは、かなりアグレッシブな設計だと思う。そういえば、昨年のシーズン終了直後のカタルニアテストで、ドゥカティのピット前でしげしげとデスモセディチを眺めているヤマハのスタッフがいたことを思い出す。たぶん車体関係の方だと思うのだが、デスモのフレームの同じ箇所に注目していて、ワタシと目が合うと「……薄いですよね〜」と口を揃えたものだ。
ワタシも、ヤマハ・スタッフの方も、デスモセディチのピボットまわりを見ていたのだが、かなり剛性が必要とされていた箇所にも関わらず、肉厚がとことん薄い。「ドゥカティがあんなに攻めた設計なら、ウチだって」と思った……のかどうかは定かではないが、刺激になったことは間違いないだろう。
「力が加わっても壊れないように頑丈にする」という日本流のモノ作りに対して、欧米では「力が加わった時に、しなりで力を逃がす」という考え方があるようだ。どちらがいい、悪いという話ではなく、国民性というか、安全に対する向き合い方というか、物事を見る角度に違いがあるように思う。
ヤマハは、ドゥカティからスタッフを引き抜いたり、ヨーロッパの開発拠点との連携を強化したり、2チーム体制に戻したりと、かなりアグレシッブにMotoGPに取り組んでいる。その攻めの姿勢がペナペナフレームに表れているように思う。ぶっちゃけ、トータルバランスではまだドゥカティに届いていないが、ここまで一気に持ってきたのは本当に素晴らしい。
2024年のヤマハYZR-M1。
2025年のヤマハYZR-M1。なかなか決定的なアングルの写真がないものの、複数掲載するので参考になるかと思う。
2025年のヤマハYZR-M1 その2。
2025年のヤマハYZR-M1 その3はイギリスGPにおけるサテライトチーム・プラマックヤマハのもの。こちらは前年モデルのフレームに近いように見える……? シートレールの付け根のあたりを見比べると分かりやすいはず。
現在におけるペラペラ代表のドゥカティ・デスモセディチGP25。
こちらはサテライトチーム・グレシーニレーシングのGP24だが、おおよそGP25と同じようなピボットまわりの形状に見える。
※その他のアングル写真は記事末へ
ファビオの予選アタックに驚愕
「素晴らしい」と言えば、ファビオ・クアルタラロの予選アタックは本当にしびれた。狙ってできるライディングじゃないし、狙って出せるタイムでもない。「よくやったな!」と思う。彼のライディングはフレームの恩恵だけではなく、エンジンのアップグレードも効いている。シーズン中に開発できる優遇措置(コンセッション)を有効に使っている証拠だし、コロナ禍でできた溝がだいぶ埋まってきたのかな、と感じる。
イギリスGPでは3戦連続ポールポジションを決めて見せた。
ちなみに「1コーナーの進入でブルブルしている」などと聞くと、「そんなの怖くて走れないんじゃないの?」とお思いかもしれない。普通の感覚で言えば、怖くて走れない可能性もある。だが、MotoGPライダーはそんなことを気にしていない。彼らの判断基準は極めてシンプル。「タイムが出るか、出ないか」、ただそれだけだ。
さらにちなみにブルブルにもいろんな種類がある。アプリリアはヘッドパイプまわりがプルプルしているし、ドゥカティは車体全体で力を受け止めている印象。KTMはフレームがしなり切ってしまって何も起きず(サスペンションが底突きしているような状態)、ホンダは相変わらずビターッとしている。
今後、MotoGPを観戦する時は、ぜひフレームのブルブルに注目していただきたい。ジトーッと眺めているうちに、見えてくるものがあるはずだ。たぶん。
その他のフレーム写真
ホンダはブロックのような造り……
……というのは冗談で、こちらはフランスGPで公開されたレゴ製のRCV213Vだ。
チームHRCのRCV213V。ヤマハに負けじとツインスパー後半部分が薄い。
LCRホンダのRC213V。ピボット部分の肉抜きはドゥカティに近いレベルだ。
スペインGPでのプラマックヤマハ・YZR-M1。ピボット部分はやや厚め。
同じ日に撮られたプラマックヤマハのYZR-M1だが、こちらはペラペラフレームを使っている。複数のフレームを投入しているのだろう。
ドゥカティ・デスモセディチGP25のフレームは真横から見ても華奢なのがわかる。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
最新の関連記事([連載] 青木宣篤の上毛GP新聞)
短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]
派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]
ブレーキ以上の制動力を求める進入、スピンレートの黄金比を求める加速 ライディングにおけるスライドは、大きく分けて2種類ある。ひとつはコーナー進入でのスライド、もうひとつはコーナー立ち上がりでのスライド[…]
実は相当ハードなスポーツなのだ 間もなくマレーシア・セパンサーキットにMotoGPマシンの咆哮が響き渡る。1月29日〜31日にはテストライダーやルーキーたちが参加するシェイクダウンテストが行われ、2月[…]
車体剛性を見極めるホンダ、V4を投入するヤマハ ホンダは終盤にやや盛り返した感もあったが、依然不安定だ。それでもシャシーはだいぶよくなった。恐らく車体剛性のカンを押さえることができてきて、剛性を落とす[…]
最新の関連記事(モトGP)
現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]
SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]
開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]
短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]
派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]
人気記事ランキング(全体)
日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]
7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]
GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]
ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]
グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]
最新の投稿記事(全体)
ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]
現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]
河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]
スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]
GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]
- 1
- 2