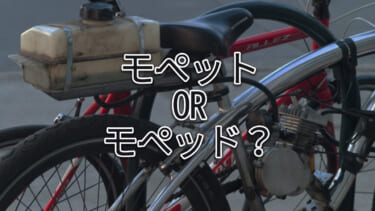●文:ヤングマシン編集部
振動の低減って言われるけど、何の振動?
ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。400ccクラスから上の排気量帯のバイクで採用例が多いが、これって何のためにあるのだろうか?
シンプルにいえば振動対策だ。特に、エンジンの振動がライダーの手に伝わるのを低減させるのが主な役割。エンジンの振動は、回転を上げるほど、また排気量が大きいほど強くなり、ハンドルバーを握るライダーの手をシビレさせたり、疲れの元になったりする。また、強すぎる振動は特にフロントの挙動を感じ取るのにも邪魔になる。これをどのように低減するのかは、バイクの開発でけっこう重要なのだ。
エンジンには1次振動(クランク1回転毎に発生する振動)と2次振動(クランクの回転の2倍の周波数で発生する振動)、カップリング振動(クランクの非対称性が基になって発生する振動)などがあり、例えば単気筒では1次振動が強く、並列4気筒だと高回転時に高周波の2次振動が顕著に出る。
これを低減するには、エンジン自体にバランサーを仕込むとか、振動が車体に伝わりにくいようにエンジンマウントを工夫するといった方法がある。そして本記事のハンドルバーウエイトのように、振動が出る部分の末端に錘を仕込んで共振する周波数を変え、一種のマスダンパーのように使うことで振動を吸収・低減する手法があるわけだ。
ここで注意したいのは、ハンドルバーやバーエンドを交換するカスタムだ。ハンドルバーの材質や重量にもよるが、何も考えずにウエイトを外すと振動が増えることもあり、またウエイトの重量を変えると共振ポイントが変わったりして、思わぬ振動を感じることになるかもしれない。
カスタムにあたっては、自分の用途や普段走る道で振動が出ないか、許容できる程度かなどを確認しながら進めるといいだろう。また、たとえ振動は増えても軽量化したいとか、ポジションを操縦しやすくしたいとか、転倒時のプロテクションのためにウエイトよりも樹脂などの素材のバーエンドを使用したいといった場合もあるだろうから、そこは好みに合わせて自己責任で。
ちなみに、ステップバーの下にウエイトが装着してある機種もあるが、こちらも同じく振動軽減のためのバランサーウエイトだ。
じつは影響があるもうひとつの振動
もうひとつ、ハンドルバーウエイトがあると低減できる振動がある。それはシミーだ。走行中にフロントタイヤが左右に小刻みに切れる振動で、80km/h以下で出ることが多い。また、100km/h以上で出る高速シミー、もっと周波数の低いウォブル(こちらは前後とも振られる)もある。
シミーやウォブルが酷くなると、左右の振れがどんどん増幅し、最悪は転倒に結び付くことも。原因はさまざまだが、最新のバイクであればタイヤの空気圧低下や偏摩耗、ホイールバランスの狂いなど、整備不良によるものが多いとされる。
これが平成中期くらいまでのバイクになると、車両自体のジオメトリーや剛性バランス、タイヤの構造などが現代ほど洗練されておらず、ちょっとしたタイヤの摩耗程度でも誘発されやすい場合がある。これを解消するには、低コストな順に、1)着座位置を変えてみる、2)サスペンションセッティングを調整してみる、3)タイヤを最新スペックのものに交換してみる、4)ステアリングダンパーを装備する、といった方法がある。
ちなみにウォブルがタイヤの構造に起因する場合、リヤに原因があることも。その場合はリヤのセンター付近でバンク角に対する旋回力の立ち上がりが早く、わずかな傾きでフロントを左または右に振る力が発生してしまうから、ということらしい。
さて、すでに読者諸兄もお気づきのように、このステアリング振動の対策として、ハンドルバーウエイトが一定の仕事をしてくれる。ハンドルが左右に振れる現象も振動であり、速度域によって共振すると増幅してしまう。これの対策として、ステアリング軸から遠いハンドルバーエンドに錘を付けることで、振動が発生しにくく、また増幅を抑制する効果を得られるのである。
ここで再びカスタムの話をすると、ハンドルバーを交換してステアリング方向の振動が増えたケースでは、ライディングポジションの変更に起因する場合だけでなく、ウエイトの影響による場合もあると知っておくと、対策する際に役立つかもしれない。意外なところでは、アルミ製のナックルガードを装備して重量が増えると、特定の速度域で振幅が増えることもあるので、「もしかして」と思ったら付けたり外したりして挙動を確認してみるといいだろう。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
最新の関連記事(ビギナー/初心者)
きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]
徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]
改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]
「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]
「一時停止違反」に、なる!/ならない!の境界線は? 警察庁は、毎年の交通違反の取り締まり状況を公開しています。 最新となる「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等につい[…]
最新の関連記事(Q&A)
スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]
Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]
[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]
振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]
オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]
ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]
最新の投稿記事(全体)
Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]
最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]
伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]
ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]
ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]