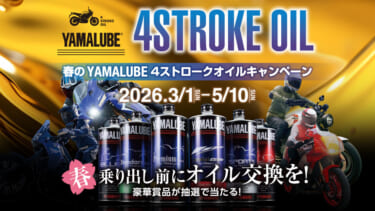信号待ちをしている車両がいることを検知してから青に切り替わる「感応式信号」。おもに交通量が多い主道路/交差する従道路などに設置されており、従道路のみが感知式になっている信号機は「半感応式信号」と呼ばれます。ただしバイクの場合は、感応式信号に検知されにくい傾向があるようです。
●文:ヤングマシン編集部(ピーコックブルー)
感応式信号=超音波センサーに検知されないと信号が変わらない
多くの感応式信号は、停止線付近の頭上に備わった超音波センサーで信号待ちの車両を検知しているため、センサーに検知されなければ信号は変わりません。
超音波センサーは、停止線の少し手前の地上5〜6mの場所に備わっており、直径15cmほどの拡声器のような形状をしています。
センサーはつねに超音波を発しており、路面に跳ね返ってくるまでの時間を計測して、センサーの下に車両が来て計測時間が変わったことをきっかけに、信号機を青に切り替えます。
これが信号待ちの車両を検知してから青になる感知式信号の仕組みですが、じつは検知範囲が意外と狭く、センサー直下の直径約1.2mの範囲に車体がなければ検知できないとのこと。
そのため、バイクは停止する位置によって反応しないことがあるというわけです。また、誤作動防止のため3秒間車両を検知し続ける必要もあり、バイクでは余計に反応しにくくなるばかり…。
「感知中/おまちください」といった表示が信号機に出るタイプであれば、検知されたかどうか確認できますが、そのように表示されない信号機の場合、検知されているかどうかすら判断できません。
また、交通量の少ない夜間にのみ感応式に切り替わる場所では、周囲が暗くてセンサーの位置自体がわからない場合もあります。
こういった事態を防ぐため、感応式信号には“2輪車用ボタン”が併設されているものも。歩道側の電柱にボタンがあれば、それを押すことで信号を切り替えられます。
なお、2輪車用ボタンがない場合は、歩行者用ボタンを押すことでも信号が切り替わります。
狭い道路や小さいバイクほど停止位置に注意
感応式信号機にしっかりバイクを検知させるためには、なによりも停止位置が重要になります。
センサーを通り過ぎて停止線のギリギリに止まったり、左折する大型車への備えとしてセンサーの手前に止まると、検知されない場合があります。
また、両側一車線しかない狭い道路の感応式信号の場合、対向車による誤作動を防ぐため、検知範囲がさらに狭い設定になっています。
優先道路との交差点に差しかかる際は、信号の色だけでなく、感応式信号の標識と頭上のセンサーの位置を確認して、なるべくセンサーの直下に停まるようにしましょう。
また、2輪車用ボタンを押すためにバイクから降りる際は、たとえ後続車にクラクションを鳴らされたとしても慌てないことが大切です。
交差点付近の路面は轍(わだち)で凸凹になっている場所も多く、慌ててバイクを降りると足を挫いたり立ちゴケをするリスクが高まることも覚えておきましょう。
感応式信号機の仕組みを知っておけば、こうしたトラブルも回避できます。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
最新の関連記事(交通/社会問題)
ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]
窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]
きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]
車検満了日の2か月前から受験可能に! 春といえば車検の季節。新車や中古車がもっとも売れるのは1~3月であり、そこから3年あるいは2年が経つと車検がやってくる。もちろん納税も……。 この季節は年度末でも[…]
改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]
最新の関連記事(バイク雑学)
BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]
元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]
なぜ「ネズミ捕り」と呼ぶのか? 警察によるスピード違反による交通取り締まりのことを「ネズミ捕り」と呼ぶのは、警察官が違反者を待ち構えて取り締まるスタイルが「まるでネズミ駆除の罠のようだ」と揶揄されてい[…]
交通取り締まりは「未然に防ぐため」ではなく「違反行為を探して検挙するため」? クルマやバイクで運転中に「なんでそんな所に警察官がいるの?!」という運転者からすれば死角ともいえる場所で、交通違反の取り締[…]
ホコリや汚れを呼ぶ潤滑スプレー 鍵を差すときに動きが渋いなーとか、引っ掛かるなーと感じたことはありませんか? 家の鍵や自転車の鍵、倉庫の南京錠など、身の回りにはいろいろな鍵がありますが、屋外保管しがち[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]
ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]
最新の投稿記事(全体)
憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]
8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]
なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]
平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]
BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]