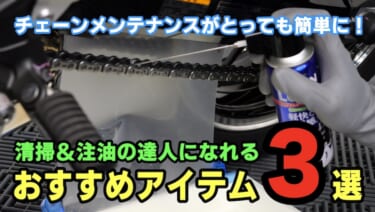電動キックボードに関する道交法改正について、東京都市大学 建築都市デザイン学部 都市工学科 准教授の稲垣具志さんに伺った。稲垣さんは埼玉県の三ない運動撤廃にあたり「高校生の自動二輪車等交通安全教育検討委員会」で会長を務めた方でもある。(以下、敬称略)
●文:ヤングマシン編集部(田中淳麿)
【東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科准教授 博士(工学) 稲垣具志氏】’16年、埼玉県に設置された「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する検討委員会(埼玉県教育委員会主催)」で会長を務め、9回にわたる会議において三ない運動を検証し、その功績と課題に向き合った。三ない運動をやめるやめないではなく、高校生にどうやって交通安全教育を届けるのかについて、プロセスを重視した議論で合意形成、同県の交通安全教育推進に寄与し、高い評価を受けた。
自転車感覚では不安が残る電動キックボードの運用
───海外の現状も鑑みて、日本では電動キックボードについてどのような運用をしていくべきでしょうか。
稲垣:警察庁は、道交法改正議論の中で調査研究をして、海外の事故やその対応についても整理しているはずです。例えば、リミッターが付いているというのは、20km/h以上での事故が増えているヨーロッパの事情を踏まえた上での決定だと思います。
───電動アシスト自転車は24km/hまでのアシストでかなり速いんですが、LUUPの実証実験では「15km/hだと周りのクルマより遅すぎて怖い」という声があって、最低でも20km/hは出したいという結果でした。
稲垣:(歩行通行車モードの)6km/hも相当遅いです。早歩きと同じくらいで本当にみんなやるのかなと。
───日本には海外のような低速モビリティレーンがほとんどありません。それに、狭い道は本当に狭い。どこまで突き詰めた実証実験やアンケート調査を行ってきたのかというと少し疑問ですが、海外で参考になるような事例はありますか?
稲垣:電動キックボードは、同じヨーロッパでも国によって導入の仕方が違っていたり、野放しのまま始まって死亡事故が多発したりとか。アメリカなどでは飲酒運転率も非常に髙いそうです。日本でもお酒を飲んで自転車に乗っている人はいますからね。それに近いようなものもあり得るかなと思います。※本インタビューは’22年7月に行なわれたが、実際に9月には飲酒死亡事故が発生している
───先日、警察に話を聞いたら、電動キックボードの駐車違反も切っているそうで、罰則は自転車と同じような扱いになる可能性が高そうです。
稲垣:自転車も場合によっては一発で裁判所に出頭しないといけないようなパターンもありますよね。踏切の遮断機が下りてきているのにくぐったりすると、一発で出頭命令だったはずです。どのような取り締まりができるのか、ということは考えないといけませんね。
諸外国と比べてですが、やはり日本は自転車が車両であるという認識がすごく薄いなと思いますね。海外では自転車はクルマ側の乗り物です。”自転車に乗るということは運転するものだ”という意識、文化があります。日本では歩行者に近くて、交通弱者と思っているレベルですよね。
こんなに自転車が日常的に使われて老若男女が乗っているような国は、先進国の中でも珍しいです。諸外国で自転車に乗る方たちはキチンとヘルメットをかぶりますし、尾灯が切れたら乗らないなど責任が伴う乗り物という認識が強いと感じます。
───LUUPは、シェアリング中に悪質な交通違反があれば、二度と乗れないようにアカウント削除を行うこともあるようです。警察が、個人所有物やシェアリング他社との見分けが付くように、車体色も真っ白に変えて差別化しました。
稲垣:シェアリングはある程度コントロールできますよね。ただ自分の持ち物として保有する場合は難しい。自動運転の話でも出がちですが、飲酒にしても高齢ドライバーにしても、問題があればクルマが動かないようにすればいいという話が出てきますが、電動キックボードでもそういう議論が起きるかもしれません。車両側にそういう機構が付けられないのかと。ドライブレコーダーのメーカーでは、アルコールの呼気検査に通ったら運転できる、みたいなシステムを検討しているようです。
───車両側で規制を設けることに関してはどう思われますか。
稲垣:できるのなら、やったらいいでしょうね。自分でコントロールできない依存レベルでの飲酒もありますし。
LUUPでは、実証実験車両とそれ以外の車両を警察が瞬時に見分けやすいように、車体色を緑×黒から白×緑に順次変更している。こうした車両のマイナーチェンジは頻繁に行われている。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の関連記事([連載] 2輪車利用環境改善部会)
【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]
1. 【背景と現状】“原付”モビリティの現状について かつては50ccガソリンエンジン車しかなかった“原付”も現在では多様化している。今回の排ガス規制により50ccガソリン原付は生産を終了し[…]
1. 【背景】50ccガソリン原付は排ガス規制をクリアできず 50ccガソリン原付はなぜ生産終了となるのか。それは地球環境保護という理念のなか世界的に年々厳しくなる排ガス規制値をクリアできないとわかっ[…]
原動機研究部が原付通学環境整備のため講習会を開催 2025年7月13日(日)、静岡県伊豆市修善寺虹の郷において、地域クラブ「原動機研究部」(略称:原研)主催による「高校生対象 原付バイク安全運転講習会[…]
1.生徒にアンケート調査!<免許取得と車両の購入> 坂本先生は、本年7月に北杜高校の生徒を対象に安全意識に関するアンケート調査を行った。対象は原付免許を持つ2.3年生の生徒100名と、小学校時に自転車[…]
人気記事ランキング(全体)
7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]
簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]
WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]
世代をまたくトップライダーたちのレプリカモデルが一気に3種も登場 『DIGGIA2』は、2024年12月にも発売された、MotoGPライダーのファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル第2弾[…]
製品名がグラフィック化されたユニークなモデルのニューカラー 『GT-Air3 MIKE』は、その製品名を巧みに図案化したグラフィックを特徴とするモデルで、2025年10月に発売された。このたび発表され[…]
最新の投稿記事(全体)
グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]
ガレージREVOのリフトアップ方法 移動式バイクスタンドであるガレージREVOにとって、スタンドとバイクの接点は重要です。前後左右に押し歩く際にスタンドに載せたバイクが転倒しては一大事なので、スイング[…]
Screenshot 便利なアイテムでチェーン注油とチェーン清掃が簡単作業に変身 日常的なバイクメンテナンスの代表格といえば洗車ですが、その次に作業頻度が高いと思われるのは「チェーンメンテナンス」です[…]
PERFORMANCE MACHINE|Race Series エンジン/トランスミッションカバー 高品質なビレットパーツで世界的な知名度を誇るPerformance Machine(パフォーマンスマ[…]
SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]
- 1
- 2