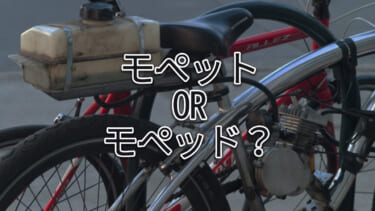●文:[クリエイターチャンネル] Peacock Blue K.K.
バイクってハザードの搭載義務はないの? ハザードの意味は?
道路で道を譲ってもらった際に、“ありがとう”の意味を込めてハザードを利用するライダーも多いでしょう。“ありがとう”を意味するハザードの使用は「サンキューハザード」とも呼ばれ、多くの運転者にとって慣例的な使い方となっています。
さて、クルマの場合はすべてのモデルにハザードが搭載されていますが、バイクではモデルによって、ハザードがついていないものがあります。
ハザードは正式名称を「非常点滅表示灯」と言い、道路運送車両の保安基準では、バイクへの搭載について下記のように規定されています。
「自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらにより牽引される被牽引自動車にあっては、この限りでない」
つまり、クルマにはハザードの搭載義務がありますが、バイクには搭載義務はありません。そのため、ハザードを搭載するバイクと、搭載しないバイクが存在するのです。
そんなハザードの使用方法は、道路交通法施行令第18条「道路にある場合の灯火」において、「自動車は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」とされています。
しかし、この場合の“自動車”は「大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く」とされており、バイクは含まれていません。
とはいえ、バイクのハザードの使い方が完全に自由というわけにはいかないでしょう。厳密に言うと使用方法は定められていないことになりますが、非常点滅表示灯の名の通り、クルマと同様に周囲に自車の存在を認知させるものとして、緊急時に活用するのがベターです。
「ありがとう」を伝えるコミュニケーションツールのひとつとしてハザードを使用したくなることもあると思いますが、ハザードはあくまでも緊急時に活用するものであることを理解し、むやみに使用するのは控えたほうが良いでしょう。
バイクへの搭載義務がないハザードですが、なかには安全性の観点からハザードを搭載しているモデルのあります。クルマと同様に、停車時や、万が一の緊急時に使用するようにしましょう。
大型バイクにハザードの搭載が多いのはなぜ?
ハザードが搭載されているバイクには、排気量の大きい大型モデルが多く、これには高速道路の走行の可否なども関係していると考えられます。
万が一、高速道路を走行中にバイクが故障してしまった場合、路肩に停車してレッカーなどの対応を待ちます。当然ですが、高速道路上では高速域で自動車が走行しており、もし停車中のバイクと接触したらさらなる被害を呼びかねません。
先ほども述べたように、ハザードには自車の存在を周囲に認知させる効果があるため、こうした緊急事態にはハザードを使用するのが有効的です。
そもそも、バイクでは総排気量が125ccを超えていないと高速道路を走行することができません。こうしたことから、排気量がある程度大きいバイクにハザードが搭載されている背景のひとつには、高速道路での走行も見越しているという点が挙げられるでしょう。
“サンキュークラクション”にもご注意!
ちなみに、「ありがとう」を伝える方法として、軽くクラクションを鳴らす人も見かけます。クラクションはクルマもバイクも共通で全車に搭載されていますが、使い方の決まりはないのでしょうか?
クラクションは正式名称を「警音器」と言い、道路交通法54条において「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とされており、警音器を鳴らすべき場合については次のふたつが挙げられます。
- 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
- 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
つまり、「ありがとう」を伝えるために鳴らすクラクションは、法令違反とみなされる可能性が高いということです。ハザード同様に使用方法を改めて認識し、誤った使い方をしないように注意しましょう。
道路交通法54条ではクラクションが使用できる場面について記載されていますが、“道路標識等により指定された区間”の標識は、“警笛ならせ”の標識となっています。この標識の場所を通過する時はクラクションをならさなくてはいけません。
※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
最新の関連記事(Q&A)
スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]
Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]
[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]
振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]
オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]
爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]
なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]
日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]
最新の投稿記事(全体)
理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]
「寒さ」を我慢する時代は終わった 冬の寒さは不快なだけではない。身体をこわばらせ、思考力を低下させ、日々のパフォーマンスを著しく下げる要因となる。 2026年2月12日から17日まで開催されているPo[…]
終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]
- 1
- 2