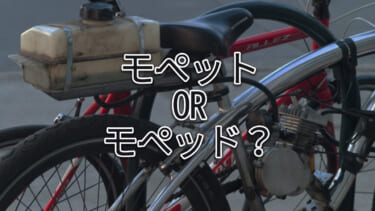●文:[クリエイターチャンネル] Peacock Blue K.K.
“法定外表示”って知ってる?
道路を走行していると、“制限速度”や“車両進入禁止”など、さまざまな標識を目にします。バイクで安全に走行するうえで、標識は言うまでもなく重要な存在です。
標識のなかでもかなりの頻度で目にするのが、赤い逆三角形に白文字で「止まれ」と書かれた“一時停止”の標識です。一時停止は自動車教習所でも厳重に扱われている標識のひとつで、例えば、自動車教習所の卒業試験で一時停止を見落とすと、その時点で試験失格となります。
公道に設置されるすべての標識に重要な意味合いがありますが、一時停止は、特に見通しの悪い交差点や交通量の多い地点など、基本的に事故の発生率が高く見込まれる場所に設置されています。
一時停止を見落とすと、自動二輪では違反金6000円が科され、違反点2点が加点されてしまいます。
街中の至るところで目にする“一時停止”の標識は、見通しの悪い交差点や交通量の多い道路など、事故のリスクが高い場所に設置されています。そのため、確実に一時停止し、周囲の安全確認を行うことが求められます。
一方で、先に述べたような一時停止の標識がなく、代わりに道路の路面に白文字で「止まれ」の文字がペイントされていることもあります。同じ「止まれ」でも、標識と路面のペイントでは意味合いが大きく異なります。
「止まれ」のような路面のペイントは、正式には「路面標示」と呼ばれます。「止まれ」は路面標示のなかでも“法定外表示”というカテゴリーに分類され、基本的には法的効力を持っていません。
法定外標示について、警視庁では「法定の道路標識等による交通規制の効果を明確にし、運転者に対して道路の状況又は交通の特性に関する注意喚起を行うなど、交通の安全と円滑に資することを目的として整備されてきた」と説明しており、標識の内容を運転者によりアピールするためのものとしています。
そのため、法定外表示だけでは実質なんの効力もありませんが、基本的には標識とセットで設置されることになっているため、結果として、法定外表示を無視すると必然的に標識も無視したことに繋がり、道路交通法違反とみなされます。
道路に「止まれ」の文字が見えたときには、一時停止の標識がすぐそばにあるものだと思って、しっかりと一時停止しましょう。
“規制標示”と“指示標示”
なお、標示は“規制標示”と“指示標示”のふたつに分けて考えられます。このふたつは法定外標示とはまったく異なり、法的な効力を持つものです。
規制標示には、“転回禁止”/“最高速度”/“車両通行帯”など、日常的によく目にする標示が数多くラインナップされています。自動車の動きを規制し、安全で円滑な交通を実現する目的があります。
規制標識は、自動車のさまざまな動きを規制するためのもの。安全かつ円滑な交通を守るために重要な役割を担っています。
また指示標示には、“横断歩道”/“進行方向”/“中央線”などが挙げられます。こちらも日常的によく目にする標識で、自動車の流れを整理したり、誘導したりする目的があります。
多くの人にとって馴染みのある横断歩道。歩行者の通行場所を確保して一点に誘導することで、バイクやクルマといったほかの交通との事故の危険性を低減させるうえ、交通全体を円滑に促します。
規制標示と指示標示については、標識の有無にかかわらず標示自体が法的な効力を持っているので、標示の内容を確実に守る必要があります。法定外表示と混同することがないように注意しましょう。
標識にも大きく分けて4つの種類が!
実は標示だけでなく標識にもいくつかの種類があり、大きく分けると規制標識/案内標識/指示標識/警戒標識の4つの種類がラインナップされています。
規制標識には、先ほど述べた一時停止に加え、“一方通行”や“通行止め”など、自動車の動きを規制するための標識が分類されます。標識の形はさまざまですが、円形の標識に赤や青を基調とした記号や文字がデザインされているものが多いです。
案内標識は、目的地までの距離や方角を示す標識です。一般道路でも高速道路でも至るところに適宜設置されているため、バイクやクルマの運転者にとっては非常に馴染みの深い標識のひとつでしょう。
指示標識には、“中央線”や“横断歩道”などが挙げられ、走行する際に必要な指示を表しています。“優先道路”なども示しており、基本的に青地に白で記号や文字がデザインされています。
警戒標識は、黄色を基調とした標識なのが特徴的です。“踏切あり”/“信号機あり”/“すべりやすい”/“動物が飛び出す恐れあり”など、運転する際にあらかじめ注意しておくべき事項が表されています。
また、これら4つの標識のほかにも“補助標識”が存在しており、それぞれの標識に付帯させることで標識の意味合いや具体的な適応範囲をより分かりやすく示しています。
補助標識には、例えば“8-20”といった時間帯を示すものや“この先100m”などの区間を示すもの、“原付を除く”など、適応される車両の区分を示すものがラインナップされています。
各標識の下に白地に黒文字の小さな標識が付帯していることがあります。標識の内容や適応範囲などを補足するものとなっているので、補助標識も必ず確認するようにしましょう。
それぞれの示す意味を知っておくことで、安全かつ円滑なバイクライフを楽しむことができます。“ついうっかり”な違反をなくすためにも、守るべき標識や標示の特徴をしっかりと押さえておきましょう。
※本記事は当該執筆者が寄稿したものであり、その文責は執筆者に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の記事
スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]
Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]
[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]
振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]
オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]
X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]
最新の記事
- 1
- 2