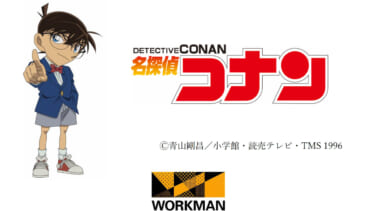2025年10月23日、ホンダから待望の正式発表となった「CB1000F」のメディア向け試乗会に参加してきた。前日も開催されていた試乗会は雨だったそうだが、日頃の行いのせいか明け方前には雨が上がり、ワインディングにバイクを持ち込んだ頃には路面もほとんど乾いていた。ここまで期待を膨らませたCB1000Fに良コンディションで乗れたことに感謝しつつ、レポートをお届けしたい。
●文:ヤングマシン編集部(ヨ) ●写真:長谷川徹 ●外部リンク:ホンダ
これぞCBだ! そう直感的に思えるライダーの視界
跨った瞬間に「CBだ!」と思えた。視界に入る燃料タンクの大きな面積や両腿の内側に感じる存在感、そして昔で言う“殿様乗り”が似合う大きくアップライトなライディングポジション、しっかりと受け止めてくれるシートのクッション厚と座面の広さ。少しディテールに目をやると、タンク上面の独特の盛り上がりや燃料タンクキャップの形状などに、まるで実家に帰ってきたかのような安心感を覚える。
これは本当に大事なことで、跨った最初の印象は、走っても眺めても、また長く所有していっても大きく外れていくことはないものなのだ。だからファーストインプレッションでそう思えたことが嬉しかった。
燃料タンクの背にある独特の盛り上がりラインがCB独自の特徴。これはCB750FからCB1300SFまでも引き継がれてきたディテールだ。
念のため筆者(1974年生まれ)の立ち位置を記しておこう。18歳でバイクの免許を取得した頃にCB1000スーパーフォア、いわゆるBIG-1が登場し、その後、街には弟分のCB400スーパーフォア(以下SF)があふれていった。1989年登場のカワサキ・ゼファーがレーサーレプリカ時代へのカウンターカルチャーとして大ブームをつくり、ホンダがCB400SFでレプリカ時代の終焉を決定づけたと言っていいだろう。
たまに見かけるCB1000SFには畏敬の念を覚えたものだったが、逆に新型CB1000Fにイメージが重なるCB750/900Fにはほとんど思い入れがない。当時も街でCB-Fを見かけることはあったが、ベテランのバイク好きが大切に乗っているバイクのひとつ、という薄めの認識だった。
バイク雑誌の業界に入ったのは初代CB1300SFとXJR1300がライバル模様を展開していた頃で、2003年にCB1300SFがフルモデルチェンジしてからは常に、仕事のかたわらにCB1300SFの大きな存在感があった。
だから筆者にとってCBの最高峰=フラッグシップCBと言えば『CB1300SF』であり、その大きさや馬鹿げたトルク感がビッグバイクの基準と言えるものだった。
改めて新作のCB1000Fを見ると、CB750F/900Fからイメージを継承したディテールも確かにあるものの、全体のたたずまいにはCB1300SFの後継ともいえる雰囲気があり、それでいてスリムで軽量、扱いやすそうなサイズ感に収まっている。
そこには1992年登場のCB1000SFから2025年のCB1300SFファイナルエディションまで受け継がれた「乗れるものなら乗ってみろ!」という巨大さはなく、250kgを超える車重もない。ただフラッグシップCBの存在感があるだけだ。
HONDA CB1000F[2025 model]主要諸元■全長2135 全幅835 全高1125 軸距1455 シート高795(各mm) 車重214kg(装備)■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 999cc 124ps-9000rpm 10.5kg-m/8000rpm 変速機6段 燃料タンク容量16L(無鉛プレミアムガソリン)■タイヤサイズF=120/70ZR17 R=180/55ZR17 ●価格:139万7000円 ●色:銀(青ストライプ)、銀(灰ストライプ)、黒 ●発売日:2025年11月14日
丸いヘッドライトやダブルホーン、そこそこのボリューム感が確保されたシートカウル、流麗なサイドカバー、ちょうどいいサイズ感のマフラーなども好ましい。旧車のようにタンク越しの視界にエンジンの左右シリンダーを望むことはできない(エンジンがコンパクトだから)が、巨大なエンジンを搭載していたCB1300SFでも大きなタンクの存在感に隠れがちだったことを思えば気にならない。
そうそう、5インチTFTのメーターは、読者の多くもご存じのように物議を醸している。メーカー開発者のプレゼンテーションではヤフーニュース等の「メーターがダサイ」といったコメントをスクリーンいっぱいに表示するなど、ホンダとしてもこの点がよくも悪くも話題になっていることは認識している。
それでもデジタルメーターの採用に踏み切ったのは、スマートフォン連携機能といった利便性が最新世代のバイクには欠かせないからだという。筆者個人としては砲弾型のアナログメーターにさほど思い入れがなく、またスマートフォンをバイクにマウントするのは面倒臭く感じるほうなので、メーターそのものがナビ画面として機能してくれるならそのほうがありがたい。
ちなみに、このTFTディスプレイは今後、アプリケーションのアップデートでフルマップのナビ画面が利用可能(CB1000Fはターンバイターン式)になることも想定した設計のようなので、購入後のさらなる利便性向上も期待できるかもしれない。
デザインや存在感だけでそこそこの文字数を費やしてしまった気もするが、各世代ごとのCBに対する思い入れはそれぞれ異なっているであろうことから、筆者の世代ではこう感じるということを最初にしっかりお伝えしておきたかった次第だ。
ちなみに、丸山浩さん(1964年生まれ)の世代はCB1000Fに往年のCB750F/900Fの面影を見いだすと言い、また1980年代以降に生まれた方はそれぞれのCB像でCB1000Fを解釈しているようである。
クランクが重くなったかのようなエンジンフィーリングと鼓動感のあるサウンド
エンジンを始動すると驚かされる。2010年に登場した空冷CB1100が1-2番と3-4番のカムタイミングをズラすことで脈動感を演出したのと同じ手法で、スーパースポーツCBR1000RR(SC77)の系譜にある4気筒エンジンに、旧車の空冷エンジンであるかのようなバラツキ感をあえて加えているのだ。
丸山浩さんが取材時に持ち込んだCB1100ベースの『Project F』(外装を往年のCB-Fのようにカスタムしたコンプリート車)とほぼ同じアイドリング音を発し、スロットルを軽くブリッピングしても、CBR1000RRベースを思わせるような鋭いレスポンスではなく、絶妙に角が丸められたようなフィーリング。
音量もメーカー純正としては「大丈夫?」と心配になるほど豊かで、閑静な住宅街ではあまり回転数を上げずに走った方がよさそうなレベル。音質も低くハスキーな「ズオオォォン」という感じで好ましく、純正マフラーでこれだけの豊かな音量と音質、デザイン性にもまとまりがあるなら、多くのユーザーにとってかなり満足感は高いはず。ここからカスタムでマフラー交換しようという気にさせるのは、それこそマフラーメーカーの腕の見せ所だろう。
改めてライディングポジションをチェックすると、シート高は795mmで足着き良好。シートの座面にそこそこ幅があるのと、足をまっすぐ下ろしたときにステップが当たりがちな点は、小柄な方だと少し気になるかもしれない。ただ、座面が広いのは走行時には乗り心地やコントロール性に寄与する部分なので、走るぶんにはこれが正解という気もした。ステップ位置も、走行時を基準にするならリラックスとコントロール性を両立したベストポジションだ。
テーパー形状のハンドルバーは幅が広めかつグリップ位置が高く、殿様乗りが似合う堂々としたポジションになる。ちなみに、シートの着座ポイントは兄弟モデルのCB1000ホーネットから35mmほど後退しているという。燃料タンクをニーグリップするとタンクの存在感はけっこうあるが、大きすぎることもなく自然に腿を沿わせやすかった。
身長167cmの丸山浩さんのライディングポジション。両足は母指球にしっかり体重が乗る感じで、スネにステップが当たるのがちょっと気になると言っていた。ライディングポジションは上半身が起きたアップライトなものだ。
参考までに身長183cmの筆者。膝の曲がりはだいたい90度で、ハンドルバーは手を伸ばした位置に自然に存在する。窮屈な感じはしない。
跨った状態でスロットルをブリッピングすると、排気音に加えて吸気音にも脈動があることに気づく。これはCB1000ホーネット比で細く長くなったファンネルを、気筒グループごとに開口部の口径を変えていることによる効果だという。
さあ、走りだそう。アシスト&スリッパークラッチを採用しているためクラッチレバーの操作はとても軽く、またアイドリング付近でも1000ccならではのトルクがあるため、なんの気負いもなくクラッチミート~発進できる。
ホーネット比では1~3速を低く設定し、全体に影響する2次減速比をロングに振ることで全体にワイドレシオ化している。これによりスロットルを操作せずに1速での発進することも難しくはなく、そこからスロットルを開けるとジワリとした出だしの、唐突さのない加速を見せる。
トルクが太い! というほどのフィーリングではないものの、街中の極低回転からでも必要十分以上の加速を得ることができる。車重が軽いこともあって、スロットルを大きく開ければ俊敏な加速も自在だ。
スパスパと決まるクイックシフター(スタンダード仕様ではオプション扱い)を使い、矢継ぎ早にシフトアップ。3000~4000rpmくらいでスロットルを大きめに開けたときの音と加速感が抜群に気持ちいい。ゴリゴリとした脈動感のあるサウンドとスムーズな加速、そしてスロットル開閉に敏感すぎないレスポンス。まるでクランクマスが重くなったかのように錯覚する(実際はホーネットから変わっていないとのこと)ような、どこか湿度感のあるトルクデリバリーだ。
クイックシフターは加速中/減速中を問わずシフトアップ/ダウンどちらにも対応する最新世代で、回転が落ち過ぎない限りはいつでも正確無比なシフトフィーリングを約束。無駄な遊びを切り詰めたセッティングは、スーパースポーツ由来のエンジンであることも思い出させてくれる。
ひらけた場所でスロットルをワイドオープンすれば、気持ちのいい脈動感が次第に収れんしていきながら回転が上がっていく。ここでもスムーズさは際立ち、上昇する途中でトルク特性が変化するようなこともなく、野太いサウンドをともないながら高回転域までフラットトルクのまま吹け上がる。最高出力124ps/9000rpmも乗り手を緊張させないよう躾けられていた。
一定速度のクルージングは大の得意で、スロットル操作に気を遣わずとも狙った速度を保ちやすい。スロットルの開けっぱなや閉じっぱなにも角はなく、脈動感に包まれながら、“このままツーリングに行きたいなぁ”とつぶやいてしまったほどだ。
スポーティな素性ながら万人が乗りやすく気持ちいいと思えるエンジン。ここにも「CBだ!」を感じずにはいられなかった。
軽快かつ穏やかなハンドリングに車重214kgが生きている!
ハンドリングは、ストリートファイターのCB1000ホーネットがベースとは思えないほど穏やかだ。といっても鈍重なわけではなく、ヒラリと軽快に寝かすことができて、鋭くというより綺麗に曲がっていく感じ。着座ポイントがホーネットより35mm後退していることもあってシートに体重を傾けるとリヤタイヤを感じ取りやすく、安心してカーブを駆け抜けていくことができる。
がっつりスポーティに走るというよりは、その一歩手前で流すような走りが気持ちいい。もちろんその気になれば応えてくれるが、バイクに急かされているような感じはまったくなく、ライダーはただ思うままのペースで走るだけでいいのだ。
少しマニアックな言い方をすれば、リヤ車高はやや低く、寝かしこみは軽いが鋭く曲がるタイプではない。シートに体重を預けながら長いコーナリングを楽しむタイプで、短く曲がってサッサと立ち上がるホーネットとは対照的。かといってフロントが遠回りするような雰囲気もなく、コーナリング中に細い木の枝なんかを踏んでも挙動が乱れることはなかった。そこから中速トルクを使って加速していくのもまた気持ちいい。
シートに体重を預けるとリヤサスペンションがググっと沈み、安定感をベースとしたコーナリングが楽しめる。
よく動くサスペンションは乗り心地重視の設定だ。ストローク中間から奥に行くほどに踏ん張り感は増すが、過渡の変化は自然かつ穏やか。フロントのSHOWA製SFF-BPはフルアジャスタブルで、リヤは伸び側減衰力とプリロードが調整できるので、スポーティに走りたい向きにはセッティングをおすすめしたい。
少しだけ気になるとすれば、フロントブレーキの利きはじめが、よく動くサスペンションに対してわずかに鋭い特性で、慣れるまでは丁寧なブレーキ操作を意識する必要があるという点。とはいえコーナー2~3つで慣れてしまうレベルではある。
スポーティな走りを意識してもボリュームのある燃料タンクは膝でホールドしやすい。サイドカバーの面も余分な凹凸がなく、スポーティな走りにおいてもライディングポジションで気になるところはなかった。ハンドルバーの高さは好み次第といったところだろうが、オフ車やクラシック系のネイキッドを好む筆者にとってはちょうどよかった。
こうした安定性ベースの車体でも軽快な感じを保っているのは、ひとえに214kgの車重ゆえだろう。250kgオーバーのCB1300SFとは比べようもないほど軽く、サイドスタンドからの引き起こしは少しの手応えを感じさせつつも不安はまったくない。それは走り出してからも同じで、街乗りからツーリング、そしてワインディングの快走まで、どこまでも軽快に疲れず走っていくことができそうだった。今回は短い時間の試乗会だったので、次はちょっと長い期間の試乗も行ってみたい。
電子制御スロットルを備え、ライディングモードはSPORT/STANDARD/RAINの3種類。SPORTにしてもレスポンスが鋭くなりすぎることはなく、ダイレクトでありつつ角のない反応が楽しめる。エンジンブレーキも少し弱まるので街乗りでも使いたくなるかも。STANDARDはレスポンスが優しくなり、多少おおざっぱなスロットルワークにも対応。とはいえ大きく開ければしっかりとパワーは出る。RAINは全体にソフトな出力特性になる。このほか6軸IMUによるコーナリングABSやホンダセレクタブルトルクコントロール(いわゆるトラコンに相当)も備えるが、今回のテスト環境ではそれを体感できる場面がなかった。
THE フラッグシップCB
1959年に登場したCB92(125cc)からはじまったホンダ「CB」は、1979年登場のCB750Fに至るまでスーパースポーツの立ち位置だったが、のちにそれをCBRシリーズへと譲り、1992年のCB1000SFで“ビッグネイキッド”へと進化した。
いずれも時代を彩ったホンダのバイクの頂点だったが、CB1000SF、CB1300SFと進化していく中で迫力を追求するあまり大きく重くなっていったのも確か。それゆえ和製クルーザーというか、“威風堂々”の側面が強調されすぎていたのかもしれない。
今回のCB1000Fは、スーパースポーツであるCBR1000RRの系譜に連なるエンジンを搭載し、基本骨格を共有する兄弟車のCB1000ホーネットが持つスポーティさを内包しながら、なんにでも使える汎用性を持った“普通のネイキッド”に仕立てられている。
“普通”というのはけっして悪い意味ではなく、むしろ“普遍に通じる”と言い換えてもいい。考えてみれば、昔は1台のバイクでツーリングにも峠にも行き、街乗りに使い、なんなら林道にチャレンジすることだってあった。そんな『これ1台!』の多用途性に対応する、シンプルな出で立ちのネイキッドこそが、バイクの王道と言っていいんじゃないだろうか。CB1000Fはその立ち位置に戻ってきたのだ。
威風堂々の大きさ重さを削った代わりに、扱いやすさと無類の汎用性を手に入れたCB1000F。これを特定のキャラクターに変化させたいなら、それはそれでいくらでもカスタムの余地がある。積載性を拡張すればツーリングマシンになり、スポーティさを追求するならホーネットの純正パーツを使ったカスタムも可能だろう。
これぞバイク! これぞCB! そう思えるバイクで心底ホッとした。いや、CB1300SFとともに業界キャリアを歩んできた身としては、こだわりがあるぶん納得できないバイクだったらどうしようって心配だったんですよ……。
よかった。よいバイクでした。偉そうな物言いですがお許しください。
今回試乗したのはスタンダード仕様に純正アクセサリーのクイックシフターを装着したもの。さまざまな追加装備を施した仕様のCB1000F SEは少し遅れて2026年1月16日に159万5000円で発売される。年間販売計画台数は5000台で、すでに1600台を受注。このうちスタンダード仕様が7割、SEが3割という構成だそうだ。
ヤングマシン12月号(無料購読できます)ではフレディ・スペンサーがCB1000Fを語り尽くす!
ホンダ CB1000F のディテール
HONDA CB1000F[2025 model]
HONDA CB1000F[2025 model]
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の関連記事(CB1000F)
機能を成立させた上で独創性と独自性を追求する 愛車を自分好みのスタイルや仕様に変更するカスタムは、ツーリングやサーキット走行と同様にバイクの楽しみ方のジャンルとして確立されている。そしてオリジナルパー[…]
ガレージREVOのリフトアップ方法 移動式バイクスタンドであるガレージREVOにとって、スタンドとバイクの接点は重要です。前後左右に押し歩く際にスタンドに載せたバイクが転倒しては一大事なので、スイング[…]
スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]
十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]
ハンドリングが選べる「コンバーチブルステムキット」 ストリートでの軽快さを求めるか、高速巡航での安定性を求めるか。一台のバイクで異なるキャラクターを楽しめるこのギミックは、走りにこだわるライダーにはた[…]
最新の関連記事(ホンダ [HONDA] | 試乗インプレッション/テスト)
久々に『コーナリング』と真剣に向き合うことになりました。 HondaGO BIKE LABでちょくちょくバイクに乗った感想文などをお届けさせてもらっている私(北岡)ですが、実のところ私の経歴というのは[…]
これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]
ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]
新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]
十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]
人気記事ランキング(全体)
日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]
7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]
GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]
ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]
グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]
最新の投稿記事(全体)
ドラレコの「配線地獄」はもう終わり! 車やバイクに乗るなら、もはやドライブレコーダーは必須装備だ。しかし、「面倒極まりない配線処理」で購入に踏み切れない方も多いのではないだろうか。ショップに頼めば工賃[…]
【第1位】ワークマン×『葬送のフリーレン』第2期コラボTシャツが登場! 人気アニメ「葬送のフリーレン」とワークマンの異色コラボが堂々の1位を獲得した。980円という驚愕の価格ながら、ふだん着やツーリン[…]
エモーショナルな体験ができる冒険ラリー オートバイ冒険家・風間深志氏が発案した日本最大級のツーリングラリー「SSTR2026(サンライズ・サンセット・ツーリングラリー2026)」が、2026年5月23[…]
久々に『コーナリング』と真剣に向き合うことになりました。 HondaGO BIKE LABでちょくちょくバイクに乗った感想文などをお届けさせてもらっている私(北岡)ですが、実のところ私の経歴というのは[…]
ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]
- 1
- 2