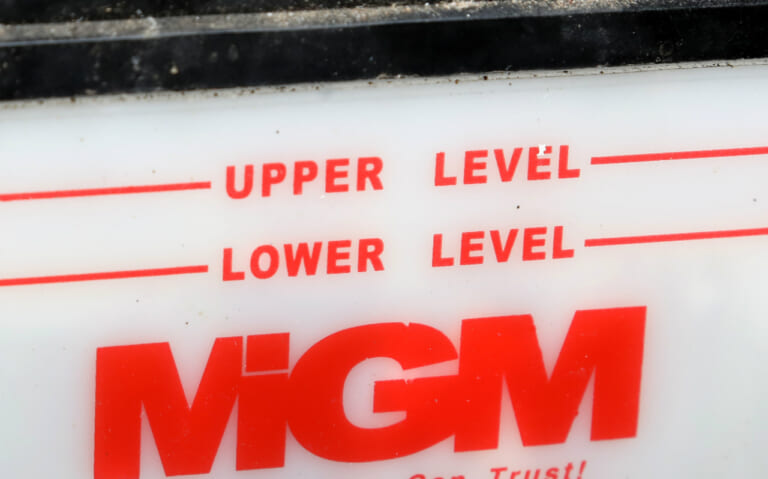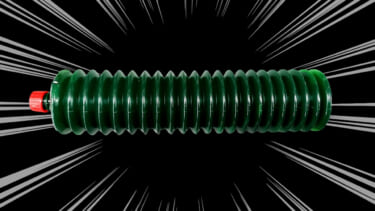セルが回らない、ヘッドライトが暗い……そんな「バイクバッテリー上がり」に直面すると焦ってしまいますよね。本記事では、バイクバッテリー上がりの原因を詳しく解説し、やってはいけないことから、正しい直し方までを一挙ご紹介します。押しがけやジャンプスターターを使った応急処置から、長期的な予防策まで、初心者の方でも実践できるノウハウをまとめました。
●文:ヤングマシン編集部(カイ) ●写真:橘 祐一
バイクバッテリー上がりの原因とは?
エンジン始動時のセルモーター駆動やヘッドライトの常時点灯、ABS制御、デジタルメーターなど、バイクは高性能化するにつれてバッテリーの負担がどんどん増加していきます。
今や電気=バッテリーはバイクにとっても最重要パーツとなり、バッテリー上がりは死活問題でありながらトラブル発生頻度の上位に挙げられています。ではなぜバッテリー上がりは起きるのでしょうか?
まずはバッテリー上がりの代表的な原因をチェックしましょう。
1. 長期間放置による自然放電
バッテリーは使わずにいると自然放電を起こし電力は目減りしていきます。日常的に走行していれば問題ありませんが、走行間隔が空く場合は注意が必要です。
2. 電装系の消し忘れ(ライトやグリップヒーター)
最近のモデルはヘッドライトが常時点灯されています。停車時にエンジンをきっているとバッテリーは電気を垂れ流している状態になります。また、USB電源をバッテリーから採っていたり、冬場にグリップヒーターを使用する際にも電力は消費されています。
3. バッテリーの経年劣化
バッテリーは消耗品です。バイクのバッテリーの場合、使用環境にもよりますが一般的に2年〜3年が寿命とされているので、劣化具合は定期的に確認しましょう。
4. 充電系統(レギュレーター/オルタネーター)の故障
充電システムが不調になった場合、バッテリーに電気が充電されないので、まだバッテリーが新しいとしても急にバッテリー上がりが発生するケースもあります。
5. 極端な寒暖差による性能低下
バッテリーは激しい高温でも性能を発揮しませんが、冬季や寒冷地対などでは寒さによって弱っていきます。
バッテリー上がりは様々な要因によって引き起こされる。もっとも多いのは長期間の放置によるものであり、いざ乗ろうとした時にバッテリーが空になって貴重な休日を無駄にした経験がある人は多いはずだ。
バイク バッテリー上がりでやってはいけないこと
いざバッテリー上がりに直面すると、焦って不適切な対応を施して事態を悪化させてしまう場合もあります。代表的なNG行為は以下のとおりです。
- セルをひたすら連打する
- 不適切なケーブル接続でジャンプスターターを使用する
- バッテリー端子に油脂や腐食を放置する
- 過放電状態で無理に押しがけを繰り返す
いずれもバッテリー上がりの対応策として不適切であるばかりか、状態によってはバイクを壊す行為にも繋がりかねませんので気をつけましょう。
バッテリー上がりではセルモーターをまわすだけの電力が足りなくなり、弱々しくしかモーターは駆動しない。このとき、何回も連続で回し続けるとバッテリーが完全に死んでしまう。回らなくなるまでセルモーターを押し続けるのは避けたい。
バイク バッテリー上がりの直し方
次に、安全かつ確実にバッテリー上がりを解消する方法をステップごとに解説します。状況に応じてそれぞれの方法を試してください。
押しがけで復活
昔からあるバッテリー上がり時にエンジンを始動させる方法に「押しがけ」があります。ギアを入れたバイクをひたすら押してクランクシャフトを回転させエンジンを始動する方法です。
ただし最近のフューエルインジェクション車の場合は少しでも電力が無いと始動できないこともあるので事前に調べておくのが賢明です。押しがけの手順は以下のとおりです。
- 事前準備:ニュートラル・クラッチを確認しキーON
- 押しがけ手順:ギアを2速以上に入れ、一定速度まで押してクラッチをつなぐ
- 注意点:無理な急停止や高いギアは避ける
キャブレター車の場合はほとんどの場合、押しがけでエンジンを始動させることが可能。バイクを人力で押すため力仕事であり、できることなら下り坂などを利用したい。クラッチをつなぐ時は半クラにせず、一気にクラッチレバーを離すこと。
ジャンプスターター・ジャンプケーブルでの応急処置
装備と環境が整っていれば、バッテリーに外部から充電して復活させるのが最良の手段です。必要なものは、ジャンプスターター(ケーブル)と電力の供給元(他のクルマやバイク、コンセントなど)です。
- 接続順序と極性の確認:バッテリーが上がったバイクのプラス端子→救援車のプラス端子→救援車のマイナス端子→バッテリーが上がったバイクのエンジンブロックなどの金属部分(ボディーアース)
- スターター使用時間の目安:30秒以内
- 使用後:すぐに走行してしっかり充電
最近はより簡単にバッテリーを充電できるハンディタイプのコンパクトなモバイルバッテリーも登場している。これならジャンプスターターも電力供給元のクルマやバイク、コンセントも不要だ。
バッテリー交換・補充電での復活
バッテリー上がりが起きた場合、バッテリーそのものが寿命を迎えている場合も少なくありません。その場合は充電してもすぐに放電してしまいますので、できるだけ早急に新品へ交換しましょう。
逆に寿命を迎えたと思ったバッテリーが復活する場合もあります。例えば液入りタイプのバッテリーは減ったバッテリー液を補充(蒸留水、強化液など)すれば本来に近い性能を取り戻すこともありますし、パルス式の充電器を使うと弱ったバッテリーが復活することもあります。
- 補充電器(メンテナンス充電器)を使った高効率充電
- 寿命が近い場合は新品へ交換
- 交換時にはバイクそれぞれで異なる規格のバッテリーに交換
オートバイ用バッテリーにはVRLA(制御弁式)と開放式の2種類が存在する。現在は車両多様化によるメンテナンスフリー性、コンパクト性のニーズが高まり、VRLA(制御弁式)タイプが主流だ。
小型軽量でメンテナンスフリーという特性をもつリチウムイオンバッテリーも普及してきた。また、従来の平板鉛蓄電池と比較して高い耐久性や高寿命、高始動性を兼ね備えたスパイラルセル方式のバッテリーも人気だ。
バイク バッテリー上がり対策
バッテリー上がりの再発を防ぐための予防策を以下にまとめます。
定期的なメンテナンス充電
長期保管前/後は必ずメンテナンス充電器で回復充電。また、しばらく乗る予定がない場合はバッテリーから端子を外しておくと安心です。ただし盗難防止装置が付いているバイクの場合は問題が発生することもあるので、適切な方法を取説などで確認してください。
充電はフルオートのものが便利。写真はディーラーなどでも使用されているオプティメート(旧型)で、バッテリーの型式や使用状況に応じて自動的に充電してくれる。万一の場合に備えてガレージに常備したいアイテムのひとつだ。
電装系の消し忘れ防止アイテム活用
電装系アイテムの消し忘れなどには、キー連動タイプやタイマー付き電源カットリレーの導入がスマート。
寒冷地・冬季対策
バッテリーを車体から外して室内保管(保温カバーを装着)すれば万全。
時期や環境、使用状況によってはバッテリーを完全にバイクから降ろして保存するのがベスト。保存する際には寒暖差が激しい場所や直射日光を避けるなどの工夫もしたい。
ツーリング前のセルチェックリスト
バッテリー上がりはほとんどの場合、事前に徴候がある。走行前にそうした兆候を見逃さずにチェックし、出先でのトラブルを避けるのが賢明。下記項目を参考に乗車前チェックする習慣をつけましょう。
- ヘッドライト・ウインカーを数秒点灯テスト
- バッテリー端子の緩み・腐食確認
- メーター上のバッテリーチェックランプ確認
バッテリー端子やリレー、ヒューズボックスなど、電子接点が腐食してバッテリートラブルに繋がるケースは少なくない。定期的に確認し、腐食を見つけたら交換しよう。また、乗車前にライトの強弱やセルモーターの回り方に異常がないかチェックする習慣をつけたい。
まとめ:安全・安心のために押さえるべきポイント
「バイク バッテリー上がり」の原因を知り、やってはいけないことを避け、正しい対処法をマスターすれば、突発的なトラブルでも慌てずに対応できます。
日頃からの対策(バッテリー上がり対策)を徹底して、快適なバイクライフを楽しみましょう!
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の関連記事(メンテナンス&レストア)
軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]
怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]
グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]
徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]
論より証拠! 試して実感その効果!! カーワックスやボディシャンプーなどを手掛けている老舗カー用品ブランドとして知られる『シュアラスター』。シュアラスター展開するLOOPシリーズはエンジン内部のコンデ[…]
最新の関連記事(ビギナー/初心者)
きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]
徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]
改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]
「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]
「一時停止違反」に、なる!/ならない!の境界線は? 警察庁は、毎年の交通違反の取り締まり状況を公開しています。 最新となる「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等につい[…]
人気記事ランキング(全体)
伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]
高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]
これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]
ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]
リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]
最新の投稿記事(全体)
兄弟車の「EM1 e:」よりも約10万円安い! ホンダは、原付一種の電動二輪パーソナルコミューター「ICON e:」を発表した。発売は2026年3月23日を予定しており、バッテリーと充電器を含めて22[…]
今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]
52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]
ワンメイクレース用に誕生した初のレーシングカー ディアブロSV-Rは、その名が示すとおりSVをベースとしたレーシングカー。1995年に、スイスの実業家、フィリップ・シャリオールによってディアブロのワン[…]
そもそも「吉方位」とは? 行くことで良い気を取り入れ、「パワー」を充電できるとされている方位。 自分にとって良いタイミングで良い方位に向かい良い気を取り入れることでパワーを充電でき、運気が整い各方面で[…]
- 1
- 2