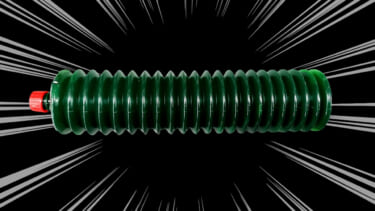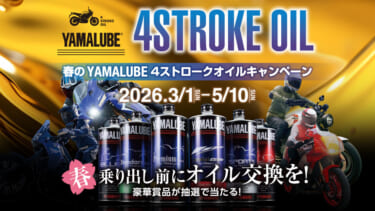ツーリング先や自宅で突然起きるバイクのパンク。最近は修理キットを使って「自分で直す」というライダーも増えています。しかし正しい知識がないまま行うと、再パンクや事故など思わぬトラブルの原因に……。本記事では、バイクのパンク修理を自分で行う際の注意点や落とし穴を、初心者でもわかるよう詳しく解説します。
●文:ヤングマシン編集部(カイ) ●写真:橘 祐一
バイクのパンク修理を自分でやるときに知っておきたい基本知識
どんなに注意して走っていても、路面の釘やネジなどを拾ってパンクすることは少なくありません。とくにバイクは路肩を走行する場合も多く、路肩には車道から弾かれたゴミや異物が多数存在します。
この物価高の中、タイヤ交換もままならないため、ご自分でタイヤを修理しようと考えるライダーも多いかと思いますので、パンク修理の基礎知識をお伝えしましょう。
チューブレスタイヤかチューブタイヤかを確認
まずは、修理するタイヤの種類を確認しましょう。バイクの場合は大きく分けてチューブレスタイヤか、チューブタイヤがあります。その名の通り、タイヤ本体とホイールの間にゴムチューブが挟まれているのがチューブタイヤ。そしてゴムチューブがないのがチューブレスタイヤで、現在の主流はチューブレスタイヤです。
パンク修理はタイヤの構造によって方法が異なるため、間違った方法で修理すると再パンクや大事故のリスクがあります。必ず修理するタイヤの種類と構造を理解してから修理を行いましょう。
自転車のパンク修理を経験したことがあれば、チューブタイヤを採用しているバイクのパンク修理は手順が同じで敷居は低いかもしれない。とはいえバイクのタイヤは重く、なかなか骨の折れる作業だ。結構な力仕事であることを覚悟して挑むべきだろう。
応急処置と本修理の違いを理解する
まず心に留めておくべきことは、パンク修理キットはあくまでも応急処置だということです。長距離・高速走行をする場合はショップでの本修理、またはタイヤ交換が必要です。
タイヤショップによっては応急ではないパンク修理メニューもありますが、それもパンク箇所の状態によっては修理が不可能になりますので、基本的にタイヤがパンクした場合は残念ながら交換すべきだと考えましょう。
チューブタイヤの場合、適切に修理すれば交換せずとも使用可能な場合はある。もちろんパンク箇所が小さく、引き裂きなどがない状態でしっかり処理されていることが前提だ。作業自体もチューブレスと比較すれば容易だ。
必要な道具・修理キットを準備する
現在主流のチューブレスタイヤをパンク修理する際、メジャーなパンク修理キットは「ロープタイプ/スクリュータイプ」になります。
その他にエアポンプやCO2ボンベ、プライヤー、カッター、石けん水なども用意しましょう。もちろんタイヤはバイクから外して作業するので、バイクスタンドや脱着工具も必要です。
左がチューブレスタイヤ用のパンク修理キット。トレッド面に穴を開けるスクリューリーマー、シール剤を埋め込むインサートニードル、穴を埋めるシール剤などがセットになっている。右はチューブタイヤ用の修理キット。接着剤とパッチが複数入っていた。
バイクのパンク修理を自分でやる時の手順と注意点
以下は、チューブレスタイヤのパンク修理キットを使った作業の手順を説明します。繰り返しになりますが、この作業はあくまでも応急修理ですので、修理完了後は速やかにタイヤ交換を行ってください、
パンク箇所の特定と初動対応
まずはバイクを安全な場所に停車し、センタースタンドやメンテナンススタンドで固定します。目視でタイヤ全体をチェックして、異物が刺さっている場合は位置をしっかり確認します。
この際、刺さっている異物は焦って抜かず、修理準備を整えてから作業を開始してください。
道路に落下したネジや釘は路肩に集まっていく。路肩を走ることが多いバイクはこのようにネジを拾ってパンクしがちだ。パンク修理する際は焦って抜いてしまわず、安全の確保と修理道具を準備して臨みたい。
穴あけ作業と修理剤挿入の落とし穴
まず第一段階は、ネジや釘などトレッドに刺さっている異物をプライヤーなどを使って引き抜きます。トレッド面の損傷を広げないよう慎重に行いましょう。
続いてシール剤を埋めるため、スクリューリーマーで穴を広げます。広げすぎると修理できなくなるので注意。また、タイヤのワイヤー部分を傷つけてしまうと応急修理とはいえタイヤ自体の寿命が損なわれるのでここも慎重に作業します。
しっかり最後まで穴を開けきったら、インサートニードルの先端にシール剤を通して穴に挿入します。ロープタイプのシール剤は奥までしっかり差し込みますが、かなり力が必要な場合がありますので、根気よく行いましょう。
しっかりシール剤が穴を塞いだら、飛び出した部分はハサミやペンチなどで必ずカットします。この際、トレッド面ギリギリでなくとも大丈夫です。
スクリューリーマーで穴を広げる(写真左)。不安定なタイヤのトレッド面に差し込んでいくので力が逃げ、一筋縄ではいかない作業だ。続いてインサートニードルの先端に挟んだインサート剤を押し込む。これも力が必要だから根性でやり遂げよう。
しっかりと奥まで差し込んだインサートニードルを引き抜くと、インサート剤だけが残ってパンク箇所を埋めてくれる。余ったインサート剤はハサミやペンチでカットする。多少出っ張っていても空気が漏れることはない。
空気を入れて漏れ確認
インサート剤で穴を埋めたら修理は完了。抜けてしまったエアーを補充するには、電動エアポンプが便利です。近頃はモバイルバッテリーとしても使える安価な中華製がたくさん売られているので、パンク時だけでなくとも役立ちます。
電動エアポンプやCO2ボンベで規定空気圧まで補充し、パンク修理箇所に石けん水などを塗ってエアー漏れがないか確認すれば終了です。
もし空気が漏れる場合は無理に走らず、JAFやロードサービスを呼んでプロに依頼しましょう。
パンク箇所を修理したらエアーを補充する。最近はハンディタイプの電動エアポンプが安価で売られているから利用したい。空気圧計がついた電動エアポンプもあるが当てにならないケースも多いから、正確な数値は専用のエアゲージで測定すべきだろう。
よくある失敗例(落とし穴)と再発防止のポイント
パンク修理は多くの人にとって慣れない作業であるため、穴を複数空けてしまい修理不能にしてしまうこともあるようです。また、古い修理キットを使用し、シール剤の粘着力不足で再パンク!なんてことも。
適正な空気圧を入れてなかった場合、空気圧不足で走行してタイヤやホイールを損傷したという事例もありますし、応急処置のまま長距離や高速道路を走行してまたパンクしたという話もあるので、修理前後にしっかり確認してください。
それでも不安な場合はプロに相談
パンク修理は装備があったとしても想像以上に重労働です。あくまで応急処置で後々タイヤ交換が必須なら自分でパンク修理にチャレンジするより、最初からJAFやバイク専門ロードサービスを呼びましょう。最寄りのバイクショップやタイヤ専門店で本修理や交換したほうが安心です。
また、突発的に発生するパンクの場合は路肩などで作業することになりますが、安全確保が非常に困難です。特に夜間・高速道路では無理せず安全を最優先にし、誰かの助けを請うことも視野に入れてください。
パンクを完全に防ぐことは難しいが、例えばタイヤの製造年を確認してフレッシュなタイヤにしておけば、サイドウォールのひび割れによるパンクの確率は下げられるし、チューブタイヤなら予備のチューブを携帯すれば交換作業は短縮できる。
正しい知識をもって万全の準備をしてからチャレンジすべし
バイクのパンク修理を自分で行うのはライダーにとって心強いスキルですが、正しい知識と準備が不可欠です。穴あけや修理剤の使い方など小さなミスが大きなトラブルにつながるため、注意点をしっかり確認しましょう。
そして出先のパンク修理は安全な作業環境を得られにくいケースも多いし、時間的な制約も発生するので、不安な場合は無理せずプロに相談するのが安全です。
スーパーカブ程度の車体サイズでチューブタイヤなら、パンク修理のハードルは高くない。とはいえタイヤ脱着工具や修理キットも必要になるから、無理せずバイクショップに任せてしまうの賢い選択だ。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の関連記事(メンテナンス&レストア)
軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]
怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]
グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]
徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]
論より証拠! 試して実感その効果!! カーワックスやボディシャンプーなどを手掛けている老舗カー用品ブランドとして知られる『シュアラスター』。シュアラスター展開するLOOPシリーズはエンジン内部のコンデ[…]
最新の関連記事(タイヤ)
オンロード80%、オフロード20%の使用を想定 ミシュランから、2019年に登場した初代アナキーアドベンチャーの後継モデルが登場する。その名も「MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 2([…]
ドライグリップを最大化した公道用タイヤ 2020年の年初に発売され、各メーカーのスーパースポーツマシンにOEM装着されてきたレーシングストリートRS11に後継モデルが登場した。 新作のバトラックスレー[…]
JMS2025のダンロップブースに出現 世界中で人気のアドベンチャーバイクだが、地域によって走行シチュエーションは異なり、日本国内ではほとんどオンロード専用ツアラーのように振る舞っているのに対し、欧米[…]
タイヤの内圧規定ってなんだ? 今シーズン、MotoGPクラスでたびたび話題になっているタイヤの「内圧規定」。MotoGPをTV観戦しているファンの方なら、この言葉を耳にしたことがあるでしょう。 ときに[…]
インプレッションタイヤ:スポーツマックスQ5S/Q5A/Q5 スポーツマックスQ5S ストリートからサーキットまでカバーする、優れた運動性能のハイグリップタイヤ。絶大なグリップ力を誇るレース用微粒子カ[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]
ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]
最新の投稿記事(全体)
2026年モデル Kawasaki Z900RS SE に適合するTRICKSTAR製品の情報が確定! 世界耐久選手権(EWC)などで培ったレーシングテクノロジーをフィードバックす[…]
憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]
8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]
なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]
平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]
- 1
- 2