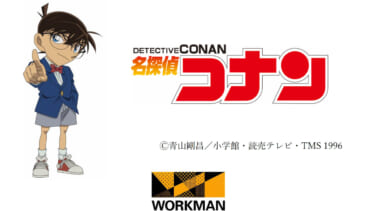元MotoGPライダーの青木宣篤さんがお届けするマニアックなレース記事が上毛グランプリ新聞。1997年にGP500でルーキーイヤーながらランキング3位に入ったほか、プロトンKRやスズキでモトGPマシンの開発ライダーとして長年にわたって知見を蓄えてきたのがノブ青木こと青木宣篤さんだ。WEBヤングマシンで監修を務める「上毛GP新聞」。第14回は、「マルケス乗り」を変えられないマルクと、現代版ミック・ドゥーハンと化してきたバニャイアの来季を早くも占う。
●監修:青木宣篤 ●まとめ:高橋剛 ●写真:Michelin, Red Bull
「なんでマルケスなの!?」「んー、あー……」
来シーズン、ドゥカティ・ファクトリー入りが確実視されていたホルヘ・マルティンがまさかのアプリリアに移籍。そのシートには、マルク・マルケスが……。
26歳で乗りに乗っているマルティンではなく、31歳で手負いのマルケスを選んだドゥカティ・ファクトリー。この決断からは、純粋なスポーツ要素とはちょっと違う意味合いが見えてくる。
サイモン・クラファーがドゥカティ・ファクトリーチームマネージャーのダビデ・タルドッツィに「なんでマルケスなの!?」とズバッと聞いていたが、タルドッツィさん、「んー、あー……」としどろもどろになりつつ、絞り出すように「旧型マシンでも、新型マシンと変わらないパフォーマンスを見せていたから……」と言っていた。
どうにかマルケスを選んだ表向きの理由を答えたタルドッツィさん。さすがに「マルケスの方が客を呼べるから」とは言わなかった。レースはスポーツだが、興行でもある。だからマーケティング的な視点は大切な要素だ。そのことは十分に理解できる。だがタルドッツィさんも、「マルティンを選ばなかった理由」を聞かれたら、きっと答えられなかっただろうな~、と思う。
パフォーマンスを見せたから? マーケティングから?
前回に引き続き何度でも言うが、マルケスの類い稀な才能は、疑いの余地がない。しかし、彼の最大の武器は、脊椎反射だ。30代になり、大きなケガも負い、どうしたって反射は衰える。勝ちまくっていたホンダでの全盛期のようには行かないだろう。
一方のマルティンは、ライダーとして一番いい時期だ。上り調子の今、もっとも勝てるドゥカティ陣営を離れることは、苦渋の選択だっただろう。もしかしたら「てめえら、覚えてろよ!」と発奮して、来年は下剋上があるかもしれないが、現実的にはアプリリアとドゥカティの戦闘力の差は大きく、かなり厳しい。
落とし所は、ギャラ以外ちょっと考えられない。多数のライダーを抱えているドゥカティに比べるから、アプリリア・ファクトリーの方がギャラはいいから、マルティンはそこでどうにか納得したはずだ。プロライダーなのだから、そういう選択もアリだ。
ただ、独走状態に入ったバニャイアを止められるのはマルティンしかいない今、彼がドゥカティを離脱してしまうのは、本当にもったいない……。来年に向けてはチーム&ライダーがいろいろシャッフルされているが、やはりバニャイアが最強だろうし、そこに立ち向かえるのはマルティンだったはずだ。
「ちょっと待て、マルケスがいるじゃないか!」と思う人も多いだろう。しかしここ数戦でドゥカティ・デスモセディチにだいぶ慣れたマルケスが、結局フロントからパタパタと転んでいる様子を見ると、「うーむ……」と首を傾げざるを得ない。
なぜ速く走れるのか、理解を超えるマルケスだが……
マルケスは、徹底的にフロントタイヤをこじって走る。相当に特殊な乗り方だ。最大ブレーキからすぐにパッとブレーキを離し、パーシャル状態でハンドルをギューッとインに切る。当然マシンは起きようとするのだが、高い身体能力で体をイン側に入れ込み、無理矢理ハンドルで曲げてしまうのだ。
……まぁちょっと普通には理解できないライディングだ。なぜこれで速く走れるのか、ワタシには未だによく分からない(笑)。マシンが起きようとしていることもあり、スロットルは開けやすいのかもしれないが、フロントタイヤを相当にこじることになるので、リスクは高い。
マルケスらしい独特のフォーム。
こちらはバニャイア。
実際、ワンメイクタイヤがブリヂストンからミシュランに替わったあたりから、フロントからスコスコと転ぶマルケスの姿が目立つようになった。ミシュランタイヤはリヤタイヤが非常に高いグリップ力を発揮するので、相対的にフロントが弱くなってしまうからだ。
それでも当時のホンダは、どうにかマルケスの特殊なライディングに合わせたマシンを作り、体裁を整え、結果を残した。その弊害としてホンダはマルケスしか乗れないマシンになり、マルケスがケガをして離脱すると、誰も結果が出せなくなって、現在に至っている。
そして、シーズン序盤は「ドゥカティ乗り」に適応しようとしていたマルケスだが、どうやら「マルケス乗り」を変えることができず、フロントからの転倒が目立ち始めている。デスモセディチは縦剛性こそ強いものの、横剛性は(恐らくあえて)低くしてあり、フロントをこじりまくるマルケスの走りには対応できないのだ。
では来年ドゥカティ・ファクトリーが「マルケス・スペシャル」を作るかと言えば、答えは明確にノーだとワタシは思う。来年のドゥカティは3チーム・6台体制となり、うち3台が最新仕様のファクトリーマシンになると言われている。今年までの8台に比べれば2台減ることになるが、それでも大所帯だ。
しかも、バニャイアは別格としても、みんなそこそこ好成績を残している。そこにマルケスが参入して「オレだけのスペシャルマシンを作ってくれ」と要求しても、いくらなんでもそれは通らないだろう。最大公約数的な開発姿勢で築き上げた「ドゥカティ栄光の時代」を、ひとりのライダーのために崩すわけにはいかない。
……ということで、ワタシは来年もバニャイアの強さが続くと思う。最強のライバルになるはずだったマルティンはアプリリアに移籍してしまうし、マルケスは自分の乗り方を変えられない。
それにしても、バニャイアである。実はものすごいことをやってのけているのに、あまりにもサラッとしているものだから、どうもすごさが伝わりにくい(笑)。いとも簡単にライバルをブッちぎる様子は、現代版ミック・ドゥーハンと言えるのかもしれない。
表彰台にたびたび登壇するなど速さは見せるが、ランキングトップのバニャイアのとポイント差はジリジリと開き始めている。
1997年イモラGPの青木宣篤(2位)、青木拓磨(3位)以来、27年ぶり2例目の最高峰クラスでの兄弟表彰台となったドイツGP。マルクが2位、アレックスが3位だった。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
最新の関連記事([連載] 青木宣篤の上毛GP新聞)
短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]
派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]
ブレーキ以上の制動力を求める進入、スピンレートの黄金比を求める加速 ライディングにおけるスライドは、大きく分けて2種類ある。ひとつはコーナー進入でのスライド、もうひとつはコーナー立ち上がりでのスライド[…]
実は相当ハードなスポーツなのだ 間もなくマレーシア・セパンサーキットにMotoGPマシンの咆哮が響き渡る。1月29日〜31日にはテストライダーやルーキーたちが参加するシェイクダウンテストが行われ、2月[…]
車体剛性を見極めるホンダ、V4を投入するヤマハ ホンダは終盤にやや盛り返した感もあったが、依然不安定だ。それでもシャシーはだいぶよくなった。恐らく車体剛性のカンを押さえることができてきて、剛性を落とす[…]
最新の関連記事(モトGP)
現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]
SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]
開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]
短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]
派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]
人気記事ランキング(全体)
日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]
7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]
GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]
ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]
グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]
最新の投稿記事(全体)
ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]
現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]
河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]
スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]
GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]
- 1
- 2