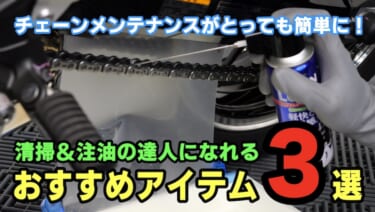初代登場時からずっと125ccエンジンを搭載しているホンダ・グロムに、ななんと250ccエンジン搭載車が現れた?! このチートマシンは初代グロム(JC61)に同じくホンダのCBR250R(MC41)用の水冷250cc単気筒エンジンをスワップしたもので、排気量は2倍、パワーはなんと約3倍!! このたび試乗機会を得たこの魔改造グロム、どんな走りを見せるのか?
●文と写真:ヤングマシン編集部(マツ) ●取材協力:京葉スピードランド
パワーは3倍!! はたしてまともに走るのか?
“エンジンスワップ”は昔から改造マニアのロマンである。エンジンを他機種用に積み替えるというカスタムは明らかに正統派ではなく、車両メーカーが構築したバランスが崩れてしまうのも否めない。それでもメーカーのお仕着せを望まず、自分だけの理想の1台を追求しようとする、その究極的な行為だからこそロマンなのだ(と思いますがいかがでしょう?)。
そして今、筆者の前にあるのはノーマルの2倍の排気量を持つ「グロム250」である。ベースは2013年に登場した初代グロム(JC61)で、本来搭載されている124ccの空冷OHC2バルブ単気筒は、同じホンダのCBR250R(MC41)用の249cc水冷DOHC4バルブ単気筒に換装され、最高出力はノーマルグロムの9.8psから29ps(ともにカタログ値)と、なんと約3倍にも達している魔改造マシンだ。そんなバイク、はたしてまともに走るものなのか?
本場アメリカでは人気スワップベース?
【ホンダ・グロム250(カスタム車)】
オーナーの鈴木政人さんによると、エンジン換装にはアメリカで発売されているマウントキットを使っており、電装系やハーネス類はMC41をそのまま流用。エンジンもMC41のノーマルだが、取り回し変更が必要な排気系や、MC41のままではフレームに干渉する吸気系は鈴木さんが自らモディファイしている。
今回はとりあえず走れるように組み上げた状態で、本格的に走らせるのはご本人も初めて。とくに最終減速はチェーンが車体に干渉したため415サイズ化(グロムは420、MC41は520)しているが、グロム用の415ドリブンスプロケは品薄だそうで、暫定的に組んだ現状の二次減速比は19✕33T。JC61グロム(15✕34T)比で言えばかなりロングに振られている。
鈴木さんによると、アメリカではグロムのエンジンスワップはメジャーらしく、ホンダCBR500RやヤマハMT-07のパラツインを積んでいる例もあるという。それと比べればキットがあるMC41換装は普通なのかもしれないが、それでも日本に存在するグロム250は両手の指に満たないだろう(その後、筆者がお世話になっている和光2りんかんさんで、同様のスワップマシン(しかも公道仕様)を2台もパワーチェックしていることが判明しました)。
初代グロム(JC61)に、CBR250R(MC41)用の水冷単気筒をスワップ。車体に対するエンジンの大きさはおかしいものの(笑)、割と違和感なく収まっている?! 車体はJC61のスタンダードだが、フロントフォーク内部パーツとリヤショックはシフトアップ製のパーツでグレードアップされている。
エンジン本体はMC41のノーマルをそのまま搭載。センターアップに変更された排気系は鈴木さんによる自作品で、吸気系もMC41のままではフレームと干渉するため、これも鈴木さんが取り回しを変更。この位置にパワーフィルターが露出する。
エンジンマウントはアメリカのCHIMERA ENGINEERING製のスワップキットを使用(グロムだけでなくモンキー125にも使用可)。同社は削り出しのインマニやラジエターなど、CBR250R/300R用エンジンをグロムに搭載するためのパーツを多数用意している。
スロットル周辺はMC41のままだとフレームに干渉するため、シリコンホースで向きを変えて暫定的に装着される。補助メーターで見えにくいが、計器類もMC41のノーマルを使用している。
違和感ほとんどナシ。これがノーマルでもいいぐらい?
今回はご縁あって試乗の機会をいただいたのだが、車両は完成したばかりで今回がほぼ初走行。当然ナンバーもないので千葉県長生郡のミニバイクコース・京葉スピードランドでの試乗となった。ちなみに筆者は学生時代、NSR50でお遊びレースに出たりしていた経験はあるものの、12インチのミニバイクでサーキット走行するのはほぼ30年ぶり。しかも京葉も初走行である。
まずはノーマルの感触を掴もうと、やはり鈴木さんが所有する2代目グロムでコースイン。とはいえこちらも164cc化を筆頭にカスタムされていてかなり速く、かつ安心感もあって1周650mの京葉スピードランドを楽しく走れる。先述のとおり、筆者はかなり久々のサーキット走行だったが、それでも楽しめたのはグロムの扱いやすさに負うところが大きいと思う。
そしてグロム250に乗り換える。またがって車体を左右に振るだけでも、換装されたエンジンの重量感がずっしりと伝わってくる。ノーマルのグロムで同じことをしてもほとんど重さは感じないが、そこは水冷250cc。エンジン単体重量は空冷125ccよりかなり重いはずだ(鈴木さんによれば「+10〜15kgぐらいかな?」とのこと)。
しかし、違和感と言える違和感はほぼそれだけだった。コースインしてまず感じるのは、164ccグロムに対する圧倒的なトルク感だ。どこから開けてもタタタタッと明瞭な鼓動感を放ちつつ、車体がぐぐぐっと前に進む。京葉のコースでは3速だけでもそこそこ走れてしまうほどで、30年ぶりのリターンミニバイカーにはグロム164よりむしろ走りやすいほどだ。
でも全開にしたらさぞアブナイんじゃないの…と思いきや、ズ太いトルク感をそのままに車速がグングン高まっていくようなフィーリングなので、身構えるような怖さがほとんどない。エンジン特性がある回転域からビュッと立ち上がるような、二次曲線的な特性ではないことが大きいのだと思うが、数周もするとアクセル全開、レブリミッターまで引っ張れるようになってしまった。
後続を確認しつつ、1速でゼロ発進からの全開加速も試してみたが、フロントが浮きまくってヤバい…といった危うさもない。このへんは二次減速比(繰り返すが現状は暫定)も関係するから、ショートに振ればウイリーマシンにも仕立てられるのだろうが、そんな潜在能力を忘れるほど普通に乗れてしまう。黙って乗せたら「やたらトルクのあるグロムですね」と、エンジンスワップに気づかない可能性すらありそうだ。
思いのほか走りやすいグロム250。開ければどこからでも前に進むため、テスター(筆者)のしょぼいスキルも助けてくれる。
車体も、少なくともミニバイクコースのスピード領域では何の問題も感じられなかった。加速時にハンドルが取られたり、リヤタイヤが激しくスライドなんてこともない。シフトアップ後にスロットルを急開するとかなり強くドンツキが出て車体姿勢が乱れるが、これはエンジン側の制御などの問題だろう。
さらに驚いたのがハンドリングで、走り出すとグロム164と感覚的にほとんど変わらないのだ。不思議なことに、またがったときのようなエンジンの重さも感じない。これは仮説なのだけど、換装されたMC41エンジンはかなり前傾して積まれているので、結果的に横型シリンダーのノーマルグロムに近い重心位置や重量配分になっているのでないか。
というわけで魔改造なグロム250は拍子抜けするほど乗りやすく、バランスの悪さもとくに感じない…という、意外にもほどがありすぎる展開になってしまった。しまったのだが、だからこそ逆に、頭の中でムクムクと広がってくる妄想があった。このパッケージには可能性があるのではないか?
予想外の好バランスに、思わず妄想が膨らむ!
古くはYSR50やNSR50、現行車で言えばグロムを筆頭にモンキーやダックスといった12インチホイール車って、小型軽量で足着き性も良好と、基本的な特性として誰にでも乗りやすいフレンドリーさを備えている。しかし排気量は大きくても原付二種の枠に留まっており“ミニバイク”という枠からは逸脱できずにいる。
ここに250ccクラスのエンジンを搭載すれば“新種”が作れるのではないか? 排気量に少し余裕を持たせて低速型に味付けすれば、手軽さを保ったまま高速にも乗れるツーリングバイクにもできるし、ギヤ比やエンジン特性の設定次第では、250ccにもかかわらず全開加速でフロントが浮くぐらいの、ちょい過激なライトウェイトスポーツにもチューニングが可能なのではないか?
12インチ車も250cc車も、そもそもが高価な機種ではないうえに、基本的にあり物の組み合わせで済む。排ガス規制もベース車でクリア済みだし、小型軽量で排気量がそう大きくないのもイマ風だ。インドあたりで200ccクラスのモーターサイクルがトレンドになりつつあると聞けば、マーケットもありそうに思える…。
素人にもかかわらず、偉そうについそんなことを考えてしまったのも、単純にグロム250が面白かったから。過去に乗ったどんなバイクにも似ていないから走らせていてとても新鮮で、かといって命や免許が危うくなるようなモンスターでは全然ない。いかがでしょうメーカーさん!! 試しに1台、テスト車でも作ってみませんか?
取材に協力してくれたオーナーの鈴木さん(左から3人目)とそのお仲間さんたち。今回は2台のグロムに加えてNSR50とNSR80、さらにスーパーカブ110(!)と計5台を京葉に持ち込み、皆で交代しながら楽しんでいた。筆者も丸1日、楽しませていただきました(メチャクチャ暑かったけどね…)。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の関連記事(カスタム&パーツ)
PERFORMANCE MACHINE|Race Series エンジン/トランスミッションカバー 高品質なビレットパーツで世界的な知名度を誇るPerformance Machine(パフォーマンスマ[…]
いま注目を集めているラッピングで印象を変える エキゾーストシステムに内臓した可変バルブを電子制御することによって、ハンドルにあるボタンひとつで音量が変えられるジキル&ハイドマフラーや、取り回し[…]
色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]
スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]
終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]
最新の関連記事(レース)
SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]
“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]
開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]
短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]
X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]
人気記事ランキング(全体)
7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]
簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]
WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]
世代をまたくトップライダーたちのレプリカモデルが一気に3種も登場 『DIGGIA2』は、2024年12月にも発売された、MotoGPライダーのファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル第2弾[…]
製品名がグラフィック化されたユニークなモデルのニューカラー 『GT-Air3 MIKE』は、その製品名を巧みに図案化したグラフィックを特徴とするモデルで、2025年10月に発売された。このたび発表され[…]
最新の投稿記事(全体)
グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]
ガレージREVOのリフトアップ方法 移動式バイクスタンドであるガレージREVOにとって、スタンドとバイクの接点は重要です。前後左右に押し歩く際にスタンドに載せたバイクが転倒しては一大事なので、スイング[…]
Screenshot 便利なアイテムでチェーン注油とチェーン清掃が簡単作業に変身 日常的なバイクメンテナンスの代表格といえば洗車ですが、その次に作業頻度が高いと思われるのは「チェーンメンテナンス」です[…]
PERFORMANCE MACHINE|Race Series エンジン/トランスミッションカバー 高品質なビレットパーツで世界的な知名度を誇るPerformance Machine(パフォーマンスマ[…]
SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]
- 1
- 2