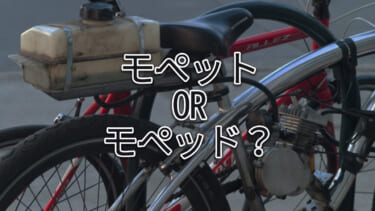![[バイクライテクQ&A] 半クラッチ発進を毎回同じようにスムーズに行うコツ](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/11/rh-clutch.jpg)
●文:根本健(ライドハイ編集部) ●写真:藤原らんか
じつはベテランも毎回同じにできていない
半クラッチはブレーキやギヤチェンジに次いでリクエストの多い課題。その半クラ発進、じつはベテランでもその都度少し違ったクラッチミートになっていて、毎回ピッタリ同じにできないのだ。その理由をクラッチの構造から説明していくと…。
クラッチはエンジンのシリンダーやクランクシャフトのすぐ後ろ、写真の赤い○で囲んだ膨らみがそれだ。
この丸い膨らみの内側には、ご覧のように薄くて細い円盤状で、コルクのような表面で外にツメがでているプレートと、スチールの円盤で内側にギザギザが刻んであるプレートとが、交互に組み込んであるユニットがある。これがクラッチの正体で、コルクに似た材質が貼ってるのがフリクションプレート、スチールのほうをクラッチプレートと呼んでいる。
外のツメと内側のギザギザが、エンジンからの駆動を受けている外側と、ミッションからドライブスプロケットへ繋がっている内側のカウンターシャフトとで、密着したり離れたりでエンジン駆動を切ったり繋いだりする仕組みだ。
これが実際にどんな動きで半クラッチになるのか、イラストの略図をご覧いただこう。見やすくするため、フリクションプレート3枚/クラッチプレート2枚の構造で描いたが、実際には写真にあるようにフリクションプレート9枚/クラッチプレート8枚ともっと多い。
このフリクションとクラッチの両プレートが、スプリングで圧着しているのを、クラッチレバーの操作でお互いが離れれば駆動が繋がらない、つまりクラッチを切った状態で、クラッチレバーを少し引いた位置のお互いの密着が弱くなり、徐々に滑るのが半クラッチと呼ばれる状態だ。
そしてややこしいのが、勢いよく半クラしたとき。お互いが滑って摩擦熱を生じるため、両方のプレートが熱膨張、つまり隙間というより圧着度合いがいきなり変わり、食いついてすぐ繋がった状態になってしまうため、半クラッチ状態が維持できない。ピョコンとフロントが持ち上がったり、エンジン回転がいきなり落ちたりと、スムーズを欠く状態に陥る。
レースライダーはこの膨張するのに合わせてクラッチレバーをわずかに引く調整をして、安定した半クラッチ状態をつくったりするが、これも膨張率が安定しにくいため、なかなか一定にはできない。
ということで、バリバリのキャリアでも、ゆっくり穏やかに発進するときは問題なくても、ちょっと頑張ろうとすると失敗する確立が高くなる、というわけだ。
探りながらレバー操作せず、繋がる半クラ位置だけを使う。そのレバー位置をアジャストしておくのが大事
そうしたムズカシイ操作はともかく、通常の発進では熱膨張もわずかなので、安定した半クラ発進が可能だ。
ただ、なんとなくクラッチレバーを操作するのでは、毎回どこで繋がるか変わってしまう。そうならないように、クラッチレバーのストローク位置と、機能との関係をあらかじめ確認して感覚を掴んでおくのが不可欠だ。
ここでビギナーがやりがちなのが……
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
ライドハイの最新記事
高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]
大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]
インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]
400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]
アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]
最新の関連記事(ライディングテクニック)
ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]
シリーズ第12回は最終回特別応用偏! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運転のお手本として白バイ流の[…]
シリーズ第11回はクイーンスターズ・スペシャルQ&A! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運[…]
シリーズ第10回は『クイーンスターズ』に学ぶ「取り回し」だ! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運転[…]
シリーズ第9回は『クイーンスターズ』と一緒に「引き起こし」だ! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運[…]
最新の関連記事(Q&A)
スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]
Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]
[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]
振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]
オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]
ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]
最新の投稿記事(全体)
Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]
最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]
伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]
ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]
ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]
- 1
- 2


![クラッチ|[バイクライテクQ&A] 半クラッチ発進を毎回同じようにスムーズに行うコツ](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/11/ride-knowledge_164_01-768x432.jpg)
![クラッチ|[バイクライテクQ&A] 半クラッチ発進を毎回同じようにスムーズに行うコツ](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/11/ride-knowledge_164_02-768x432.jpg)
![クラッチ|フリクションプレート/クラッチプレート|[バイクライテクQ&A] 半クラッチ発進を毎回同じようにスムーズに行うコツ](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/11/ride-knowledge_164_03-768x432.jpg)
![クラッチの動き|[バイクライテクQ&A] 半クラッチ発進を毎回同じようにスムーズに行うコツ](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/11/ride-knowledge_164_04-768x432.jpg)