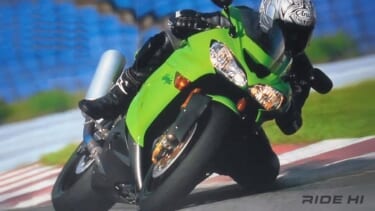![[バイク雑学] ホンダ新型CL250/500の純正フラットシートから、国産バイクのシート&足着き性の変遷を考察【1980年代以降、薄く低く?】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/th_MW_00017_RE.jpg)
●文:モーサイ編集部(中村友彦) ●写真:渡辺昌彦
ホンダの新しい試みに感心=CL250/500は低価格で純正ハイシートを用意
本国仕様や輸出仕様のシート、あるいは純正アクセサリーのハイシートを装着すると、乗り心地と着座位置の自由度が向上し、ハンドリングが軽快になる──。1990年代以降の日本で販売されたロードモデルに対して、僕はこれまでに何度もそんな印象を抱いている。では、そもそもどうして1990年代以降の日本で、シートが低い車両が増えたのかというと、乗り心地や自由度や軽快さより、良好な足着き性を求めるライダーが多くなったからだろう。
2023年5月に発売されたホンダCL250/500も、そういった事例に該当するモデルだが、近年のシートが低い車両と同列で語るべきではないと僕は感じている。というのも、まず開発ベースになったレブル250/500と比較すれば、CL250/500のノーマルシートは格段に好感触なのだ。しかも、乗り心地と自由度と軽快さに磨きがかかる純正アクセサリーのフラットシート(座面高はノーマル+30mmの820mm)の価格は、既存の常識で考えれば激安と言って差し支えない1万2540円なのである。
欲を言うなら、車両購入時にシートが選択できるといいのだが、プラス1万2540円なら異論を述べる人はそんなに多くはないだろう。いずれにしても、近年のロードバイクのシートに微妙な印象を抱くことが多かった身としては、ノーマルで足着き性に配慮しながらまずまずの快適性と運動性を確保し、本来の資質が満喫できるハイシートを低価格で販売する手法に、大賛成したい気分なのだ。
「ハイ」ではなく「フラット」という言葉を使用するCL250/500用の純正アクセサリーシート(左)。その製品名には、高さを強調するのではなく「体格的にOKなら、ぜひともこちらを!!」という開発陣の意図が表れている…ような気がする。座面の高さはスタンダード(右)より30mmアップ。
シートの歴史に対する個人的考察:レーサレプリカブーム以降、薄くなっていった?
というわけで、ホンダの手法に感心した僕ではあるものの、改めて考えると、CL250/500のフラットシートに革新的な要素はない。少なくとも1950〜1980年代前半以前のバイクは、CL250/500のフラットシートとほとんど同様の形状=ウレタンが分厚くて座面が平らなシートが普通だったのだから。
【1968 ホンダ ドリームCL250】1960年代車の一例・初代のホンダCL250(1968年)。クッションの厚いフラットなシートを装備している。
そしてそういったシートが少数派になったきっかけは、1980年代のレーサーレプリカブームではないか、と僕は感じている。
もっとも、ブーム前半のレーサーレプリカのシートは意外に快適だったのだけれど、1980年代後半以降は薄いウレタンと前下がりの座面が定番化。サーキットや峠道での速さを重視したキャラクターや、低く構えたセパレートハンドル+高くて後退したステップとのバランスを考えれば、そういった変化は自然な流れだったのだろう。
また、1980年代後半以降のレーサーレプリカは、ウレタンを薄くした副産物として、シート高が一様に低くなった(一例としてホンダ車の数値を記すと、1981年型CBX400Fは775mm、1990年型CBR400RRは750mm)。もちろん、それは決して悪いことではないのだが…。
僕が微妙な印象を抱くことが多いのは、レーサーレプリカの次にブームとなったネイキッドのシートだ。車両全体は1980年代前半以前を思わせる雰囲気でも、日本のメーカーが日本を主なターゲットとして開発したネイキッドの大半は、シートだけがレーサーレプリカ風、ウレタンが薄くて座面が前下がりだったのである。
その背景には、アグレッシブなスタイルを好むデザイナーの感性や、レーサーレプリカブームを経験して低いシートに慣れたライダーからの要求があったようだが、1990年代以降の日本では「シートが高いバイクは売れない?」という風潮が徐々に広まり、一部の外国車の日本仕様はローシートを標準化。だからこそ、冒頭で述べたような印象を抱く場面に遭遇する機会が多くなったのだ……
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
モーサイの最新記事
窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]
きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]
改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]
125と155の基本的な違いを整理 ◆トリシティ125 メリット・原付二種なので維持費が155に比べ少しだけ安い・燃費性能が高く、毎日の通勤でも財布に優しい デメリット・高速道路が走れないため行動範囲[…]
「お金も時間もありそうなのに、なぜこんな天気の良い日にツーリングにも行かず、用品店に来ているんだろう?」という疑問 都内の某大手バイク用品店の駐輪場にて。今日も「なぜ来ているのかわからない?」ようなバ[…]
最新の関連記事(CL250)
ホンダCL250/Eクラッチの概要を知るなら… 車両の基本スペックと価格、そしてマイナーチェンジの詳細を報じたニュース記事を見よう。2025年10月24日に発売された新型CL250は、Eクラッチ搭載モ[…]
抜群に上手い半クラッチ制御、しかも再現性は完璧 正直言って驚いた。兄弟車であるレブル250で先行してデビューしていた250ccクラスのHonda E-Clutch仕様だが、10月に発売されたCL250[…]
250ccクラスは16歳から取得可能な“普通二輪免許”で運転できる バイクの免許は全部で7種類ある。原付(~50cc)、小型限定普通二輪(~125cc)、普通二輪(~400cc)、大型二輪(排気量無制[…]
レブル250ではユーザーの8割が選択するというHonda E-Clutch ベストセラーモデルのレブル250と基本骨格を共有しながら、シートレールの変更や専用タンク、マフラー、ライディングポジション構[…]
シュアラスターの「バイク洗車図鑑」 バイクが違えば洗い方も変わる! 車種別の洗車情報をお届けするシュアラスターの「バイク洗車図鑑」、今回はホンダCL250を洗車します。 洗車ポイントは“黒い部分をしっ[…]
人気記事ランキング(全体)
きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]
バイクとクルマの“いいとこ取り”を目指したパッケージング Lean3の最大の特徴は、そのコンパクトなサイズとモビリティとしての立ち位置だ。全長2470mm×全幅970mm×全高1570mmという車体サ[…]
待望の「ドア付き」がついに入荷、カラーは全6色展開へ ビークルファンが販売する「アーバントライカー(URBAN TRIKER)」は、フロント1輪・リア2輪の電動トライクだ。以前から存在したモデルだが、[…]
前年のマイナーチェンジでデザインも装備も最新世代 ホンダが2026年型「X-ADV」を発表、カラーリング変更とともにモノトーンとトリコロールそれぞれ1万6500円プラスの価格改定した。フラットダートく[…]
待望の4気筒DOHC、クラス最強の心臓部 Z400FXが登場する以前、400ccクラスは2気筒モデルが主流となっていた。メーカー側も「400なら2気筒で十分速い」という姿勢を見せていた時代である。しか[…]
最新の投稿記事(全体)
「本物」だけが許されたカフェレーサースタイル 昨今のネオクラシックブームにおいて、「カフェレーサー」を名乗るモデルは数あれど、トライアンフほどその称号が似合うメーカーはないだろう。ロッカーズ全盛期の1[…]
なっちゃんがモタサイでもっと見れる! 一般社団法人日本二輪車普及安全協会は元AKB48のメンバーで、現在はマルチタレントとして活躍中の平嶋夏海(ひらじまなつみ)さんが、2026年より「JAPAN RI[…]
窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]
ブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE(スズキ ファンズ ガレージ)」 スズキが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出品概要を発表した。モーターサイクルショーのスケジュール[…]
リッタークラスでサーキットを目指す過激なコンセプト! カワサキは2000年まで、フラッグシップとして世界最速に君臨するのが、半ばブランドのこだわりに近い歴史を歩んでいた。 しかしそれはサーキットで勝負[…]
- 1
- 2


![ホンダCL250/500|純正フラットシート|[バイク雑学] ホンダ新型CL250/500の純正フラットシートから、国産バイクのシート&足着き性の変遷を考察【1980年代以降、薄く低く?】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/th_MW_00046-768x512.jpg)
![ホンダCL250/500|スタンダードシート|[バイク雑学] ホンダ新型CL250/500の純正フラットシートから、国産バイクのシート&足着き性の変遷を考察【1980年代以降、薄く低く?】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/th_CL250_025-768x512.jpg)
![ホンダCL250/500|純正フラットシート装着車|[バイク雑学] ホンダ新型CL250/500の純正フラットシートから、国産バイクのシート&足着き性の変遷を考察【1980年代以降、薄く低く?】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/th_MW_00034-768x512.jpg)
![ホンダCL250/500|スタンダード|[バイク雑学] ホンダ新型CL250/500の純正フラットシートから、国産バイクのシート&足着き性の変遷を考察【1980年代以降、薄く低く?】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/th_CL250_002-768x512.jpg)
![ホンダ ドリームCL250|[バイク雑学] ホンダ新型CL250/500の純正フラットシートから、国産バイクのシート&足着き性の変遷を考察【1980年代以降、薄く低く?】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/th_HONDA_CL250-1-768x512.jpg)