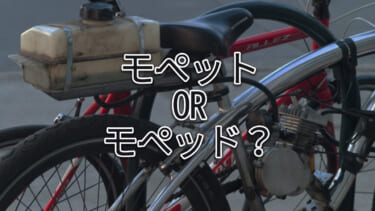●文:[クリエイターチャンネル]Peacock Blue K.K.
バイクごとの高速道路ルールは?
バイクは道路交通法上、大型自動二輪(大型二輪)/普通自動二輪(普通二輪)/原動機付自転車(原付)の3つに区分されます。50cc以下が原付、原付超え400cc以下が普通自動二輪、そして、400ccを超える排気量のモデルはすべて大型自動二輪となります。
一方、道路運送車両法においては、排気量が50cc超から125cc以下のものは「原付二種」と呼ばれます。原付二種と区別する意味で、排気量が50cc以下のものが「原付一種」とされます。
普通二輪/大型二輪と原付一種/原付二種、また原付一種と原付二種の間でも、公道を走行するうえでのルールに異なる点がいくつかあります。そのなかでも決定的に異なるのが、原付一種/原付二種は、高速道路の走行が認められていないことです。
原付一種と原付二種の両方とも高速道路を走行することはできないので、勘違いしないようにしましょう。
排気量125cc超のバイクであれば、一般的なクルマと同じように高速道路を走行することが可能ですが、125cc以下の原付二種と原付一種は、いかなる区間であっても高速道路に乗ること自体が禁止されています。
原付一種と原付二種は、一般道路の法定速度が大きく異なり、原付一種は30km/hまで、原付二種は60km/hまでとなっています。この“60km/h”という法定速度は、一般道における普通二輪/大型二輪/クルマと同等の数値であることから、原付二種が高速道路を走行できると勘違いしてしまうケースもあるようです。
排気量125cc超のバイクに関しては、基本的にすべての高速道路を走行することが可能ですが、首都高速の一部の区間などではタンデム走行(二人乗り)が禁止されているなど、気をつけるべき点もあります。
首都高では年間400件も? 高速道路の“誤進入”
しかし、原付一種や原付二種による高速道路の誤進入は後を絶たず、毎年多く発生しています。SNSでも時折「高速道路に原付が!」といった趣旨の投稿が見られ、多くのユーザーが衝撃を受けています。
例えば首都高速では、歩行者や自転車も合わせて年間400件を超える誤進入が発生しています。これはあくまでも首都高速が確認できた件数であるため、未確認の事例も含めるとその数はさらに多くなると見られます。
そして、原付による誤進入はこのうちの約86%に及びます。これは1日に1件程度のペースであり、原付による誤進入がいかに多いかがわかります。首都高速やNEXCO各社では、看板や横断幕、カラー舗装などで出入口を強調するなどさまざまな誤進入対策を講じていますが、原付による誤進入は後を絶ちません。
その背景には、スマートフォンの普及も関係しているようです。スマートフォンなどのナビアプリに従って走行し高速道路に誤進入してしまったという事例は意外に多く、首都高速における自転車や原付の誤進入の約4割はこれが要因になっているといいます。
こうした危険を避けるため、原付に乗っている際にナビアプリを活用する場合は、あらかじめ高速道路の案内を避けるように設定しておく必要があります。そのうえで、ナビアプリの指示だけを頼りにするのではなく、標識や道路標示をしっかりと確認するように心がけなければなりません。
原付で高速道路に侵入した場合、通行禁止違反として2点の減点と5000円)原付二種は6000円)の反則金が科されることになります。
誤進入したらどうする?
では、万が一、原付一種や原付二種で高速道路に誤進入してしまった場合、どのように行動したら良いのでしょうか?
まず、高速道路に誤進入したことに気づいた場合、料金所やインターチェンジが近ければ安全に留意しながらそこまで走行し、係員に事情を伝えるようにしましょう。
本線上で料金所やインターチェンジなどが近くにない場合には、安全確認を行ったうえでバイクを路肩に止め、自身はガードレールの外側など安全な場所に退避します。その後、高速道路の路肩に設置されている非常電話を利用するか、自身のスマートフォンなどを活用して警察や高速道路の管制センターに連絡します。
非常電話は、本線の路肩に500m〜1km、トンネル内では200mの間隔で設置されています。受話器を取ることで自動的に管制センターなどに繋がるため、電話番号を入力する必要もありません。さらに、非常電話では電話をかけているおおよその位置も把握できるようになっているので、いま自分が高速道路のどのあたりにいるのか明確でなくても問題はありません。
電話が通じたら誤進入してしまった旨を伝え、電話先の指示に応じた対応を取るようにしましょう。基本的にはその場で待機し、係員や警察官が来るのを待つことになりますが、その際には常に身の回りの安全を確認しなければなりません。
待機する場所はガードレールの外が基本です。後続車に追突される危険があるため、乗車しながらの待機や、バイクに近い場所での待機は絶対にやめましょう。
高速道路に誤侵入した際にはまずは安全を確保して、可能であれば最寄りの料金所の係員に相談しましょう。
当然のことながら、誤進入にすぐに気が付いたとしても、逆走して一般道路に戻ることは絶対にしてはいけません。高速道路ではなにがあっても逆走はNGです。速度域の高い状態でほかのクルマと正面衝突した場合、命の保証はありません。
誤進入に気が付いた際には、まずは焦らず状況を把握し、落ち着いた行動を取るようにすることが重要です。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
最新の関連記事(Q&A)
スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]
Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]
[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]
振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]
オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]
人気記事ランキング(全体)
簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]
型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]
スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]
初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]
YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]
最新の投稿記事(全体)
PANDO MOTOが目指しているもの PANDO MOTOは、バイク文化が成熟しているヨーロッパ市場で高い評価を得ている、モーターサイクル・アパレルブランド。目指しているのは「快適さ、機能性、安全性[…]
60年代から続くデューンバギーの草分け的存在 デューンバギーといえば、本家本元はブルース・F・マイヤーズが創立した「マイヤーズ・マンクス」ということに。 オープンホイールのバギーは星の数ほど生まれまし[…]
【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]
スキルアップから大型デビューまで、ライダー必見のイベント目白押しだ! 那須モータースポーツランドでは、毎年数々のイベントを開催!日頃の安全運転に役立つ「ライディングスクール」や、普通自動二輪免許で大型[…]
NMAX155が装備している電子制御CVT“YECVT”とはなんぞや? エンジン回転域で吸気バルブのカムプロフィールを切り替えるVVAやアイドリングストップ、トラクションコントロールシステムなどなど。[…]
- 1
- 2