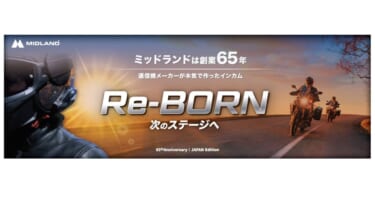●文:モーサイ編集部(石橋寛)
ヘルメットをどう持ち運ぶ? 購入時に付属の“保存袋”はお出かけ向きじゃないような…
ライダーにとって、ヘルメットは身に着けて移動するものと相場は決まっていますが、ときおり電車での移動や自転車でもって教習所に通うなどという場面も。はたまた、タンデムツーリングに出かける際、後席に座る方(いわゆるパッセンジャー)を迎えに行くなどというシーンでも、ヘルメットを持参する必要が生じるかもしれません。そんな場合は、たいていはヘルメットを買った際に付属してきた保存袋を使ったりするのがデフォルトでしょう。
しかしながら、あの保存袋とやらは、名前の通り保存しておくには適しているのでしょうが、持ち運びにはやや不便。なんとなれば、ヒモでぶら下げることになり「スイカじゃないんだから」と自らに突っ込みを入れる方すらチラホラと。
「ヘルメットバッグ」と検索すると、ナゾのトートバッグが大量にヒット!?
そこで、ヘルメットが入るバッグを買ってもいいかなと、「ヘルメットバッグ」と検索してみると、出るわ出るわ、“俺が探してるのはこれじゃない”感マシマシなバッグ。大きなトートバッグのようなカタチです。
たしかにオシャレだし大ぶりな袋モノだから、形状によってはヘルメットも入ることもあるかもしれませんが、スクエアなスタイルや、担げそうもないちょっとした手提げハンドルなど、およそライダー向けには見えません。
一体、どうしてこれが「ヘルメットバッグ」と呼ばれているのか、不思議に思う方も少なくないでしょう。
トートバッグ風「ヘルメットバッグ」の誕生は、1950年代のアメリカ空軍
じつは、このトートバッグ風ヘルメットバッグはアメリカのミリタリーグッズに端を発しているもの。その来歴をちょっとだけご紹介しましょう。
1950年代、朝鮮戦争時にアメリカ空軍(US AIR FORCE)が正式に組織された際、パイロットがハードヘルメットを装着するようになりました。ハードヘルメットには強い日差しをカットしてくれるサンバイザーや、高高度向け酸素マスクといった装備があったため、空軍の装備課が「やっぱ、なんかバッグにいれたほうが良さげ」と考えたとしても妥当でしょう。
ちなみに、ハードヘルメット以前は、レザーでイヤーマッフルがついた“飛行帽”でしたから、バッグやケースの必要性はそれほど高くなかったのでしょう。
で、最初に支給されたヘルメットバッグは、いわゆる普通のトートバッグ。ナイロン製で、当時の写真を見ればわかりますが、いかにもミリタリーなテイストで少々安っぽい。これでヘルメット大丈夫か? と思わず心配になってくるほど。それでもシンプルで丈夫そうな印象で「これはこれでアリ」と思わせてくれる仕上がりです。
その後、空軍で好評だったのか、陸/海軍でも「ヘルメットバッグ」が正式備品となりました。朝鮮戦争が終結し、アメリカがベトナム戦争に介入したころですから、1960年代ということですね。
そして1970年代、現代に生き残るあのカタチに
で、トートバッグだったスタイルが、今度はちょっと大きめのきんちゃく袋に変わりました。現代のいわゆる「ヘルメット保存袋」とさして変わらないスタイルですが、当時は陸海空軍とも兵士向けバッグが充実していたらしく、このきんちゃく袋はバッグインバッグとして活用されていたようです。そして、カラーもいわゆるアーミーグリーン(セージグリーン)へと変更。ミリタリー感が上がってきました。
そして1970年代、ベトナム戦争が終わってからのヘルメットバッグこそ、検索するとたくさん出てくる“あのカタチ”へとモデルチェンジ。おおむねトートバッグに近いものですが、バッグの身頃には大きなポケットが装備され、支給される日用品がどっさり入る仕様です。また、容量も上がっているようで、朝鮮戦争後も進化を続けているパイロットヘルメットの大型化にも対応しているとのこと。それにしても、シンプルというか無骨なスタイルなのに、ファッションシーンでこれほどウケて、後にスタンダード化するとは、最初の備品課担当者は夢にも思わなかったことでしょうね……
※本記事は2022年8月24日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
モーサイの最新記事
ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]
新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]
十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]
ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]
窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]
最新の関連記事(バイク雑学)
元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]
なぜ「ネズミ捕り」と呼ぶのか? 警察によるスピード違反による交通取り締まりのことを「ネズミ捕り」と呼ぶのは、警察官が違反者を待ち構えて取り締まるスタイルが「まるでネズミ駆除の罠のようだ」と揶揄されてい[…]
交通取り締まりは「未然に防ぐため」ではなく「違反行為を探して検挙するため」? クルマやバイクで運転中に「なんでそんな所に警察官がいるの?!」という運転者からすれば死角ともいえる場所で、交通違反の取り締[…]
ホコリや汚れを呼ぶ潤滑スプレー 鍵を差すときに動きが渋いなーとか、引っ掛かるなーと感じたことはありませんか? 家の鍵や自転車の鍵、倉庫の南京錠など、身の回りにはいろいろな鍵がありますが、屋外保管しがち[…]
きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]
X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]
最新の投稿記事(全体)
つながらなければ意味がない!「MIDLAND Re-BORN(リ・ボーン)」を実施! 創業65周年という節目を迎え、MIDLAND(ミッドランド)が掲げたスローガンは「MIDLAND Re-BORN([…]
リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]
HBG-065 カフェメッシュグローブ:人気モデルを現代の技術で再設計 デイトナのオリジナルブランド「ヘンリービギンズ」で高い支持を得ていた「DH-609」を現在の技術で再設計したメッシュグローブ。 […]
移動手段の枠を超えた“相棒”、“遊び心”、“洗練されたスタイル”を提案 ヤマハの大阪・東京・名古屋モーターサイクルショー出展概要が明らかになった。「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」「第5[…]
最大の衝撃! 製品登録で「保証期間が最長1年追加」の大盤振る舞い 今回の目玉は何と言ってもこれだ。購入したB+COMをサイトに登録するだけで、通常1年の製品保証が最長でさらに1年追加される。 精密機器[…]


![ヘルメット保存袋|[バイク雑学] ヘルメットが入らないのに、なんで“ヘルメットバック”なの? 【米空軍発祥のミリタリーアイテム】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/th_C2hrfDMVIAA909U.jpg)
![ヘルメットバッグ|[バイク雑学] ヘルメットが入らないのに、なんで“ヘルメットバック”なの? 【米空軍発祥のミリタリーアイテム】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/th_122219144-768x1157.jpg)
![初代軍用ヘルメットバッグ|[バイク雑学] ヘルメットが入らないのに、なんで“ヘルメットバック”なの? 【米空軍発祥のミリタリーアイテム】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/65d600b751cdf605f17f032b28ba75da-768x942.jpg)