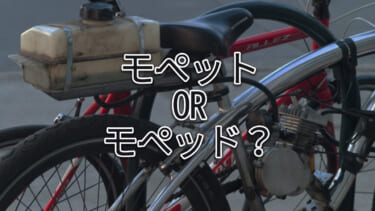●文:ライドハイ編集部(根本健)
きっかけはNR500の敗退。2スト最後発の歴史に残る突撃ぶり
1980年代の2ストレプリカ時代を知るファンにとっては、1988年式ホンダNSR250Rといえば、史上最強の2スト市販公道マシンに位置づけられる頂点マシンだろう。
その完成度の高さ、それも他を圧倒して寄せ付けない圧倒的な強さとパーフェクトさを得るまで、まっしぐらに駆け抜けた開発スピードの凄まじさが語り草でもある。
そもそものきっかけは、ホンダが1978年に世界GPへの復帰を宣言して、翌1979シーズン終盤から走り出したNR500にある。
当時の世界GP頂点は500ccクラス。2ストローク4気筒のヤマハYZR500やスズキRGΓが凌ぎを削っていた。それに対してホンダは、かつて1960年代にもそうであったように、シンプルな構造でパワーを稼ぎやすい2ストロークではなく、高度なメカニズムを駆使した技術力で闘う4ストロークで挑戦しようとしたのだ。
しかし、2万rpm回しても通常のバルブ面積では2ストパワーに追いつかない。そこで捻り出したのが、気筒あたり吸気4本と排気4本の8バルブを収めるオーバルピストンだった。
ただ、2シーズンとちょっとを経ても、2スト勢に追いつかない。
そこでまずは勝利を狙い、ついに2スト化を決意。ただ当時のホンダには、1974年のエルシノアという2スト単気筒モトクロッサーに端を発したCR125/250Rのレッドホンダモトクロスマシンしかノウハウがない。
そこでホンダはこの経験から、トップスピードを狙わずコンパクトでダッシュ力があって、トラクションの塊のようなマシンをほぼ1年で開発。それは4気筒ではなくモトクロスのノウハウを活かせる3気筒で、V型にシリンダー配列することで350ccクラス並みのコンパクトさを狙っていた。
このNS500はデビュー年からトップ争いに加わるポテンシャルを発揮、その手応えとノウハウから4気筒NSR500が誕生、歴史に残る快進撃が始まったのだ。
急遽開発した2スト250レプリカ3気筒は惨憺たる結果に
その頃はすでに、ヤマハRZ250でGPマシンのイメージをフィーチャーしたハイパー2スト250がブームに。ホンダは世界GP復帰後に2スト参戦も始めたことから、NS500と同じV型3気筒(ワークスマシンは前1気筒後ろ2気筒なのに対し、市販車は前2気筒で後ろ1気筒のレイアウト)のMVX250Fを開発した。
しかし、2ストロークで市販スポーツの歴史が皆無なことから、焼き付きなどの初歩的トラブル続出で、手堅いV型2気筒のNS250Rと交替を余儀なくされた……
※本記事は2022年7月8日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
ライドハイの最新記事
高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]
大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]
インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]
400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]
アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]
最新の関連記事(Q&A)
スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]
Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]
[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]
振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]
オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]
最新の関連記事(ビギナー/初心者)
きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]
徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]
改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]
「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]
「一時停止違反」に、なる!/ならない!の境界線は? 警察庁は、毎年の交通違反の取り締まり状況を公開しています。 最新となる「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等につい[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]
ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]
最新の投稿記事(全体)
初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]
Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]
最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]
伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]
ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]


![1979 ホンダNR500/CR250R/NS500|ホンダNSR250R[名車レビュー] 1988モデルは2スト究極の頂点。他を圧倒した凄まじい“復讐パワー”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/88nsr_2_20220613_01-768x551.jpg)