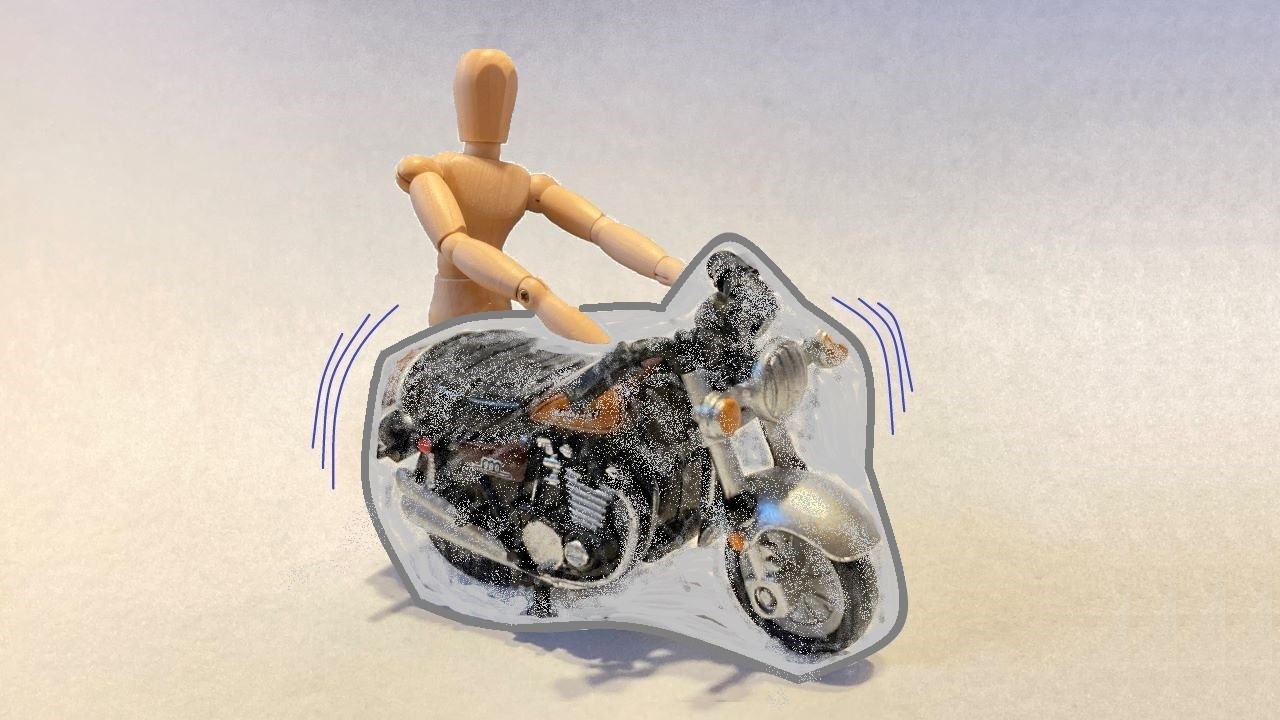
多くのライダーが使っている『バイクカバー』は、雨やホコリから愛車を守り、防犯上でも必須アイテム。……とはいえ、カバーをかけるが故のトラブルもなくはない。どのタイミングでカバーをかけて、どのタイミングで外すのが良いのだろうか?
●文:伊藤康司 ●写真:デイトナ
バイクが冷えてから掛けるのが基本だけど……
バイク用のカバーは猛烈に種類が多く、プライスも安価なモノから高価なタイプまで10倍ほども差がある。ありていに言えばピンからキリまであるワケで、ピンの方は高い耐水性や紫外線カット、蒸れにくいベンチレーションやチェーンロック用のホールなど非常に機能的に作られている。
とはいえ、どんなバイクカバーにも共通する注意点は「エンジンやマフラーが十分に冷えてから掛けること」。耐熱素材を使用するタイプもあるが、それでも走って帰ってすぐにカバーをかけるのはNG。エキゾーストパイプに触れた部分が溶けてペチャーっと張り付いてしまった……、なんて悲しい経験をした方もいるだろう。
だから気温の高い夏場なら、エンジンを止めて1時間くらい経ってから掛けるのが安全かも。しかし防犯上では、あまり長い時間「剥き出し」のまま停めておきたくないので、冷えるまでの待ち時間は悩ましいところでもある……。
バイクカバー
写真はデイトナのブラックカバー ウォーターレジスタント ライト(1万2100円~)。高い耐水圧を誇る特殊素材を採用し、湿気がこもらないエアベントも装備。マフラーの熱で溶けるのを防ぐ耐熱インナーが付属するが、充分に冷えるまでかけないのがよいだろう。
雨が降っていたらどうする?
天気が良ければ帰宅して充分に冷えてからカバーを掛ければ良いが、雨の日だったらどうする? 雨ざらしにはしたくないが、やはりエンジンやマフラーが冷えるまではカバーを掛けられない。雨で濡れるぶん、晴れた日より冷えるまで時間はかからないとはいえ……これも悩みどころ。
しかも「その後」に問題になるのが『湿気』。車体がビショビショに濡れた状態でカバーをかけるので、カバー内には当然湿気がこもる。ベンチレーションが付いていても、濡れた車体やカバーの内側が完全に乾くには相応に時間がかかるし、駐車している場所が水はけのよいコンクリートならまだ良いが、土や砂利だと地面からも湿気が上がってくる。そしてこの湿気が、サビやカビが発生する大きな原因になる。
気付いたらエンジンやホイールが粉を吹いたようにサビていたり、シート表皮に白や緑の染みのようなカビが生えてショックを受けた方もいるだろう。また近年のバイクは防水性が高いとはいえ、湿気がこもることで電気系の不具合が出ないとも限らない。
なので理想を言えば、雨が止んだらカバーを外してバイクをしっかりと乾かすことが大切だ(さらに理想を言えば、洗車して泥汚れなどを落としてから乾かす)。そしてカバーも開いて干して、裏側まで乾かしてから掛ける。……そんな時間はない! と怒られそうだが、あくまで理想の話だ。
実際はカバーをかけていないと防犯上よろしくないし、カバーを外したまま仕事に出るわけにもいかない。だから雨が止んだ後にバイクに関われるタイミングができた時に、速やかにカバーを外して車体の水気を拭き取り、短時間でもカバーを干し、そしてまたカバーを掛ける……のが現実的にできる最大限のケアだろう。それでもけっこう大変だ。
設置が可能なら「簡易ガレージ」がオススメ!
そんな「バイクカバー問題」は、ガレージがあれば解決する。……が、そんなのは当然だし、それが出来れば苦労は無い。それでは「簡易ガレージ」はどうだろうか?
簡易ガレージにもいわゆるビニールハウス的なタイプや、蛇腹に開閉するアコーデオン型など様々な種類があるが、いずれも最大のメリットは「バイクと非接触」なところだ。たとえば帰宅して完全に冷えていなくても(ある程度は冷えてから)マフラーに張り付いて溶ける心配は無いし、雨天時も比較的短時間で閉じて大丈夫だ。
湿気に関してはバイクカバー同様に開けて乾かすのが理想だが、閉めたままでも車体と非接触で空間があるぶん蒸れにくいし乾くのも速いだろう。
またバイクカバーは風でバタつくと、車体表面に付着した砂ボコリが「ヤスリがけ」するように細かな傷をつけてしまうが、簡易ガレージだとその心配がない。これも非接触ならではの大きなメリットのひとつだ。
簡易ガレージ
写真はデイトナのMCハウス1700(車体2台分:5万5000円。1台用のMCハウス1300:4万4000円もあり)。奥行2600mmで大型バイクも収容可能。湿気対策のベンチレーションも装備する。
比較的コンパクトなので、自宅の庭や駐車スペースの脇などに設置できる可能性もある。プライス的には数万円台の製品が多く、バイクカバーよりは高額だがメリットを考えたらコストパフォーマンスは高い。
設置するにはアンカーやボルト等で地面に固定が必要な場合もあるので、マンションの駐輪場や賃貸住宅の駐車場に設置したい場合は、必ず事前に確認・許可を取ろう。
スペース確保と設置許可が取れるなら、バイクライフにおいて簡易ガレージはかなりオススメなアイテムだ。
※本記事は“ミリオーレ”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
あなたにおすすめの関連記事
愛車がガソリン1リットルで何キロ走れるか知ってる? インジェクション化され高性能なECUで制御される最近のバイクは、瞬間燃費や残燃料での走行可能距離を表示する車種も少なくない。そんなバイクなら燃料タン[…]
国内最大排気量、だからエライに決まってる!? 1969年、ホンダCB750FOURの登場は、世界はもちろん日本でもとてつもない衝撃だった。それだけに開発中は、国内外のライバル社に察知されないよう、CB[…]
1980年代初頭まで、カウリングが無いのが普通だった 市販量産車初の4気筒エンジンを搭載したホンダのCB750Fourや、もはやレジェンドとして君臨するカワサキZ1などの威風堂々としたスタイル。そして[…]
スイングアーム式のリヤサスペンションが2本ショックの始まり 市販車もモノクロスサスペンションを装備 リンク式でさらに性能アップしたサスペンション 2本ショックとモノショック、それぞれの特徴は? そもそ[…]
ギヤチェンジにかける時間を短縮したい! ギヤチェンジはスロットル、クラッチレバー、シフトペダルの3カ所を、正確なタイミングで操作する必要がある。普段乗りでもそうだが、これがスポーツ走行やレースなら、よ[…]
最新の記事
- 配線不要ってマジか…! 車とバイクで使い回せる「ボタンゼロ」ドラレコが反則級すぎる【MAXWIN MF-V40】
- ヤングマシン2月の人気記事まとめ。ワークマンのコラボアイテムや次世代EVが話題独占!
- 伝説の冒険へ! 千里浜を目指すSSTR2026、過去最大規模で「平日枠」も新設
- 【2026年新製品】ワークマンが『名探偵コナン』と初コラボ! 980円Tシャツやポンチョなど全5アイテムが5月発売
- 世界GP王者・原田哲也のバイクトーク Vol.157「ついに開幕!! 1000cc&ミシュランタイヤ最後の年の見どころは?」
- 1
- 2
































