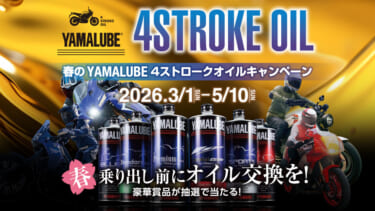バイクを乗り換える際は、“下取り”もしくは“買い取り”のどちらかの方法を取るのが一般的です。どちらも同じくバイクを売却する方法ですが、それぞれにメリット/デメリットがあり、どちらを選ぶべきかはバイクの状態などによって異なります。
●文:ヤングマシン編集部(ピーコックブルー)
“下取り”と“買い取り”の違いは? どちらを選ぶのがトクなのか?
下取り/買い取りの違いを簡単に言い表すと以下のようになります。
- 下取り:新たに商品を購入することを前提として、それまで使っていた商品を購入店で引き取ってもらい、新たに購入する商品価格から値引きなどの形で対価を受け取ること
- 買い取り:商品売却を前提として、買い取り業者が定めた価値を現金として受け取ること。
つまり、バイクの価値を“値引き”として還元するのが下取りで、“現金”として還元するのが買い取りということです。
また、下取りは同じ店でバイクを購入することが前提となります。それに対して買い取りは、売却店舗と新たなバイクを購入する店舗が同一である必要はありません。
それ以上に大きな違いが売却価格。一般的には高値で買い取ってくれる買い取りを選ぶほうがお得に思えますが、下取りにもメリットはあります。
では、それぞれどのようなメリット/デメリットがあるのでしょうか?
◆下取りのメリット
- 乗り換え時の手間が省ける:新しいバイクの購入と古いバイクの処分が同時にできるため、店舗への訪問回数を減らせる
- バイクに乗れない期間ができない:新しいバイクの納車日まで乗り続けられるため、乗り換えがスムーズに行える
◆下取りのデメリット
- 下取り価格が安い:下取り価格は、市場価格を参考にした一般的な買い取り価格よりも安くなる場合がほとんど
- クーリングオフができない:契約後でも一定期間内であれば無条件で契約解除ができるクーリングオフは、下取りに適用されないため、手続き後はキャンセルできない場合がある
- 下取り価格が減額されるリスクがある:下取り契約から納車日までの間はバイクを使用できるが、その間に事故や故障があると下取り価格が減額される可能性がある
- バイクの状態によっては下取りができない:不動車/事故車/改造車など、著しく状態が悪いバイクは下取りを断られる場合がある
なお、下記に該当する人は下取りを選択するとよいでしょう。
- 新しいバイクを購入することが決定している
- 乗り換え手続きに手間や時間をかけたくない/かけられない
- 通勤/通学などで毎日バイクを利用し、かつバイク2台を置くスペースを確保できない
一方で買い取りのメリット/デメリットとしては、以下の内容が挙げられます。
◆買い取りのメリット
- 買い取り価格が高い:買い取り業者は買い取ったバイクを売りさばく仕組みが整っているため、下取りに比べて高値での買い取りが期待できる
- どのようなバイクでも買い取りしてくれる:下取りで断られるような状態が悪いバイクや動かないバイクであっても、不動車/事故車専門買い取り業者なら値段を付けて買い取ってくれる
◆買い取りのデメリット
- 乗り換え手続きが煩雑になる:古いバイクの売却手続きと、新しいバイクの購入手続きを別々の店で進める場合は、それだけ乗り換えに手間がかかる
- 買い取り業者選びが難しい:業者によって買い取り価格が大きく異なるため、買い取り業者選び/妥協点の判断が難しくなる
- 売却交渉に手間がかかる:複数の業者に査定を依頼するほど高値で売却しやすくなるが、査定業者を増やすほど交渉に時間/手間がかかる
また、買い取りを選択したほうがいい人として、以下の内容に該当する場合が挙げられます。
- バイクの購入を急いでいない
- できるだけ高値でバイクを売りたい
- 一時的に2台以上のバイクを保有できる
売却予定となるバイクの相場を知っておくと、下取り/買い取りの判断がしやすい
上述のメリット/デメリットをふまえたうえで、以下の3点に注目して下取り/買い取りを決めるとよいでしょう。
- 乗り換えスケジュール
- 買い取り価格
- バイクの状態
乗り換え手続きに手間や時間をかけたくない/かけられない場合は、よほど安く買い叩かれないかぎりは下取りの一択。現在乗っているバイクをより高く売りたいのであれば、迷わず買い取りを選択しましょう。
ただ見極めが難しいのは、バイクの状態について。高値で売れる価値あるバイク/値段が付かないようなボロボロのバイクは買い取りを選んだほうがよいでしょう。
一方で買い取り相場が安いバイクは、わずかな金額で売却するぐらいなら下取りに出して乗り換えの手間を省いたほうがお得とも言えます。大型バイク店などが実施する期間限定の下取りキャンペーンなどを活用すれば、多少の下取り価格アップも狙えます。
いずれの場合でも、乗っているバイクの市場相場を知っておくことが、下取り/買い取りを決めるよい判断材料になります。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
最新の関連記事(バイク雑学)
BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]
元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]
なぜ「ネズミ捕り」と呼ぶのか? 警察によるスピード違反による交通取り締まりのことを「ネズミ捕り」と呼ぶのは、警察官が違反者を待ち構えて取り締まるスタイルが「まるでネズミ駆除の罠のようだ」と揶揄されてい[…]
交通取り締まりは「未然に防ぐため」ではなく「違反行為を探して検挙するため」? クルマやバイクで運転中に「なんでそんな所に警察官がいるの?!」という運転者からすれば死角ともいえる場所で、交通違反の取り締[…]
ホコリや汚れを呼ぶ潤滑スプレー 鍵を差すときに動きが渋いなーとか、引っ掛かるなーと感じたことはありませんか? 家の鍵や自転車の鍵、倉庫の南京錠など、身の回りにはいろいろな鍵がありますが、屋外保管しがち[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]
ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]
最新の投稿記事(全体)
憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]
8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]
なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]
平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]
BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

![バイクディーラーの店頭写真|[バイク雑学] “下取り”と“買い取り”の違いとは? 乗り換えの際におすすめなのはどちら?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/photo-1-4-768x512.jpg?v=1721717535)
![バイク買い取りのイメージ画像|[バイク雑学] “下取り”と“買い取り”の違いとは? 乗り換えの際におすすめなのはどちら?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/photo-2-4-768x576.jpg?v=1721716757)