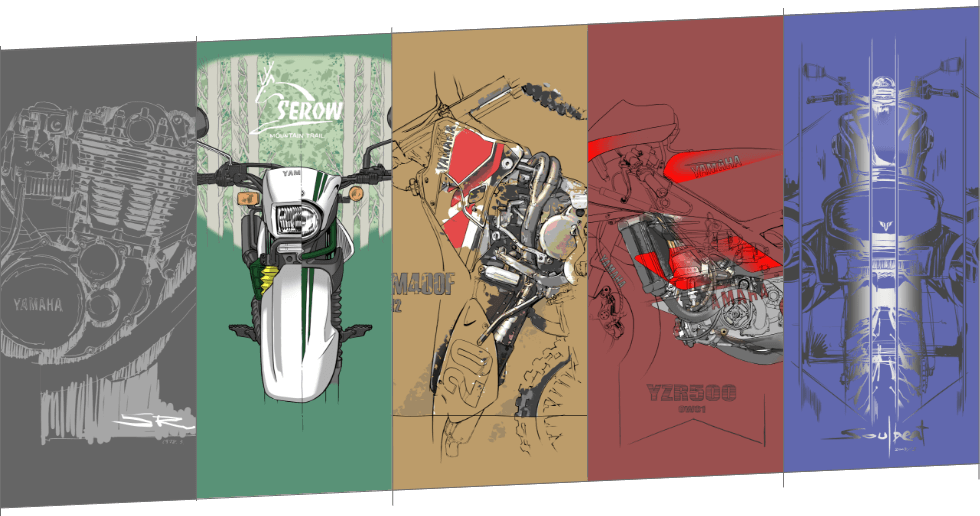ヤマハは欧州で、新型「R7(日本名:YZF-R7)」を発表した。R1由来のIMUを搭載し、バンク角対応型のトラクションコントロールやスライドコントロールを含む電子制御ライダーエイドを獲得。車体もアップグレードを受け、ライダーはあらゆるスキルレベルに合わせてパフォーマンスを堪能できるようになった。
●文:ヤングマシン編集部(ヨ)
スポーツライディングの登竜門へ、新たなる役割を得たR7が長足の進化
ミラノで開催中のEICMA 2025でヤマハの新型「YZF-R7(欧州名:R7)」が登場した。2026年から従来のワールドスーパースポーツ300選手権に代わり、ヤマハR7やアプリリアRS660、スズキGSX-8R、カワサキNinja ZX-4Rなどが参加できる『ワールドスポーツバイク選手権』が始まる。これに向けてR7が電子制御を中心に大きなアップデートを受けた。
といっても、幅広いライダーに扱いやすいキャラクターはそのままに、フルアジャスタブル化かつ軽量化された倒立フロントフォークやスピンフォージドホイールなどを新採用。素性のいいCP2エンジンの特性も活かしながら、新たにR1譲りのIMU(慣性計測ユニット)や電子制御スロットルを採用し、最高峰スーパースポーツに並ぶほどの制御デバイスを獲得している。
これらにより、公道とサーキットで最適なパフォーマンスを発揮しつつも、リーズナブルな価格帯は維持するというから驚きだ。
YZF-R7[2026 EU model]Anniversary White
R7は2024年に導入されたFIM女子世界選手権のワンメイクレースマシンに指定され、ほどよい価格とパフォーマンス、壊れにくいチューニングなどでミドルウェイトスーパースポーツの重要性を広く認知させたが、新型R7はさらにこの流れを加速するものになる。
R1の血統を受け継ぐ先進の電子制御を“全て”採用
新型R7の最大の特徴は、ヤマハのフラッグシップスーパースポーツ「R1(日本名:YZF-R1)」で開発されたテクノロジーをミドルクラスに惜しみなく投入した点だ。
まずはR1由来の6軸IMUを搭載。これにより前後/上下/左右の加速度とピッチ/ロール/ヨーの角加速度を常に測定し、そのデータをECUでリアルタイム処理することでライダー支援機能を拡充する。これに新採用の電子制御スロットルを組み合わせることで獲得したのは以下のシステムだ。
- バンク角対応トラクションコントロールシステム(TCS):3段階で利用可能。
- スライドコントロール(SCS):リヤのスライドを検知し、エンジン出力を調整する(3つのサポートレベル)。
- リフトコントロール(LIF):加速中のウイリーを制御。
- ブレーキコントロール(BC)システム:ブレーキング中にリーンしている場合のスライドを検知し、ブレーキ圧を変更して補正。
- エンジンブレーキマネジメントシステム(EBM):サーキット走行中にエンジンブレーキを2つのレベルで増減できる。
- バックスリップレギュレーター(BSR):過度なエンジンブレーキや低グリップ状況での後輪ロックアップを制御。
- ローンチコントロールシステム(LC):静止状態からの加速を最適化。
これらのライダー支援機能は、経験の浅いライダー向けの保護的な設定から、サーキット走行を頻繁に行うライダーに向けた高度なサポートまで、ライダーのスキルに合わせて最適なレベルのサポートを設定することが可能。さらに、リヤのABSにはOFFモードもあり、現代の4ストロークマシンでのサーキット走行では必須ともいえる『後輪からの減速』を最大限に得ることが可能だ。
YZF-R9などの上位機種と同じ第3世代クイックシフターを獲得した。
また、前述の電子制御スロットル(YCC-T=ヤマハ チップ コントロール スロットル)の採用により、689cc並列2気筒エンジンから全回転域でよりスムーズなトルクとリニアなフィーリングを得ることが可能に。また、YCC-Tの導入によってR9に続く形でヤマハ ライド コントロール(YRC)のカスタム設定も作成可能になった。
加速/減速中を問わずシフトアップ/ダウンが可能な第3世代クイックシフトシステム(QSS)も導入し、シフターのアップ/ダウンを個別に2段階+OFFでセッティング可能。さらに、より滑らかでスポーティなギヤチェンジを実現するため、1~3速のドッグギヤのかみ合い歯数が5枚から6枚に増加している。4~6速についてもドッグギヤの角度が変更され、スムーズなギヤチェンジに繋がっている。
シャシーと足まわりも『よりダイナミックなハンドリング』を目指して見直し
新型R7はより洗練されたダイナミックなハンドリング体験を目指し、安定性向上のための剛性強化が図られた。
フレームはパイプのレイアウト、直径、厚さ、補強など、ほぼ全ての要素が変更あるいは最適化。その結果、捻じれ剛性、縦剛性、横剛性が全て向上しつつ、従来モデルと同じ重量を維持している。剛性向上に対応するため、センターブレースにはプラスチックカバー付きの鋼板が使用されている。
スイングアームも再設計され、路面からのより明瞭ないフィードバックを提供。新設計のトリプルクランプ(三つ又)はフラッグシップのR1やR9に近い外観になるとともに、剛性フィーリングが最適かされた。
φ41mm倒立フロントフォークには従来のスチール製からアルミ製に変わったピストンロッドが採用され、全体の重量を350g削減。新作フロントフォークはプリロード/伸び側減衰力/圧側減衰力が調整可能なフルアジャスタブルだ。
スイングアーム、ホイール、装着タイヤの全てが刷新された。
そして足元には、R9などが採用しているスピンフォージドホイールをR7として初採用。これによって大幅な軽量化を達成しただけでなく、ホイールの慣性重量を削減され、いっそう俊敏なハンドリングを獲得している。装着タイヤはブリヂストンのバトラックスハイパースポーツS23だ。
これらのシャシー改善により、R7はよりダイレクトなコーナリング、改善された接地感、そして全体的に穏やかな車体フィーリングを備えた、より“振り回しやすい”ダイナミックなハンドリングを提供する。
ライディングポジションはより“動きやすい”設定に
ライダーのインターフェイス、いわゆる“ライダーが触れる部分”も一新された。ハンドルバーは位置が変更され、上半身の動きの自由度が増した。燃料タンクも再設計され、ライダーは前後の体重移動がよりしやすくなった。そしてシート高は従来の835mmから830mmへと低くなり、小柄なライダーもアクセスしやすくなっている。
フットペグ(ステップバー)にはR1のものが採用され、コーナリング時の下半身の安定性が向上した。
5インチフルカラーTFTディスプレイを採用
公道の表示テーマは4つ。トラック表示モードではラップタイムとタコメーターが大きく目立つ表示になる。
メーターは従来の反転表示フルLCDから5インチフルカラーTFTに変更され、Y-TRAC Revアプリと連携可能に。これはライダーにプロレーサーのような体験を提供するもので、ラップタイムやセクタータイムに加え、バンク角、エンジン回転数、トラクションコントロールのサポートレベルといった詳細なマシンデータを記録・分析できるという。さらに、ピットクルーが走行中のライダーのダッシュボードにメッセージを送れる「バーチャルピットボード」というオプションも提供されるというから驚きだ。
TFTディスプレイには4つの行動をテーマにした表示モードと、レーススタイルのトラック専用モードが搭載されているほか、クルーズコントロールシステム(3速以上、40km/h以上で作動可能)や任意設定可能な速度リミッターも採用。また、前述のトラックアプリのほか、MyRideアプリに接続することで着信を表示、またGarmin StreetCrossアプリを通じて完全なナビゲーションシステムも利用可能だ。
デザイン刷新とともに70種年記念カラーも登場
新型R7は、MotoGPマシンのYZR-M1からのデザインエッセンスを維持しつつ、カウリングの幅をスリムかつ滑らかにすることで前面投影面積を減らし、さらなる空力向上を達成。ヘッドライトはレンズを変更することで、これも空力向上に貢献。ヘッドライト下のチンスポイラーは形状変更を受け、ラジエターにより効率的に導風できるようになった。
70周年記念カラー(アニバーサリーホワイト)は音叉マークがゴールド仕様。
フロントウインカーはバックミラーに統合され、見た目にも空力的にもスッキリ。エマージェンシーストップシグナルは変わらず標準装備だ。
そして、2025年にヤマハが創業70周年を迎えたことを記念し、1999年のYZF-R7が採用していた象徴的なホワイト×レッドのスピードブロックパターンのカラーリングを採用。このカラーは当時のスーパーバイク世界選手権や鈴鹿8耐でも暴れまわったもので、今年の鈴鹿8耐などでも70周年記念カラーとしてファクトリーマシンが纏っていたことをご記憶の読者もいらっしゃるだろう。
このほか、ヤマハのイメージカラーである“アイコンブルー”と、全身黒の“ミッドナイトブラック”を揃え、全3色のカラーオプションが用意される。欧州での発売は2026年4月なので、日本への導入は夏以降だろうか。多くのライダーが楽しめそうな1台だけに、早期導入を期待したい。
YAMAHA YZF-R7[2026 EU model]
主要諸元■全長2070 全幅725 全高1160 軸距1395 最低地上高135 シート高830(各mm) 車重189kg(装備)■水冷4ストローク並列2気筒DOHC4バルブ 689cc 73.4ps/8750rpm 6.9kg-m/6500rpm 変速機6段 燃料タンク容量14L■ブレーキF=φ298mmダブルディスク+4ポットキャリパー R=φ245mmディスク+1ポットキャリパー タイヤサイズF=120/70ZR17 R=180/55ZR17 ※諸元は欧州仕様
YAMAHA YZF-R7[2026 EU model]Anniversary White
YAMAHA YZF-R7[2026 EU model]Icon Blue
YAMAHA YZF-R7[2026 EU model]Midnight Black
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 新型スーパースポーツ)
2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]
ヤマハの3気筒スーパースポーツに早くも2026年モデル! ヤマハは国内向けモデルのYZF-R9を2025年10月30日に発売したが、早くも2026年モデルを発表。新色のスタンダードカラーは150万円切[…]
伝説の「OW-02」を彷彿とさせるヘリテージカラー 70周年記念カラーは、1999年に登場したレース専用ホモロゲーションモデル「YZF-R7(OW-02)」がモチーフとなっている。 白と赤を基調とした[…]
125ccクラスは16歳から取得可能な“小型限定普通二輪免許”で運転可 バイクの免許は原付(~50cc)、小型限定普通二輪(~125cc)、普通二輪(~400cc)、大型二輪(排気量無制限)があり、原[…]
16歳から取得可能な普通二輪免許で乗れる最大排気量が400cc! バイクの免許は原付(~50cc)、小型限定普通二輪(~125cc)、普通二輪(~400cc)、大型二輪(排気量無制限)があり、原付以外[…]
最新の関連記事(新型大型二輪 [401〜750cc] | ヤマハ [YAMAHA])
2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]
伝説の「OW-02」を彷彿とさせるヘリテージカラー 70周年記念カラーは、1999年に登場したレース専用ホモロゲーションモデル「YZF-R7(OW-02)」がモチーフとなっている。 白と赤を基調とした[…]
カワサキ KLR650:質実剛健を貫くビッグシングルのタフガイ カワサキの北米市場におけるロングセラー「KLR650」は、まさに質実剛健を地で行くモデルだ。心臓部には100mmという巨大なボアを持つ6[…]
TMAX生誕25周年! 特別装備満載の記念モデルが登場! ヤマハは、”オートマチックスポーツコミューター”という独自のジャンルを築き上げた「TMAX」の誕生25周年を記念し、特別仕様車「TMAX560[…]
欧州では価格未発表だが、北米では前年から200ドル増の9399ドルと発表 ヤマハは北米で新型「YZF-R7」を発表。欧州で発表された新型「R7」にモデルチェンジ内容は準じつつ、北米独自のカラーリングで[…]
人気記事ランキング(全体)
高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]
YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]
街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]
現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]
ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]
最新の投稿記事(全体)
もし、モンスターハンターの世界にSUZUKIがあったら 2026年2月22日に幕張メッセにて開催される「モンスターハンターフェスタ’26」に、スズキ×カプコンのカスタマイズド車が出品される。二輪のオフ[…]
リッター51.9kmの低燃費、735mmの低シートでユーザーに優しい ヤマハは、同社の原付二種スクーターで最も廉価な原付二種スクーター「ジョグ125(JOG125)」の2026年モデルを3月19日に発[…]
2026年モデル Kawasaki Z900RS SE に適合するTRICKSTAR製品の情報が確定! 世界耐久選手権(EWC)などで培ったレーシングテクノロジーをフィードバックす[…]
憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]
8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]
- 1
- 2